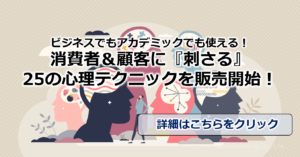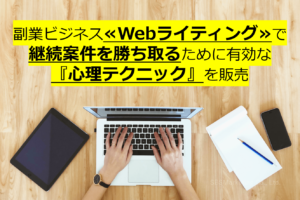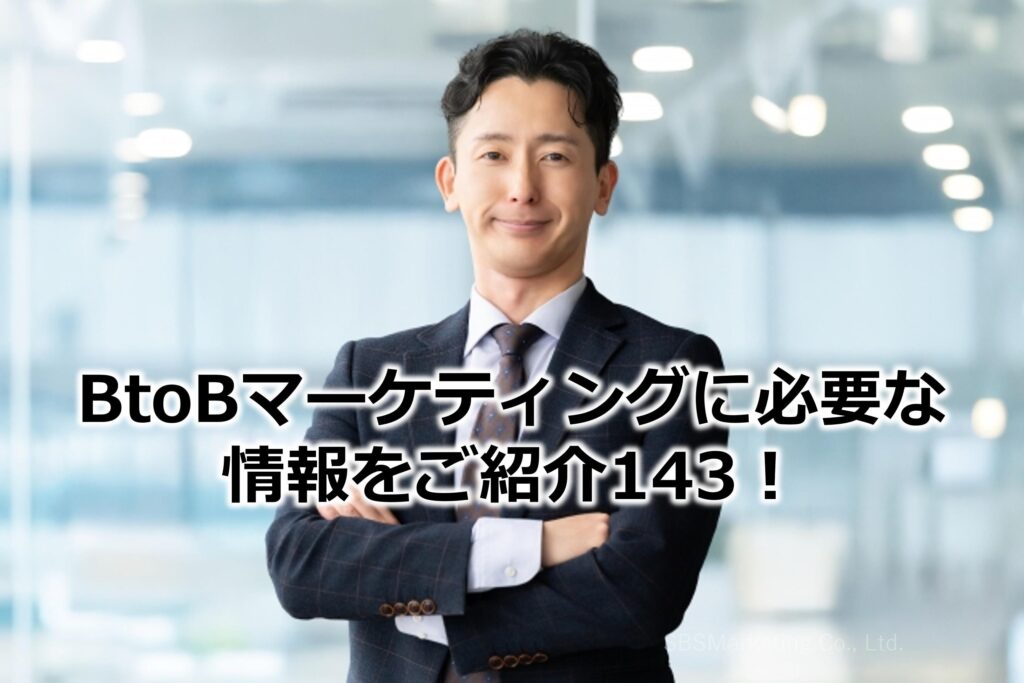「物事を簡単にするのは簡単だが、簡単にするのは複雑である」ということを意味する『メイヤーの法則』。
物事を「難しくしてしまう例」と「簡単にする例」、ビジネスシーンにおいて「物事を複雑化」してしまう原因、
タイムマネジメントへの活用方法や「複雑なことを単純化する」ために必要なコトについて解説しています。
『メイヤーの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『メイヤーの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『メイヤーの法則』とは?

「物事を簡単にするのは簡単だが、簡単にするのは複雑である」ということを意味する『メイヤーの法則(mayer’s law)』。
日常生活でもビジネスシーンでも、何か物事に取り組む際に、人はムダな要素や複雑さを加えてしまいがちであることを示した法則です。
「シンプル」なことをややこしくしてしまう人は、この『メイヤーの法則』に陥っているかもしれません。
提唱したのは?

この『メイヤーの法則』は、1842年にドイツの物理学者である ユリウス・ロベルト・フォン・メイヤー によって提唱されました。
メイヤーは、熱力学を研究する中で『カルノーの原理』を発見し、その法則から「複雑な物事ほどさまざまな要素が絡み合っているため、単純化することは難しい」ということを導き出しました。
物事を「難しくしてしまう例」と「簡単にする例」
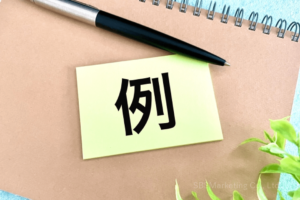
『メイヤーの法則』に基づく、日常生活やビジネスシーンにおける代表的な例は、以下のようなケースが挙げられます。
- 部屋の片付け
- ゲームのルール説明
- 数学の問題
- プレゼンテーション資料の作成
部屋の片付け

- 難しくしてしまう例:片付ける前に、何をどこにしまうか細かく決めようとすると、かえって時間がかかってしまう。
- 簡単にする例:「ジャンルが同じものをまとめる」「(とりあえず)不要なものを捨てる」というざっくりとしたルールで片付けを始めれば、効率的に進めることができる。
ゲームのルール説明

- 難しくしてしまう例:始める前にルールを事細かく説明してしまうと、やる前から聞き手は混乱してしまう。
- 簡単にする例:最初に大枠となる基本的なルールだけを説明し、プレイする中で細かなルールを説明すると、聞き手は理解しやすくなる(ゲームの内容によりますが)。
数学の問題

- 難しくしてしまう例:簡単な計算問題であるにもかかわらず、複雑な公式を使って解こうとすると、混乱してしまう。
- 簡単にする例:計算問題の基本的な公式である「四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)」だけを使うようにする。
プレゼンテーション資料の作成

- 難しくしてしまう例:「伝えたい」思いが強すぎて専門用語を用いたり、長尺な説明をしてしまうと、かえって内容が伝わりにくくなってしまう。
- 簡単にする例:誰でも知っている言葉で説明したり、短い時間で単純明快な資料を作成することで、受け手の理解度が高まりやすくなる。
ビジネスシーンで『メイヤーの法則』に陥ってしまう原因

「物事を簡単にするのは簡単だが、簡単にするのは複雑である」という『メイヤーの法則』に当てはまってしまうケースとしては、以下が挙げられます。
- システムやプロセスの複雑さ
- 商品やサービスの複雑さ
- コミュニケーションの複雑さ
- 変化を拒む慣習や社内ルール
システムやプロセスの複雑さ

ビジネスに用いられるシステムや、意思決定などのプロセスは、多くの部門や役職者が関与していたり、自社独自の(ネガティブな)慣習・社内ルールに基づくことがあり、結果として複雑になりがちです。
システムやプロセスが複雑であると、従業員の負担が増加し、運用時にミスが発生しやすくなってしまいます。
『メイヤーの法則』の観点でみると、システムは運用しやすい構造設計やマニュアルの整備、プロセスは単純化することが求められます。
商品やサービスの複雑さ

顧客や消費者に提供する商品が多機能であったり、サービスに多くのオプションが付随していると、かえって「使いにくさ」を感じてしまったり、混乱を招くことにつながるため、満足度を低下させるリスクが高まります。
『メイヤーの法則』の観点でみると、どういった機能が必要なのかを見極めて、「使いやすさ」を前提にした仕様やデザインを商品やサービスに反映していくことが求められます。
コミュニケーションの複雑さ

ビジネス規模が大きくなると、部門や役職者が増えたり階層に厚みが増すことから、組織内のコミュニケーションが複雑になってしまい、情報の伝達が遅れたり、誤解や齟齬が生じやすくなってしまいます。
『メイヤーの法則』の観点でみると、例えばツールの導入などでシンプルなコミュニケーションの仕組みを構築することが求められます。
変化を拒む慣習や社内ルール

ビジネスには常に変化が求められますが、長年根付いている慣習や複雑な社内ルールを変えることは反発を招くことがあり、容易ではありません。
『メイヤーの法則』の観点でみると、(簡単なことではありませんが)そういった慣習やルールを見直すことが求められます。
『メイヤーの法則』のタイムマネジメントへの活用方法

『メイヤーの法則』をタイムマネジメントに活用するための方法としては、以下の方法が挙げられます。
- タスクを「分割」する
- 「優先順位」をつける
- 「シンプル」な手法を取り入れる
- 「役割を明確化」する
- 日々の業務を「振り返る」
タスクを「分割」する

複雑なプロジェクトやタスクがある場合、ステップを踏めるよう「分割する」ことで、複雑さが薄れて取り組みやすくなり、進み具合(進捗)を確認しやすくなります。
「優先順位」をつける

簡単なことでも、同時に進めることは難しい場合があります。
そのため、「優先順位」をつけて、重要なことから取り組むことで、複雑なことに巻き込まれるリスクを減らすことにつながります。
「シンプル」な手法を取り入れる

複雑な手法やフローを介することは、やることを面倒にする一因になってしまいます。
そこで『メイヤーの法則』に従い、「シンプル」な手法を取り入れることで、効率的に進めることができます。
「役割を明確化」する

複数人で進めるプロジェクトの場合、コミュニケーション不足や齟齬、タスクの重複が起こりがちです。
複数人のチームで取り組む際には、各メンバーの「役割を明確化」して、誰がどのタスクに責任を持つのかを明らかにすることがポイントになります。
日々の業務を「振り返る」

『メイヤーの法則』の、簡単な(単純な)仕事を複雑にしてしまうことを回避するためには、日々取り組んでいる仕事を振り返り、自身の意志決定やそれに基づく行動を思い返すことで、複雑にしてしまった点を理解しやすくなり、繰り返しを回避することにつながります。
↓
この続きでは、『メイヤーの法則』に基づいた「複雑なことを単純化する」ために必要なコトについて解説しています。
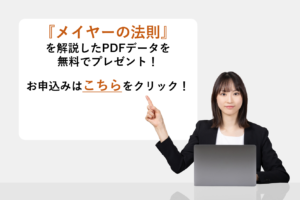 『メイヤーの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
『メイヤーの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『メイヤーの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。