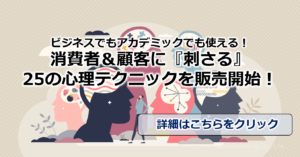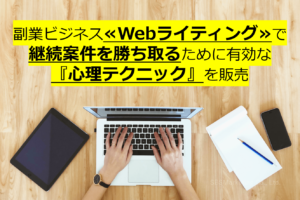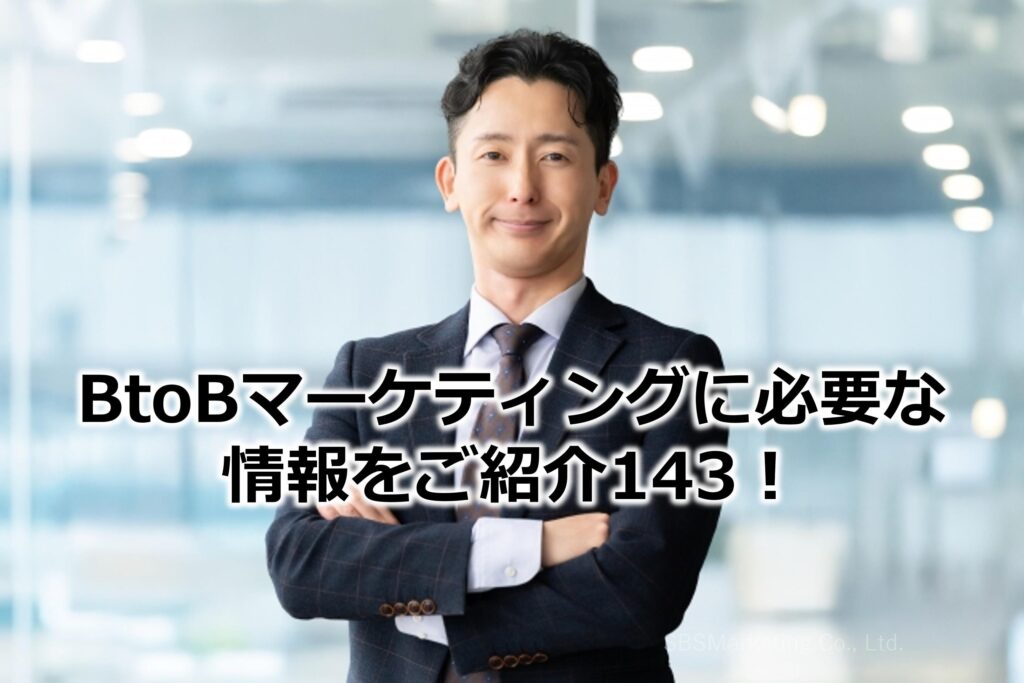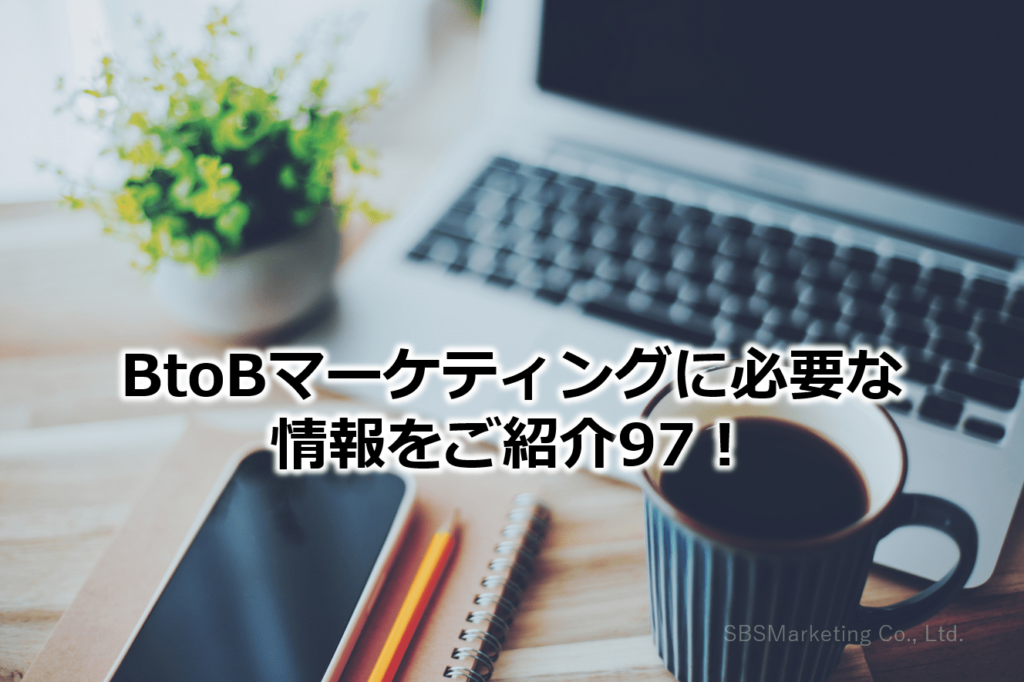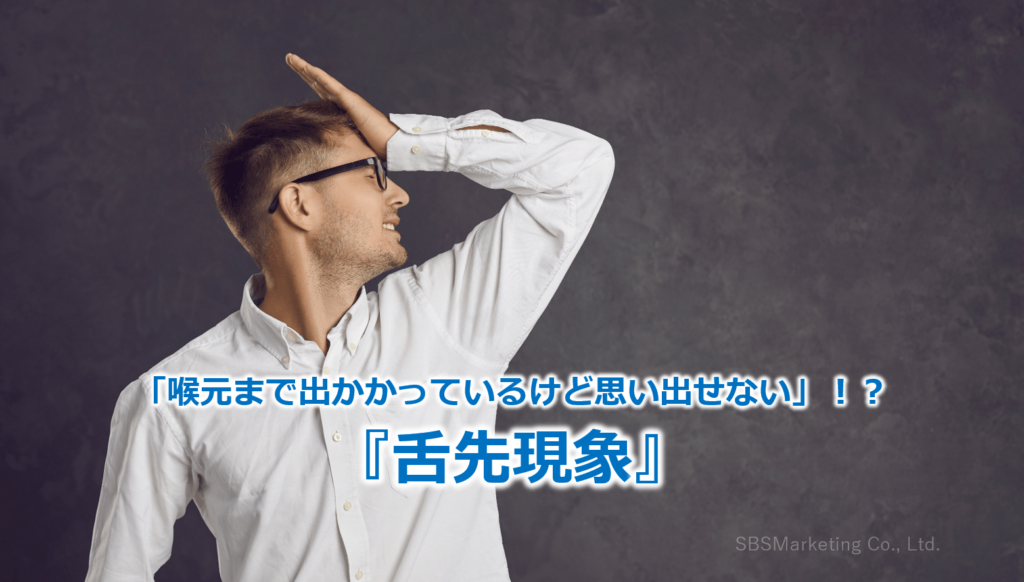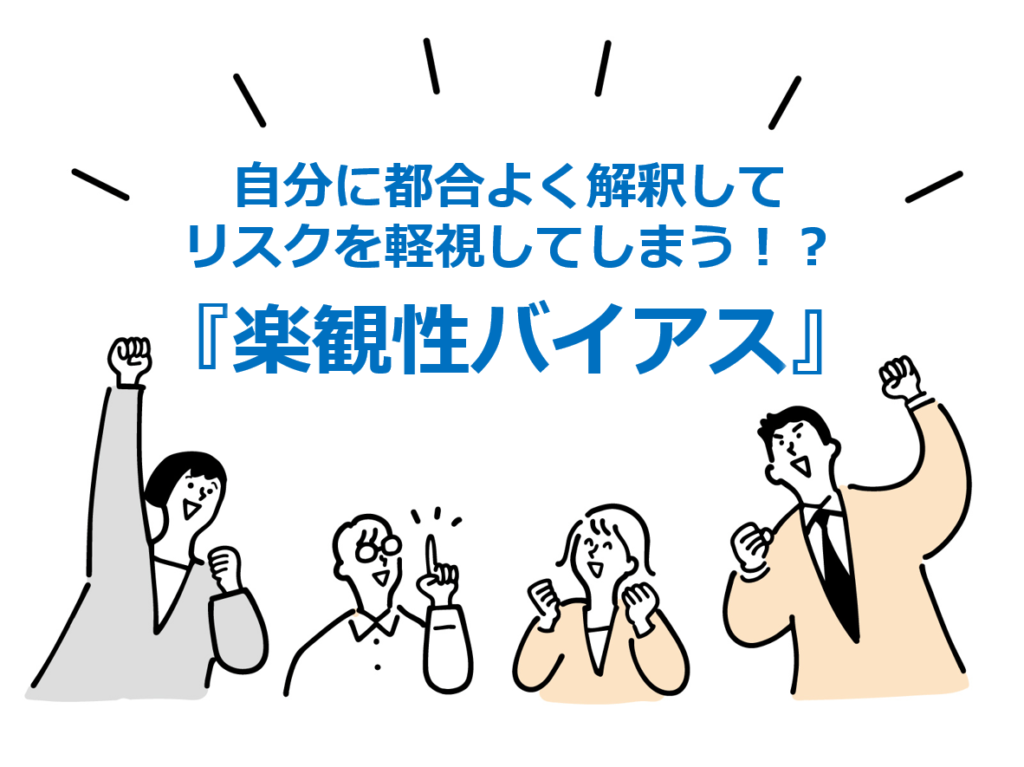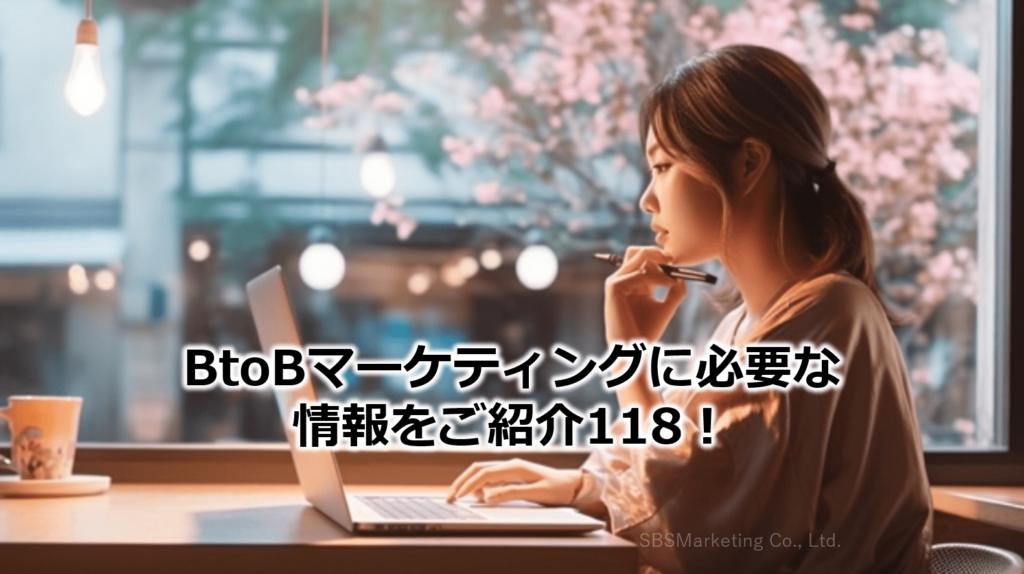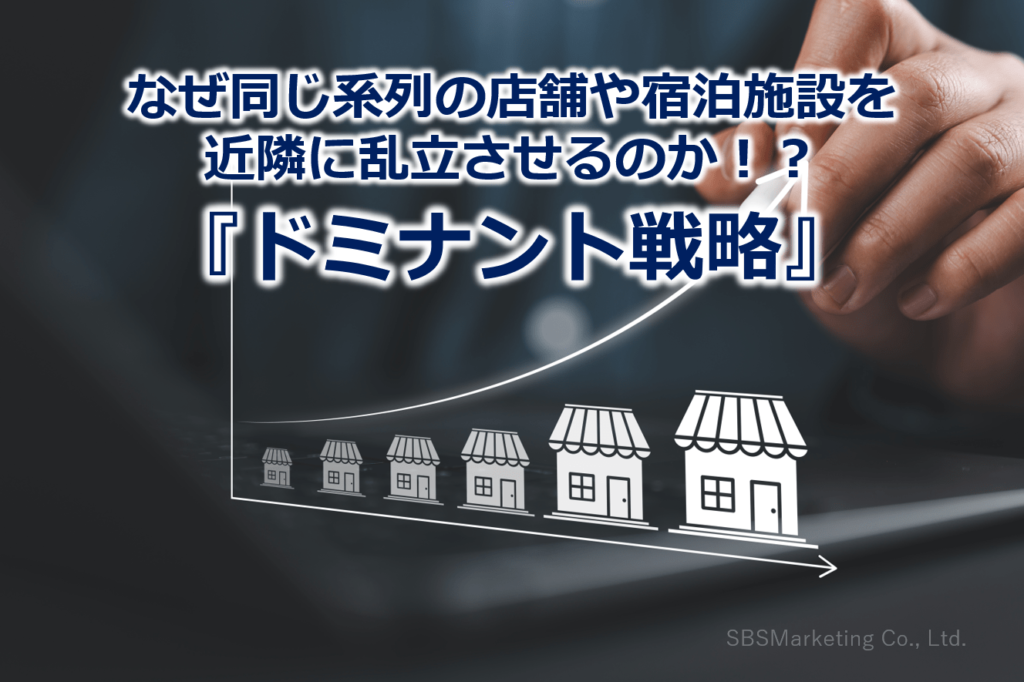
特定の地域に経営資源を投下し集中的に出店することで、シェアを独占して競争優位性を確保する『ドミナント戦略』。
メリットとデメリット、ランチェスター戦略との違い、4社の成功事例と成功させるためのポイントなどについて解説しています。
『ドミナント戦略』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『ドミナント戦略』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『ドミナント戦略』とは?

街を歩いていると、数メートル間隔で同じチェーン店があることに気づいたことはありませんか?
この、あえて特定の地域に経営資源を投下し集中的に出店することで、シェアを独占して競争優位性を確保する店舗戦略のことを『ドミナント戦略(Dominant Strategy)』と呼びます。

ドミナント(Dominant)とは、「支配的な」「優位性がある」「独占的」という意味で、集中して店舗を多数構える地域のことを「ドミナントエリア」と呼びます。
この戦略は、主にコンビニチェーンやスーパーマーケットといった小売業やファミリーレストランなどの外食チェーンなどで実施されています。
特に、資本の少ない企業・店舗が、競合と戦う際に有効な手法として知られています。
『ドミナント戦略』のメリット

一般的には、広いエリアに満遍なく店舗を配置した方が良いと考えられますが、あえて特定の地域に集中することで、さまざまなメリットを得ることができます。
- 「エリアマーケティング」の最適化
- 特定の地域で知名度や認知度を高めやすい
- 経営資源の効率化
- 物流コストの削減
- 人材の確保が容易に
- 競合の参入を抑制できる
「エリアマーケティング」の最適化

メリットの1つは、「エリアマーケティング」を最適化できるという点です。
特定の地域に応じたマーケティング手法を指す「エリアマーケティング」。
特定のエリアに出店を集中させるため、その商圏内の顧客の特徴や傾向に絞ったマーケティングを実施すればよいので、効率的に特性に応じた商品開発や価格の設定、サービス展開や出店計画をすることが可能になります。
また、複数店舗で同時にセールやキャンペーンを実施することが容易になるため、広告宣伝費などのマーケティングコストを最適化しやすくなります。
さらに、市場調査にかかるコストも、エリアを限定することで削減が可能になります。
※おすすめ記事:【地域集客】田舎ならではのエリアマーケティング手法7選を解説 | 新潟SEO情報局
特定の地域で知名度や認知度を高めやすい
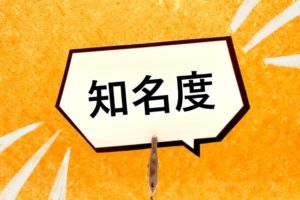
特定の限定した地域に集中して資本を投下することから、その地域での知名度や認知度(※)が高まるようになります。
日常生活で頻度高く視界に入ったり来店する機会が生じやすくなるため、その店舗名やブランド名などが記憶に残りやすくなる、というわけです。
特定の地域で知名度や認知度が高まりシェアを確保できれば、その地域において「プレミア感」を出したり、ほかのエリアへ出店を拡大展開しやすくもなります。
※『知名度と認知度の違い』については、こちらのページをご覧ください。
理解しているようで曖昧な『知名度』と『認知度』の違いやそれぞれの意味について解説しています!
経営資源の効率化
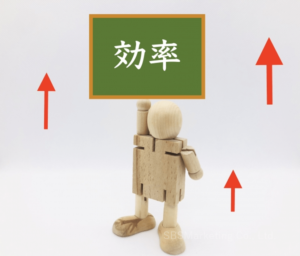
フランチャイズチェーン店の場合、特定のエリアに集中して店舗を複数構えることで、各店舗の運営を監督・指導する役割を担うスーパーバイザーが効率良く巡回しやすくなり、監督・指導する時間をより長く確保できます。
つまり、フランチャイザーである本部の中央管理コストを低く抑えることが可能になる、という効果を見込むことができます。
物流コストの削減

『ドミナント戦略』によって、店舗間の物理的距離が近くなることで、商品や資材の配送などの物流コストを抑えることが可能になります。
さらに、余剰在庫を近隣店舗へ短時間で移動させやすく、自然災害が起こった際にも柔軟に出荷対応ができます。
人材の確保が容易に

物流の効率アップとともに、店舗間の人員不足にも対応しやすくなり、また限定されたエリア内での配送となるため、近年のドライバー人材の不足についても有効な手立てになります。
競合の参入を抑制できる

『ドミナント戦略』は、ライバルとなる競合店の新規参入を阻むことにもつながります。
特定のエリアに集中して店舗を出店していれば、競合店が参入しようにも成功する採算が低いため、ライバル店の出店意欲を抑える効果が期待できます。
『ドミナント戦略』のデメリット

多くのメリットがある一方、『ドミナント戦略』には以下のようなデメリットもあります。
- 「カニバリゼーション」のリスク
- 地域の需要変化の影響を受けやすい
- 巨大資本が参入してくると太刀打ちできないケースも
- 他のエリアへの展開が遅れる
「カニバリゼーション」のリスク
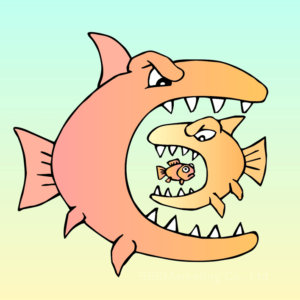
『ドミナント戦略』では、同系列店舗間で「カニバリゼーション(共食い)」が生じて顧客の取り合いが起こるリスクがあります。
限定的な地域で、店舗間でノウハウを共有しながらサービスや接客レベルが向上するメリットがある一方で、店舗ごとにノルマがある場合、同じ系列店舗同士で競争が生じる可能性があります。
「カニバリ」が生じて共倒れが起きないよう、出店計画を綿密に練り、厳しいノルマを設定しないことがポイントになります。
地域の需要変化の影響を受けやすい

特定に地域に限定し、そのエリアのニーズに特化して店舗展開ができるメリットがある一方で、ニーズ自体が変化したり、地域の環境変化によって、売上が落ちやすいデメリットがあります。
そういった影響に対しては、経営戦略の見直しやコスト投入など、大掛かりな変革を講じなければなりません。
そのため、変化に対応可能な柔軟性や経営リソースを担保しておくことが重要です。
さらに、刻々と進む「人口減少」も大きなリスクとなります。
『ドミナント戦略』に基づき、大量出店した地域の人口が急速に減少していく場合、複数店舗を出店している方が大きな被害を被ることになります。

「人口減少」に加え、突発的な自然災害などによって壊滅的な被害が出た場合、売上の減少や店舗の改修・修繕などのコストがかかる点も、大きなデメリットと言えます。
そういったリスクに対しても、相応の対応ができるよう事前準備しておくことが大切になります。
巨大資本が参入してくると太刀打ちできないケースも
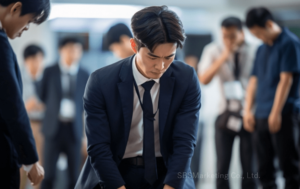
自社よりも規模の大きい店舗や企業が、巨大な資本を投下し参入してきた場合、対応できずに閉店・撤退の恐れが生じてしまいます。
他のエリアへの展開が遅れる

特定の地域に大量出店する戦略であるため、ほかのエリアへの展開が遅れてしまうというリスクもあります。
『ドミナント戦略』を重視していると、新規エリアへ参入する際の開発力(情報や資金、人材など)に乏しく、出店ができなくなってしまうことも。
また『ドミナント戦略』の対象となる地域に特化することから、それまで培ったマーケティングやノウハウが通用しない、ということも起こりえます。
『ランチェスター戦略』との違い

『ドミナント戦略』のほかに、中小企業や資本の乏しい企業・店舗が競合と戦うための手法として『ランチェスター戦略』があります。
『ランチェスター戦略』とは、「弱者(中小企業)視点」と「強者(大企業)視点」からマーケティング分析し、「弱者が強者に勝つ」ためのマーケットや手法を打ち出す戦略のことです。
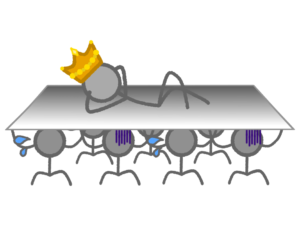
経営資源が潤沢な大企業に対し、中小企業が市場シェアを勝ち取ることは困難と言えます。
そんな状況下においても、弱者(中小企業)が打ち勝てるポイントを見つけ、シェアを勝ち取る可能性を高めるのが『ランチェスター戦略』であり、特定の地域に資本を投下しシェアを勝ち取る手法が『ドミナント戦略』です。

つまり、経営資源の限られた中小企業が、商圏に固執せずに、競合の少ない特定の分野(ジャンル)・商品カテゴリーに特化して圧倒的なシェアを獲得して独占的な地位を固め、その後は広範囲なマーケットでも優位に立とうとするのが『ランチェスター戦略』で、戦略の方向性に違いがあります。
この『ランチェスター戦略』は、『ドミナント戦略』のベースとなった戦略的思考で、日本の販売戦略、企業戦略の草分け的な戦略に位置付けられています。

2つの戦略の違いをまとめると、以下のような内容となります。
ドミナント戦略
- 市場での優位性と支配的地位を獲得するのが目的。
- 特定の市場シェアを最大化する。
- 大規模な投資と経営資源が必要。
- 主に大規模・業界のリーダー的ポジション企業が実施。
ランチェスター戦略
- 市場規模や競合に応じて最適な戦略を選択するのが目的。
- ニッチな市場での競争。
- 限定的なリソースでも効果的に競争できる。
- 主に中小企業やスタートアップが実施。
※ちなみに、「中小企業が大企業に打ち勝つ」手法には、「スピード」に特化してビジネスを展開する『チェンバースの法則』もあります。
『ドミナント戦略』の成功事例

この『ドミナント戦略』は、多くの企業で採用されています。
- セブンイレブン
- ツルハドラッグ(ツルハホールディングス)
- スターバックス
- アパホテル
セブンイレブン

日本で最大の店舗数を有しているコンビニエンスストアチェーンのセブンイレブン。
『ドミナント戦略』によって成功を収めた日本国内の最初の代表例として知られています。
1974年5月に東京都江東区豊洲に第一号店をオープン後、2025年1月時点では21,534店舗を展開しています。
第一号店出店当初、「江東区以外では出店しない」というルールで、次々と新店舗を展開していきました。
セブンイレブンオリジナルの商品は『ドミナント戦略』を背景に、独自の専用工場を設置、販売時間帯に合わせた計画的な配送を実現し、品質が高く新鮮な商品の提供を可能にしました。

セブンイレブンが『ドミナント戦略』を体現している理由には、顧客の囲い込みとともに、物流の効率化があります。
コンビニチェーンという事業形態は、おにぎりやお弁当などの食料品の補充が、一日に何度も必要になるため、店舗同士が近くにあればあるほど、物流効率は高まります。
「お客様が求める商品を、店舗が必要とする数量で、確実に供給する」という理念を掲げて、多頻度配送などの物流システムを構築しており、競合他社との差別化につなげています。
さらに、フランチャイズ店舗を監督・指導するために、本部から派遣されるエリアマネージャーが頻度高く巡回できる点も、店舗が近接していることが有利に作用しています。

一方で、セブンイレブンの『ドミナント戦略』は、難局に直面しています。その要因の一つとして挙げられるのが、「フランチャイズ契約」です。
「フランチャイズ(=FC)」では、本部と契約した加盟店オーナーが店舗を経営します。
「セブンイレブン」というブランドや独自のノウハウを活用できるなどのメリットがありますが、コンビニオーナーは多額のロイヤルティーや違約金で縛られ、「365日24時間」を前提とした営業時間の変更や廃棄品の安売りといった、ビジネスの裁量権をオーナーに与えていないことが多く、直営店(※)とは異なり、多くの経営リスクを「フランチャイジー」であるコンビニオーナーに委譲している状況が続いています。
つまり、経営的な裁量が非常に限定的でありながら、本部が『ドミナント戦略』に基づいて店舗を近接出店するため、同じセブンイレブンの店舗であっても「競合関係」になってしまっている、ということです。
集客も求人もセブンイレブン同士でバッティングしてしまうため「潰し合い」が起こりやすく、現場の疲弊感は強まっていると言えます。
※直営店・・・フランチャイズとは異なり、企業本部が経営し、従業員の採用や売上管理などを行う。
ツルハドラッグ(ツルハホールディングス)

北海道・東北から日本全国に店舗を展開しているドラッグストアチェーンであるツルハドラッグ。
ドラッグストア業界は成長が著しいこともあり、シェアの拡大競争も激しい業界です。
そんな業界の中で、ツルハドラッグ(ツルハホールディングス)は、M&Aと『ドミナント戦略』によって市場シェアを獲得した成功例として知られています。

競合他社と比較して、地域性を重視しニーズに応じた細かな店舗運営を実現していることから、「カニバリゼーション」を抑止するなど、『ドミナント戦略』によって生じるデメリットを解消した手法が取り入れられています。
スターバックス

2024年2月時点で、全世界では41,999店舗を出店し、日本では2025年に2,000店の大台を超える見通しであるスターバックス。
一大カフェチェーンとして知られていますが、典型的な『ドミナント戦略』の成功例として知られています。
その始まりは、1971年、アメリカのシアトルのパイク・プレイス・マーケットでした。
創業当初から、シアトル市内で『ドミナント戦略』を展開。その後、1992年には店舗数は165店になり、そのほとんどが北米大陸の太平洋岸北西部に位置し、年商1億300万ドルの企業になりました。
スターバックスは、『ドミナント戦略』とともに、「ロケーショニング(立地を選ぶこと)」も重視し、巨額の広告投資をせずに目につきやすく往来の多い角地の中から店舗を構えるのに最適な場所を選び出しています。
店舗の立地の良さと『ドミナント戦略』により、お店の知名度や認知度の向上、顧客の囲い込みを効率的に行っています。

また『ドミナント戦略』によって、通りを挟んだ向かい合わせに店舗をオープンさせたとしても、各店舗の顧客の受け入れ能力とその地域で見込める客数に目を光らせることで「顧客の奪い合い」にはならず、むしろ「(混んでいるから)すぐ近くの別のスタバに行こう」という客の流れを作り、既存店舗への集中を和らげつつ、チェーン全体の売上を確保しています。
来店客からすると、待ち時間は減少しますし、店舗のバリスタの疲労も軽減するため、より開放的で落ち着いた店の雰囲気作りを実現しています。
アパホテル

ホテル業界で存在感を増しているアパホテル。
アパホテルでは、中央区日本橋エリアを重点地域と位置付け『ドミナント戦略』を進めており、周辺には複数棟出店しています。
『ドミナント戦略』を採用する理由として、アパホテルでは以下の3つを挙げています。
- 「(エリア)ならアパホテル」という認知を得る
- オーバーブッキングを恐れずに稼働が可能
- 従業員の共有・交流による人員の効率化やノウハウの蓄積
「このエリアに旅行・出張に行くならアパホテル」という意識付けができれば、宿泊予約が増え、同じエリアに複数のホテルがあることで「どこかのアパホテルで予約が取れる」という安心感も得られるため、次の機会にも選ばれやすい。
ホテル業界でも叫ばれる人材不足という課題に対しても、ホテル運営を効率化することで従業員への報酬も厚みを持てるようになります。
さらに、『ドミナント戦略』による同エリアで複数のホテルを建設することで、客室設備の発注コストも抑えることができます。

ホテル業界の性質として、コンビニエンスストアのように毎日のように利用することも、スーパーマーケットのように高い頻度で配送することもありません。
そのため、同じアパ系列のホテル同士で顧客を奪い合うという「カニバリゼーション」が起こりにくい、という状況を作り出しています。
↓
この続きでは、『ドミナント戦略』を成功させるためのポイントなどについて解説しています。
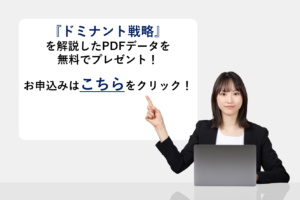 『ドミナント戦略』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
『ドミナント戦略』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『ドミナント戦略』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
- BtoBマーケティング
- Dominant Strategy
- アパホテル
- エリアマーケティング
- カニバリゼーション
- スターバックス
- セブンイレブン
- チェンバースの法則
- ツルハドラッグ
- ドミナント戦略
- ドミナント戦略を成功させるためのポイント
- フランチャイズ
- マーケティングコストを最適化
- ランチェスター戦略との違い
- リスク管理
- ロケーショニング
- 事前の商圏調査
- 人口減少
- 人材の確保が容易に
- 地域の需要変化
- 客の奪い合い
- 巨大資本の参入
- 弱者が強者に勝つ
- 株式会社SBSマーケティング
- 物流コストの削減
- 特定のエリアに集中的に出店してシェアを独占
- 知名度や認知度が高まる
- 競合との差別化を徹底
- 競合の参入を抑制
- 経営資源の効率化
- 自然災害
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。