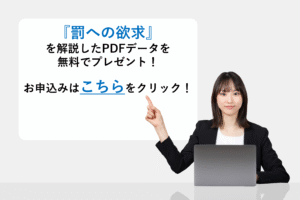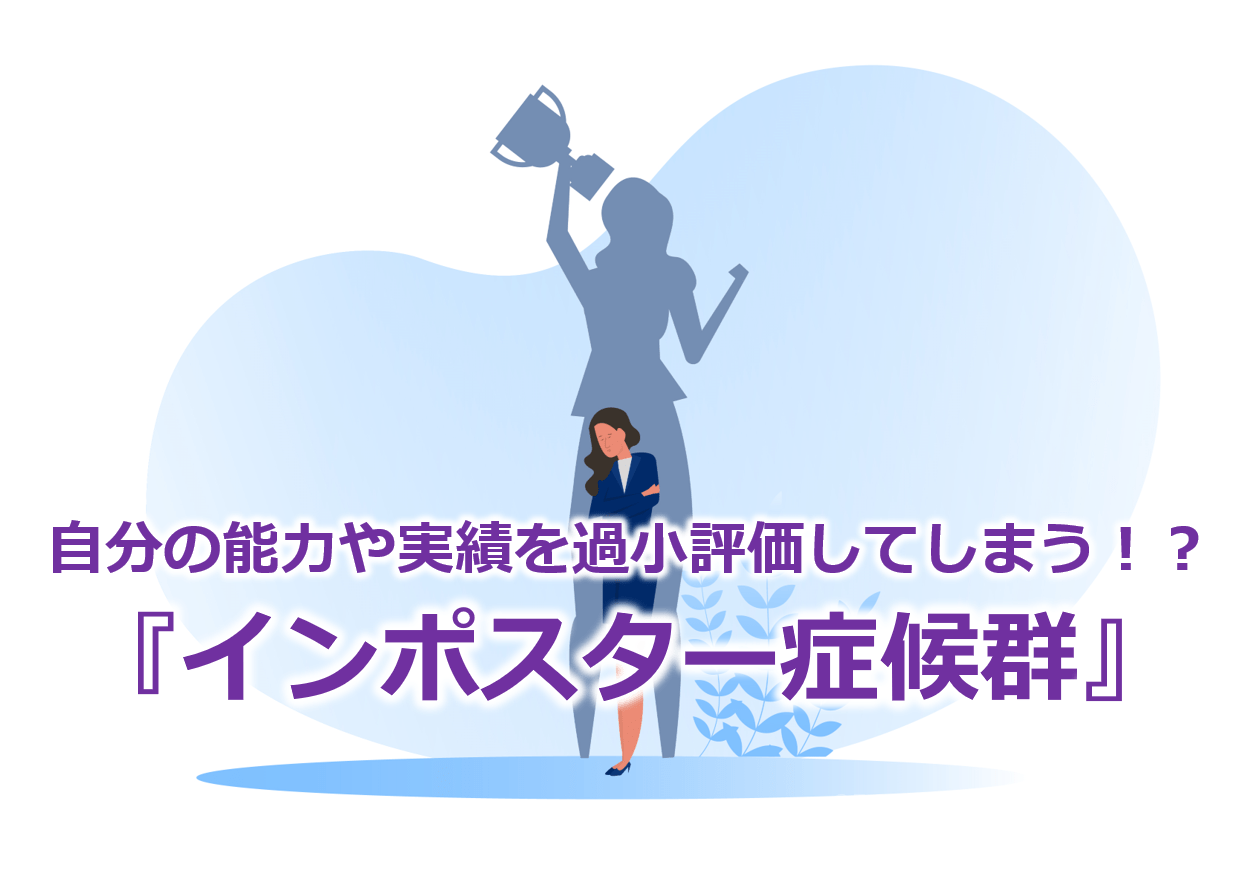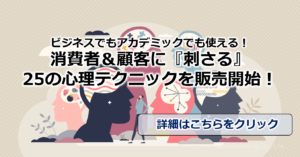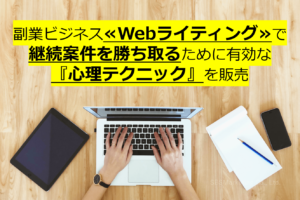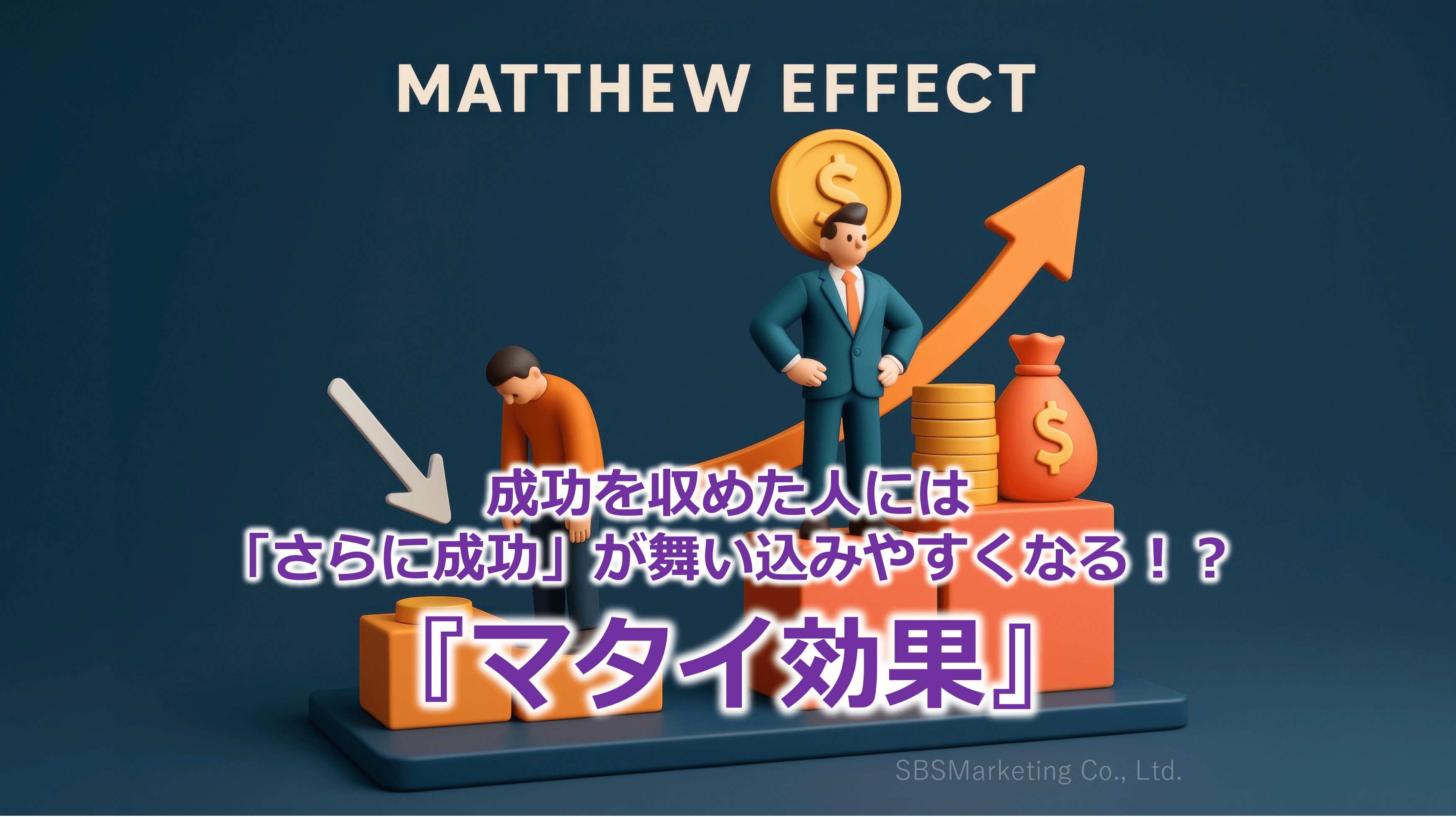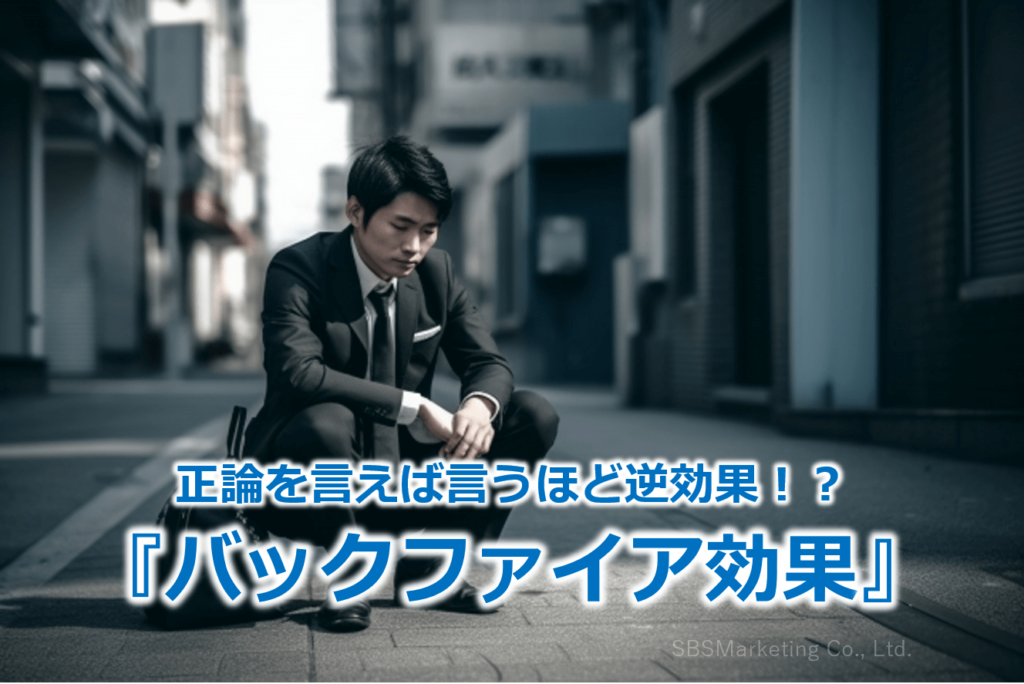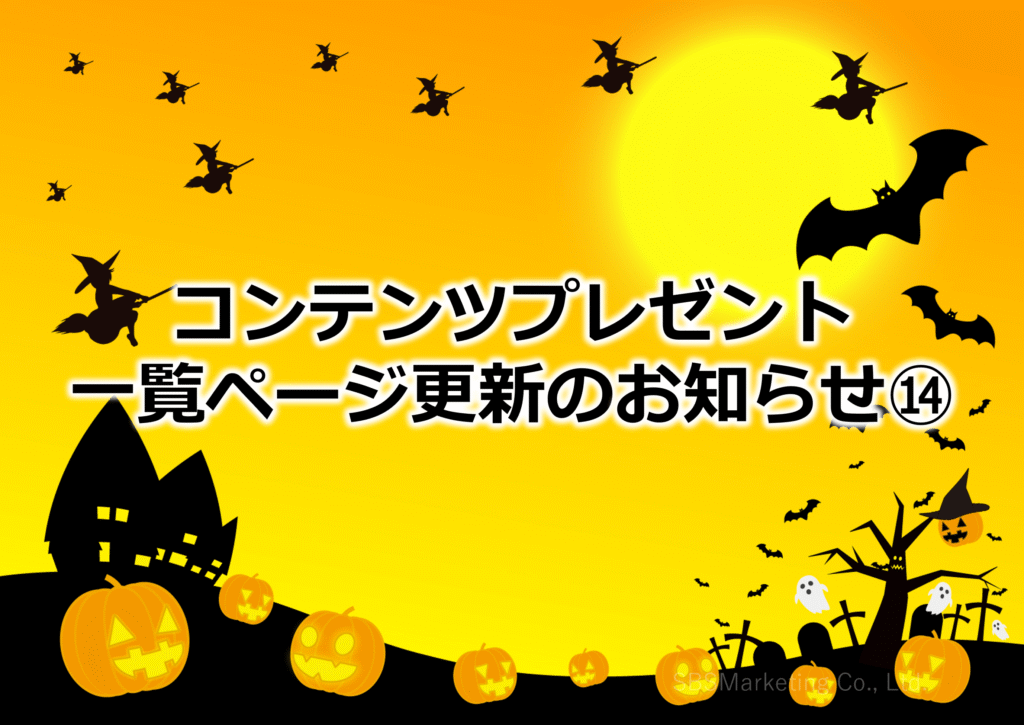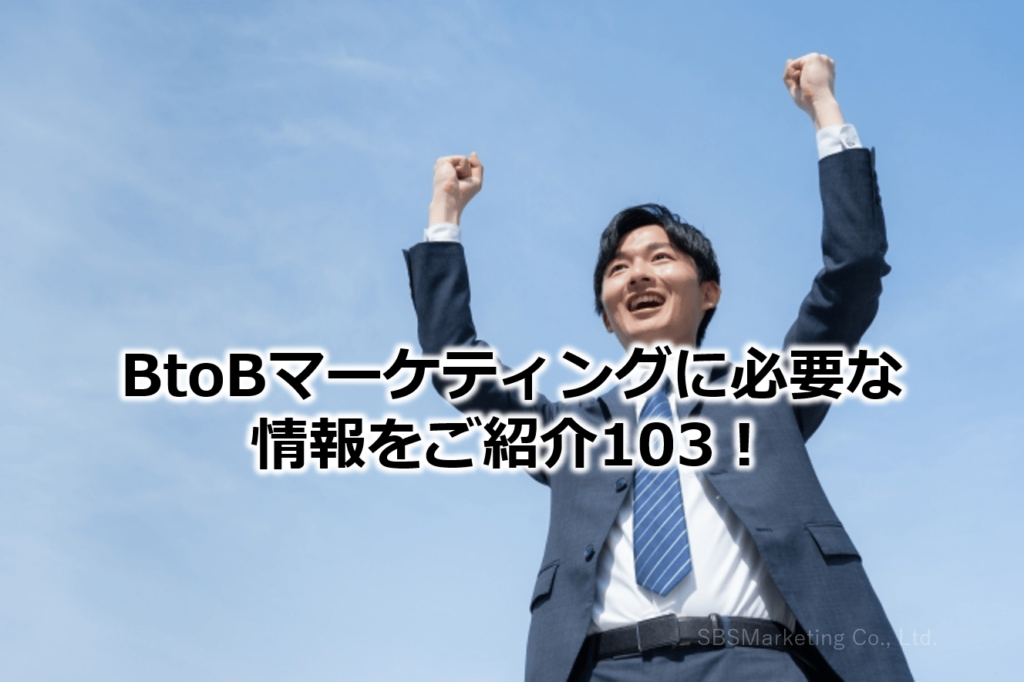うまく物事が続くと不安にかられたり心配になり、悪いことや失敗を望むようになる『罰への欲求』。
発生するメカニズムや具体例、活用する際のポイントなどについて解説しています。
『罰への欲求』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『罰への欲求』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『罰への欲求』とは?

うまく物事が続くと不安にかられたり心配になり、悪いことや失敗を望むようになる『罰への欲求』。
「うまく行き過ぎて不安」「こんなに良いことが続くはずがない」といった感情を抱き、「今度は逆に悪いことが起こるんじゃないか」と不安感を覚えたり、悪いことが起きることを求めるようになるという心理現象のことです。
提唱したのは?

この『罰への欲求』は、消費者心理に訴える広告を提言した、アメリカの深層心理学者の E・ディヒター(Dichter Ernest)が提唱した心理現象です。
ディヒター 氏は、著書『欲望を創り出す戦略(The Strategy of Desire)』の中で、以下のように述べています。
人の心の中では、快楽と罪悪感が常に衝突し合っている。
広告マンの大きな仕事は「商品を売り込む」ことよりも消費者に「安心感」を与えることだ。

多くの人間には「幸せはずっと続くことはなく、良いことと悪いことは同じだけ起こる」と考える傾向があります。
すると「良いことが続くと、その後には必ず悪いことが起こる」と不安を覚えるようになります。
そのため、ビジネスシーンにおいては消費者が「快楽(幸せ)」と「罪悪感」のバランスをうまくとれるような手法が求められる、というわけです。
実際に起きた出来事が事例に

『罰の欲求』を提唱した E・ディヒター 氏は、1950年~1955年に起こったアメリカの出来事を事例として挙げています。
1950年から1955年にかけて、アメリカでは肥満や虫歯などの原因は「砂糖菓子」にあると言われていました。
すると、消費者の多くは、砂糖を使った菓子商品の購入を避けるようになりました。
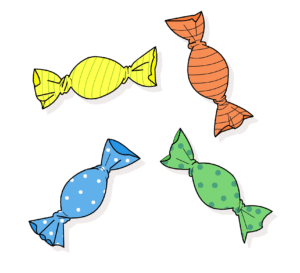
その結果、菓子商品の消費が10%も減少してしまったことに対して、E・ディヒター 氏は消費者の抵抗感を減らすためにある「キャンディ」を販売しました。
当時は大きいキャンディケースにキャンディが詰められており、一度にキャンディを食べなければならない仕様になっていました。
そこで、一口サイズで一つ一つを個装したキャンディを販売したことで、一度にキャンディを食べきってしまうことへの不安心理を取り払うことに成功し、売上を回復させることができました。
キャンディを食べる「罪悪感」に、一口サイズで食べられるという「快楽」を取り入れてバランス保ったことで、『罰への欲求』をうまく活用した例として知られています。
『罰への欲求』が発生するメカニズム
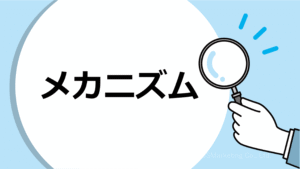
良いことが続くことで引き起こされてしまう『罰への欲求』。発生するメカニズムとしては、以下が挙げられます。
- 幸せ恐怖症
- 予期不安
- インポスター症候群
幸せ恐怖症

「幸せ」を感じることに恐怖感を抱く精神的な状態を指す『幸せ恐怖症』。
「幸せになると何か悪いことが起こるのではないか」という不安や、「喜びを表現する」ことへの恐れを特徴としています。
不安症の一種と捉えられることもあり、自己肯定感の低下や抑うつ、不安感やストレスにつながる可能性があります。
予期不安

「強い不安を伴う出来事が起こるのではないか」という、まだ現実化していない未来(将来)への恐怖や心配を意味する『予期不安』。
インポスター症候群

自身の能力や実績を過小評価し認めることができない心理的傾向を意味する『インポスター症候群』。
「自分の能力を偽って他人を欺いている」と感じることで罪悪感や不安、後ろめたさが生じ、それが一種の自己罰的な感情につながる可能性があります。
※『インポスター症候群』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
自身の能力や実績を過小評価し認めることができない『インポスター症候群』。症状例や症状を起こす原因、マネジメントをする立場として緩和・克服させる方法、自身で緩和する・乗り越える方法などについて解説しています。
『罰への欲求』の具体例
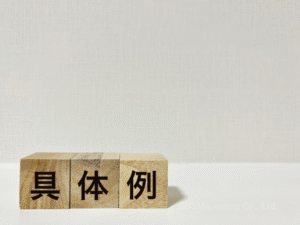
『罰への欲求』は、ビジネスシーン以外にも、身の回りで起こりやすい心理現象です。
- 「宝くじ」が当たったとき
- 「投資信託」をする際のリスク
「宝くじ」が当たったとき

宝くじが当選した際、「これで運を使い果たしてしまった」と感じ、今後悪いことが起きてしまうだろう、と思ってしまう。
「投資信託」をする際のリスク

「財産を構築したい」という思いから行う投資信託。
投資を検討する際、「リスクが無く高い収益が見込める」と記載されていても疑念を抱く人が多いと思われますが、「リスクが低く高い収益が見込める」と記載されていれば、不安に感じても多少のリスクがあると理解することができます。
つまり、「まったくリスクが無い」と伝えるよりも、「リスクがあっても高い収益が見込める」と訴求した方が消費者は安心できるようになる、ということです。
『罰への欲求』に基づくビジネスシーンでの活用例

「良いことが続いているから悪いことが起きるだろう」という『罰への欲求』から、「メリットばかりを訴求していても商品やサービスは信頼されない」ことを学ぶことができます。
つまり、商品やサービスの「メリット(良さ)」ばかりを訴えかけるのではなく、意識的に「デメリット(悪さ)」と「それをカバーする要素」も伝えることで、消費者に安心感を与えることができるようになるのです。
こういった活用手法を用いた具体例としては、以下が挙げられます。
ダイエット

デメリットを伝えつつも、先回りしてその対策をする。
パーソナルトレーニングや器具を用いたダイエットには、「サービスや器具を使っても痩せないのではないか?」「ジムに通う・器具を使うことが面倒になるのではないか?」というネガティブな要因が頭に浮かびます。
そこで、Webサイトや店舗でそれらを指摘し、「食事の管理や日々のトレーナーのアドバイスで無理なくボディメイクができます」「スキマ時間を使って理想の体型に近づくことができます」、また「トレーナーがメンタル面までサポートします」「手軽に使える器具なので負担少なく使い続けられます」と伝えることでネガティブな点をフォローでき、『罰への欲求』を満たすことにつながります。

「ダイエット」のケースのように、『罰への欲求』を満たすためには、「メリット」だけでなく「デメリット」も伝えることが求められます。
この「良し悪し」の両面を消費者に提示する手法は『両面提示』と呼ばれています。
※『両面提示』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
交渉したり説得する際に、相手に「メリット」と「デメリット」の両方を伝える説得方法である『両面提示』。活用する際のメリットや特に効果を発揮するケース、ビジネスシーンでの活用例や活用時の注意点などについて解説しています。
↓
この続きでは、『罰への欲求』を活用する際の2つのポイントについて解説しています。
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『罰への欲求』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。