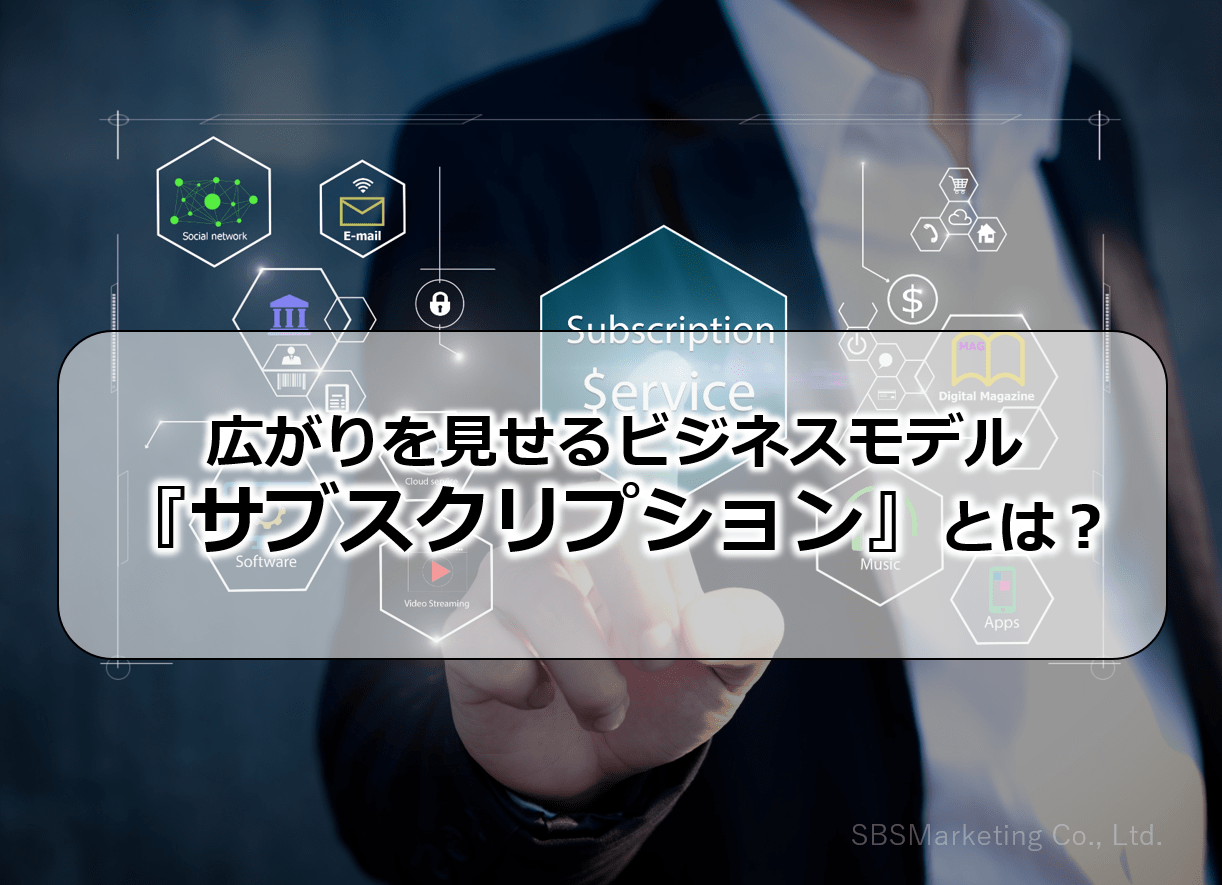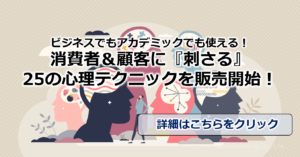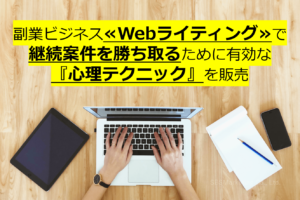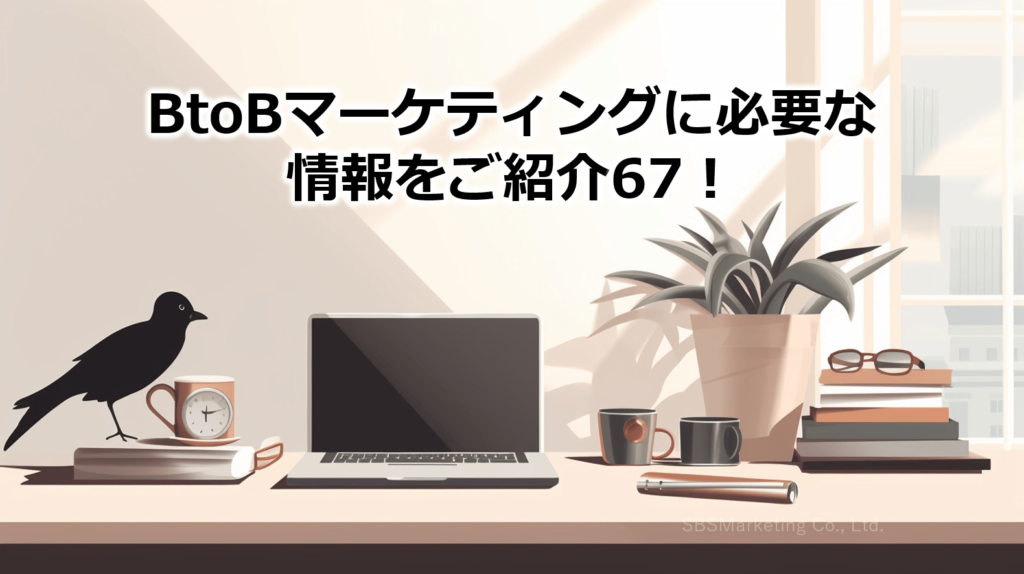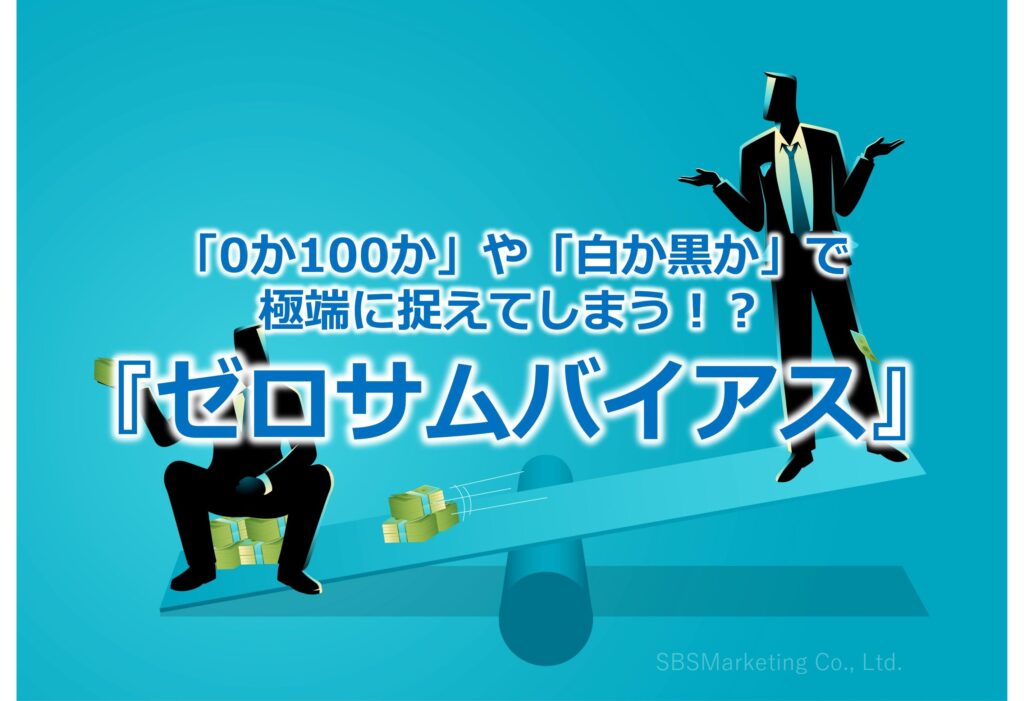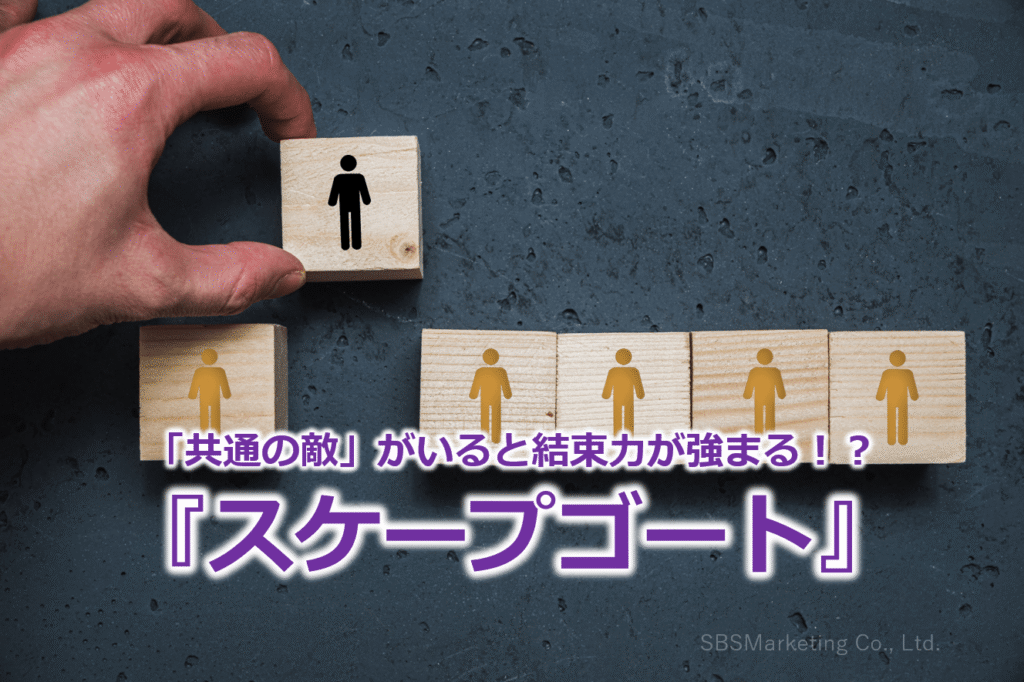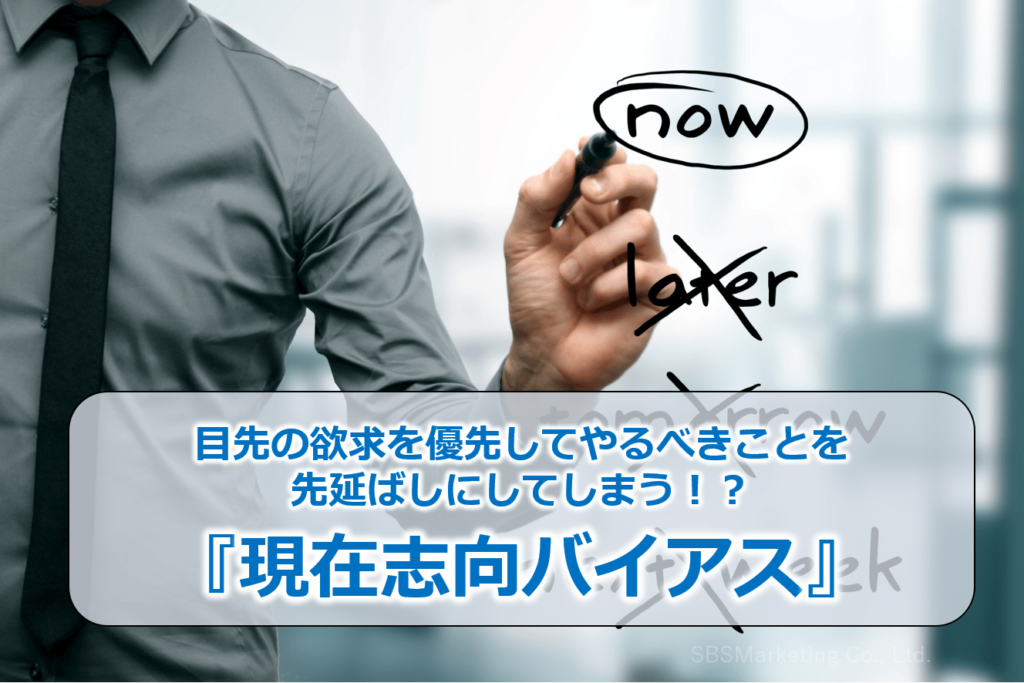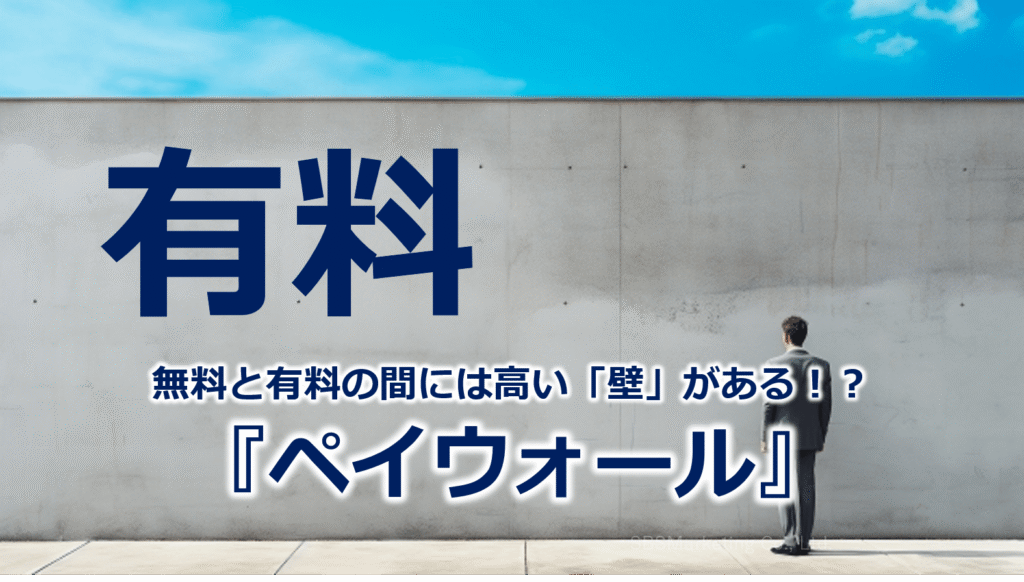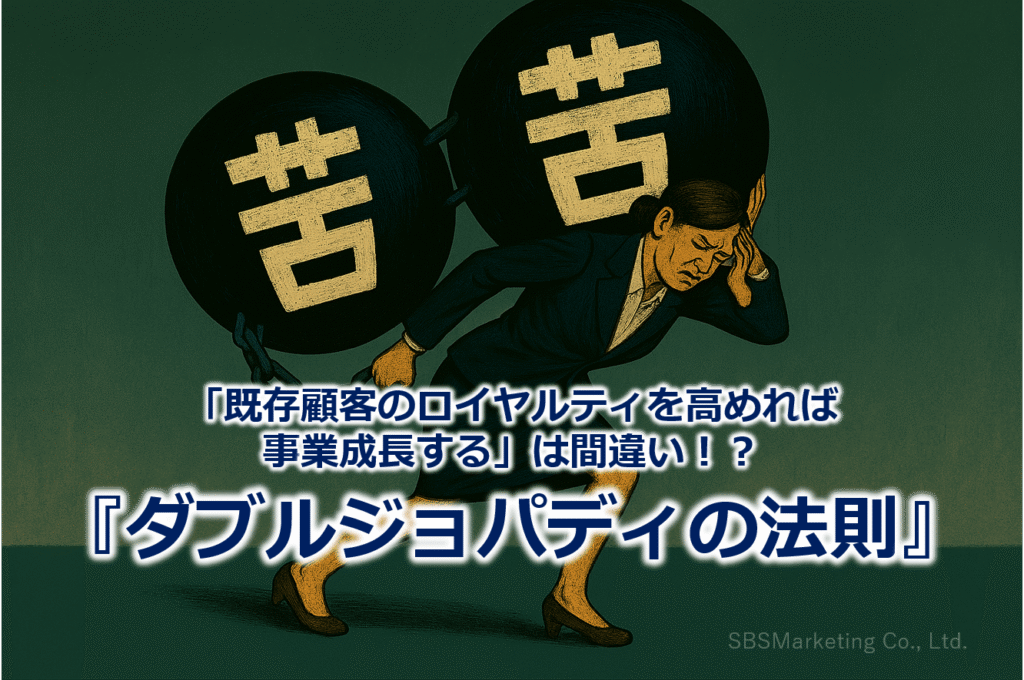
マーケットにおいて浸透率が低いブランドほど、購入される頻度も低くなる傾向があることを示した『ダブルジョパディの法則』。
発生するメカニズムと「市場での浸透率」を高めた例、中堅・小規模企業が浸透率を高める方法などについて解説しています。
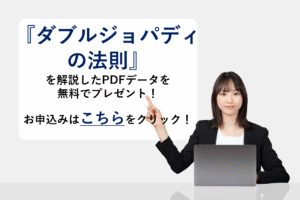
『ダブルジョパディの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『ダブルジョパディの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『ダブルジョパディの法則』とは?
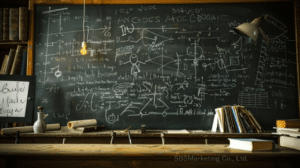
マーケットにおいて浸透率が低いブランドほど、購入される頻度も低くなる傾向があることを示した『ダブルジョパディの法則(Double Jeopardy)』。
日本語では『二重苦の法則』とも呼ばれ、マーケティング理論の一つとして知られており、「ブランドのマーケットシェア」と「顧客のロイヤルティ(リピート購入率)」の関係をあらわしています。
言い換えると、購入する人が少ないということは、購入される回数も少なくなるため、市場でシェアを確保できていないブランドは「二重の苦しさ(ダブルジョパディ)」を被ることになる、ということです。
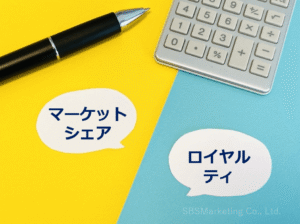
この、ブランドのマーケットでの浸透率と購入頻度は比例するという『ダブルジョパディの法則』は、「近代マーケティングの父」フィリップ・コトラーなどの従来の理論に異議を唱える法則として知られています。
この法則は、食品や化粧品などの日用品から自動車、無形サービスまでの幅広い市場で確認されており、「小さなブランドが成長するには『浸透率』を高めることが重要」であることを示唆しています。
※『ロイヤルティ』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
カスタマーサクセスや経営陣だけでなく、マーケティング担当・マーケターも理解が求められ始めている『ロイヤルティ(Loyalty)』。なぜ注目されるようになったか、ロイヤルティの意味や種類、可視化する指標、高めるための方法について解説しています。
法則を提唱したのは?

『ダブルジョパディの法則』は、南オーストラリア大学のアレンバーグ・バス研究所の、バイロン・シャープ教授の著書『ブランディングの科学』などによって知られることになりました。
この著書などで指摘されるまでは、「小さなブランドであってもロイヤルティの高い既存顧客に支えられ、その既存顧客の満足度を高めていくことで、いずれ新規顧客が増えて成長できる」というのが通説となっていました。
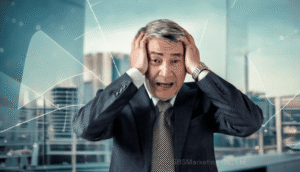
しかし、企業や事業を成長させるためには「既存顧客の満足度を高めることが事業成長のカギになる」のではなく、「商品やサービスのマーケットにおける浸透率(顧客数)」が重要になる、という説を提唱したのです。
これは、従来の通説を信じるマーケターへ「青天の霹靂」ともいえるような衝撃を与えることになり、物議を醸したと言われています。
『ダブルジョパディの法則』が発生するメカニズム

『ダブルジョパディの法則』が示唆している「マーケットでの浸透率が低いと、購入されない」という「二重苦」がなぜ起こるのか。
消費者や顧客に、以下の3つの要因が作用することで生じると考えられます。
- そもそも購入検討の「土俵」に上がっていない
- 購入への「ハードル」が高い
- 「販路」を確立できていない
そもそも購入検討の「土俵」に上がっていない

商品やサービスが消費者や顧客に認知されていないため、購入検討の「土俵」にすら上がっていないというケースが考えられます。
購入への「ハードル」が高い
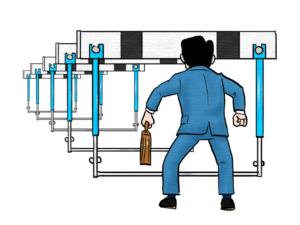
商品やサービスに関する情報が少ない場合、「本当に購入(導入)しても大丈夫か?」と不安を抱え、手を出しにくくなってしまいます。
「販路」を確立できていない
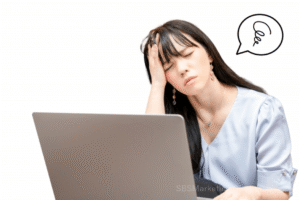
販路を確立できてない場合、購入機会が限定的になるため、購入頻度も上がりにくくなってしまいます。
マーケットで「浸透率を高める」ためにはどうすればよいか?
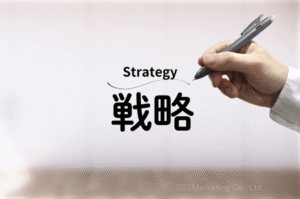
ブランドを成長させるには「市場において浸透率を高めることが重要」だと示唆している『ダブルジョパディの法則』。
つまり、消費者や顧客に商品やサービスを広く認知してもらい、実際に「手に取ってもらう」ことがポイントになります。
消費者や顧客に「知ってもらう」「手に取ってもらう」ことを促し、市場での浸透率を高めるための戦略としては、以下の4つが例として挙げられます。
- 「認知度」を高める
- 「販路」を広げる
- 「手軽に試せる」環境を整備する
- 「話題性」を高めるために口コミを喚起する
「認知度」を高める
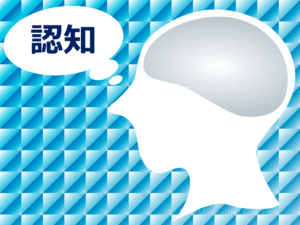
まずは「知ってもらう」ことが欠かせません。
商品やサービスのターゲットに合致するチャネルに情報を投入し、「面」的な施策で露出を高めるのも手です。
具体的には、テレビCMやWeb広告、SNSでの情報発信や、インフルエンサーを活用して大量の認知を獲得する手法が挙げられます。
「販路」を広げる
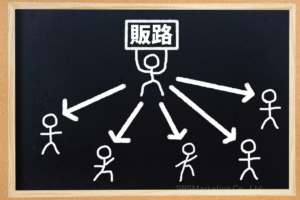
特に有形商品の場合、「どこにも売っていない」状態だと認知を獲得しても機会損失に終わってしまいます。
オフラインでは販売店への売り込みを強化する、オンラインではECサイトやサブスクリプションモデルを導入するなどして「手に取れる場所」「買える場所」をしっかりと配置することが必要になります。
※『サブスクリプション(サブスク)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
定期的に定額の利用料を支払うことでサービスが提供される『サブスクリプション』。利用者・消費者、サービス提供者・事業者それぞれのメリットとデメリット、定額制/月額制サービス、SaaSとの違いについて解説しています。
「手軽に試せる」環境を整備する

「知ってもらった」後には「実際に使ってもらう」ことが重要になります。
有形商品であればサンプルの配布、無形サービスであれば「無料トライアル」を設けるなどして、商品やサービスの「価値」を体感してもらうことが例として挙げられます。
「話題性」を高めるために口コミを喚起する

実際の人同士の間だけでなく、SNSでも口コミを喚起して「話題性」を高めることで、市場における浸透率が高まりやすくなります。
キャンペーンやコラボ企画を実施して、「自然発生的な拡散」を狙うのがポイントになります。
市場での「浸透率」を高めることに成功した事例
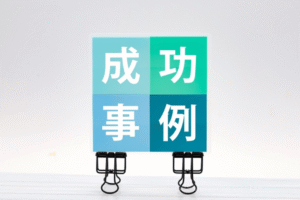
実際に、マーケットでの浸透率を高めることに成功し、ブランド力を強化した例は以下の2社が挙げられます。
- ザ コカ・コーラ カンパニー
- ナイキ
ザ コカ・コーラ カンパニー

ザ コカ・コーラ カンパニー(The Coca-Cola Export Corporation)は当初、特定の薬局で細々と販売されていました。
その後、ファミリーレストランやボールパーク(野球場)へ積極的に配荷を拡大し、多くの消費者が「いつでも手に取れる」環境を整備しました。
さらに、広告キャンペーンを大々的に実施し、クリスマスには「赤いコーラ・サンタ」を定着させるなど、認知度を向上。
やがて、世界規模の販売網を築き上げ、高いブランド力を獲得するまでに至りました。
ナイキ

アメリカ合衆国のオレゴン州ビーバートン近郊に本社を構えるナイキ(Nike, Inc.)。
1970年代に、アスリート向けの性能を重視したシューズメーカーとして事業を開始。
トップアスリートとのスポンサー契約と同時に、スポーツファンの日常に溶け込む幅広い接点づくりを進めていきました。
テレビCMやスター選手の活躍で認知度を高め、全国のスポーツショップやオンラインストアで販売展開し、「買いたい時にすぐ買える」環境を整備。
現在では、世界的ブランドへと飛躍を遂げています。
中堅・小規模企業が「市場での浸透率を高める」ための手法

前述の ザ コカ・コーラ カンパニー や ナイキ のような、多くの予算と販路を確保できる大企業でなくとも、『ダブルジョパディの法則』の二重苦を克服することは可能です。
逆に規模が小さいからこそできる手法の代表例は以下の通りです。
- 各メディアで「独自のストーリー」を発信
- 「機動力」のあるコンテンツ展開
- 消費者が身近で「買える環境」を構築する
- 「体験機会」を創出して愛着を持ってもらう
各メディアで「独自のストーリー」を発信
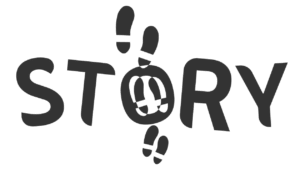
大規模なマス広告を出稿できなくても、自社のオウンドメディアや、X(旧Twitter)やFacebook、InstagramやYoutubeなどのSNSを活用して、自社独自の創業の経緯・商品開発のストーリーを継続的に発信することで、中堅・小規模企業ならではの差別化ポイントを打ち出すことができるようになります。
「機動力」のあるコンテンツ展開

事業規模が小さいからこそ、購入者との距離が近く、柔軟かつ機動力のある施策を展開しやすいというメリットがあります。
定期的なメルマガの発信や、オウンドメディアでのコンテンツ発信などを頻繁に行うことで、見込み客や顧客とのつながりを深めやすくなります。
消費者が身近で「買える環境」を構築する

「機動力」を有した小規模な事業の特徴を活かして、企業が根付いた地域の商店やセレクトショップと協力関係を築いて「棚」を確保してもらう、期間限定で開催されるマルシェへの参加で「買える環境」を構築。
「体験機会」を創出して愛着を持ってもらう

大規模企業のように広範でなくとも、小規模の試食会や試飲会、無料サンプルの配布などで「体験のきっかけ」を作り、消費者と直接接触する機会を増やすことも有効です。
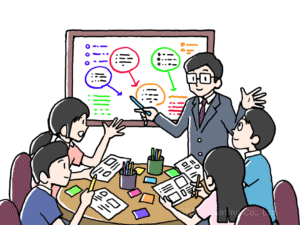
小規模の店舗であれば、見学ツアーやワークショップを開催することで、商品やサービスへの「愛着」を深めてもらう機会を創出することも手です。
↓
この続きでは、『ダブルジョパディの法則』が示唆しているコトについて解説しています。
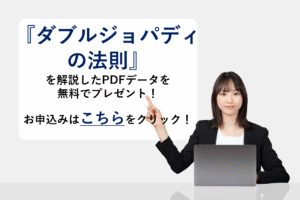 『ダブルジョパディの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
『ダブルジョパディの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『ダブルジョパディの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
- BtoBマーケティング
- Double Jeopardy
- SNS
- Web広告
- インフルエンサー
- お試し
- コカコーラ
- サブスク
- サンプル
- ストーリー
- セレクトショップ
- ダブルジョパディの法則
- テレビCM
- ナイキ
- ハードルが高い
- フィリップコトラー
- ブランディングの科学
- ブランドのマーケットシェアとロイヤルティの関係
- マルシェ
- リピート購入率
- ロイヤルティ
- ワークショップ
- 二重苦の法則
- 体験機会
- 価値を知ってもらう
- 口コミ
- 土俵に上がっていない
- 差別化
- 市場浸透率
- 情報発信
- 手に取ってもらう
- 接触機会
- 既存顧客か新規顧客か
- 株式会社SBSマーケティング
- 機動力
- 浸透率を高める手法
- 無料トライアル
- 狭く深くではなく広く浅く
- 発生するメカニズム
- 話題性を高める
- 認知度
- 販路
- 青天の霹靂
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。