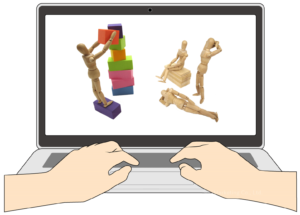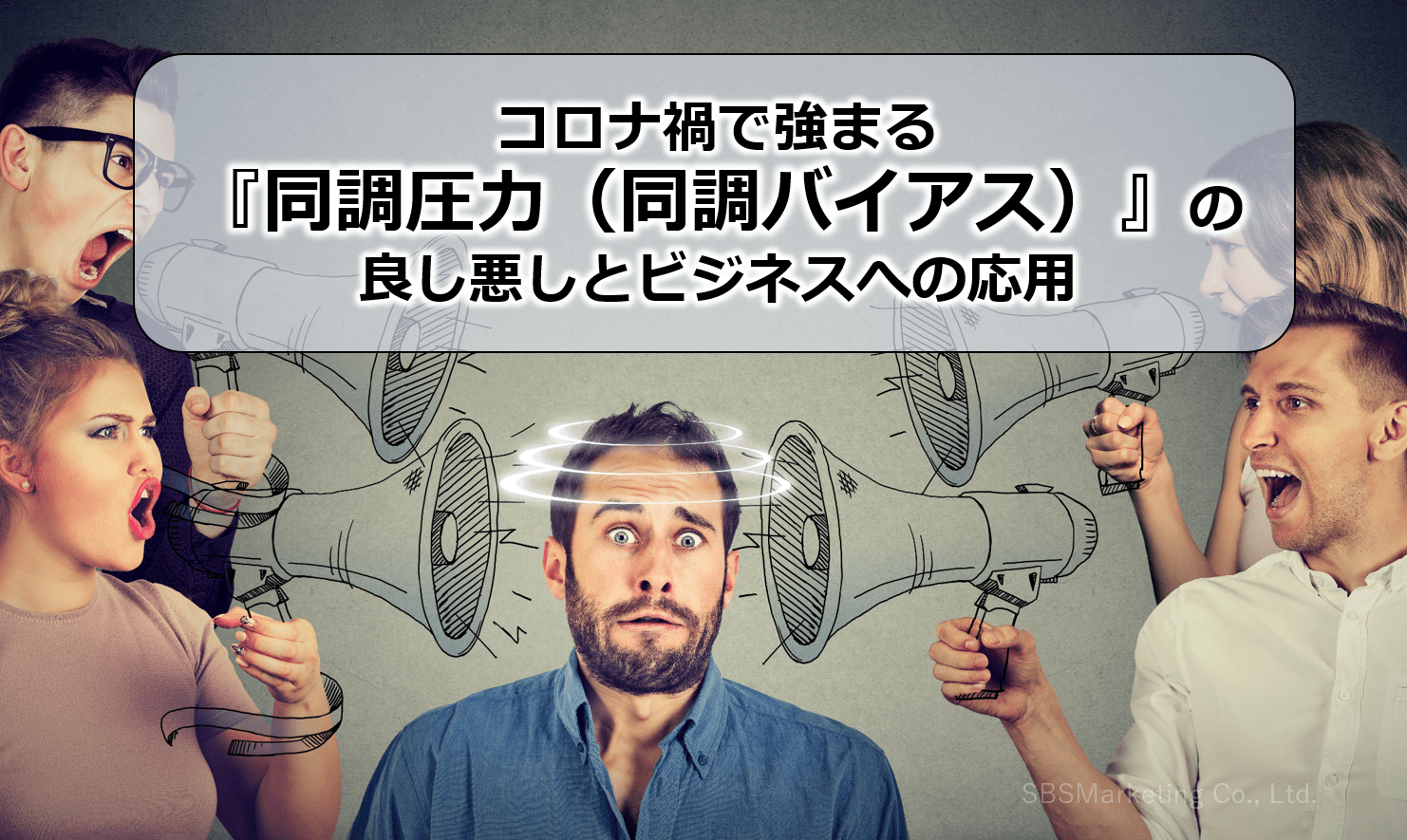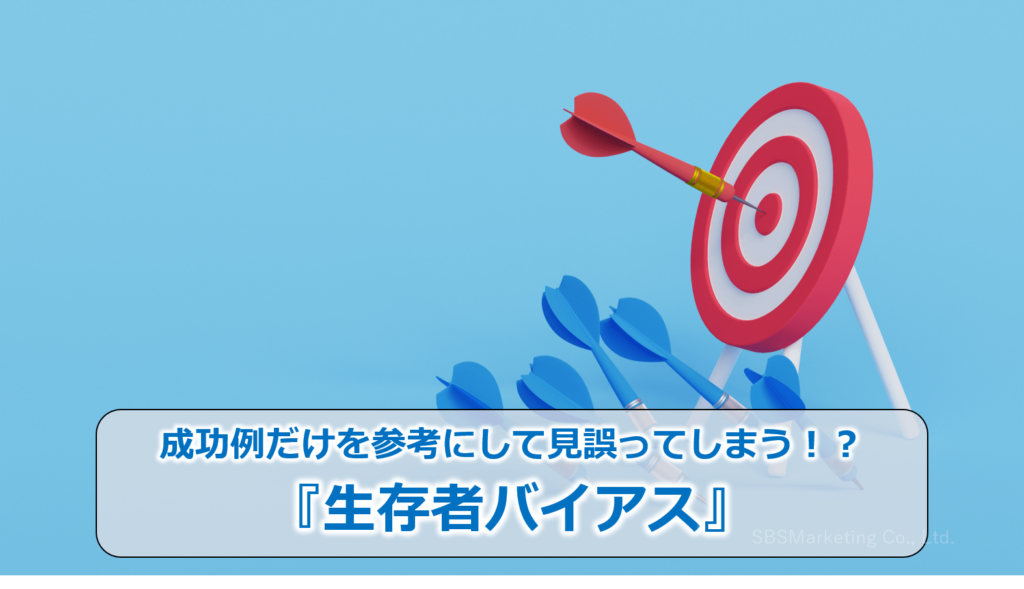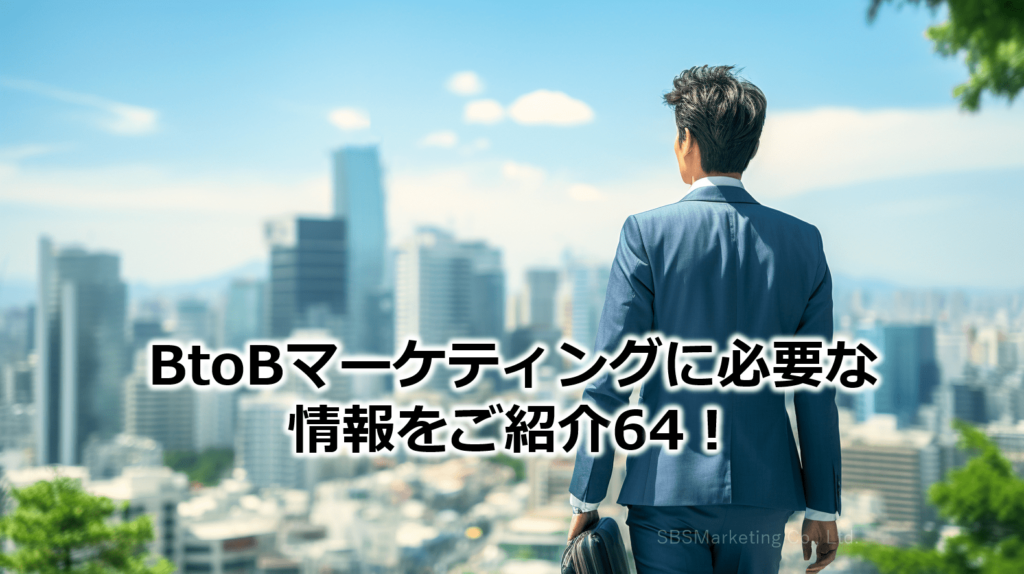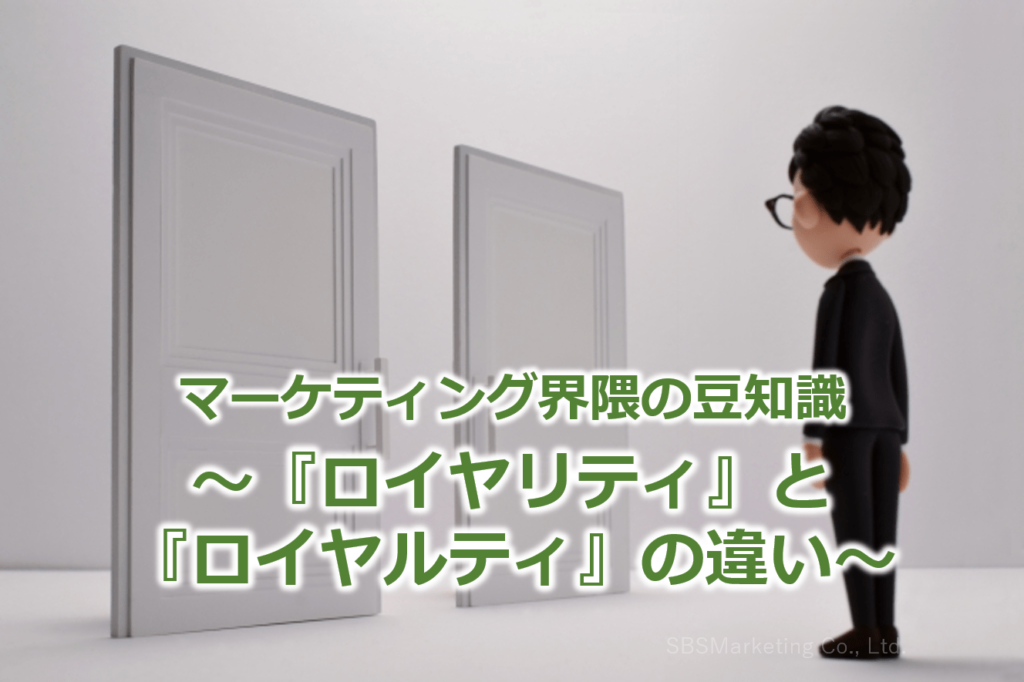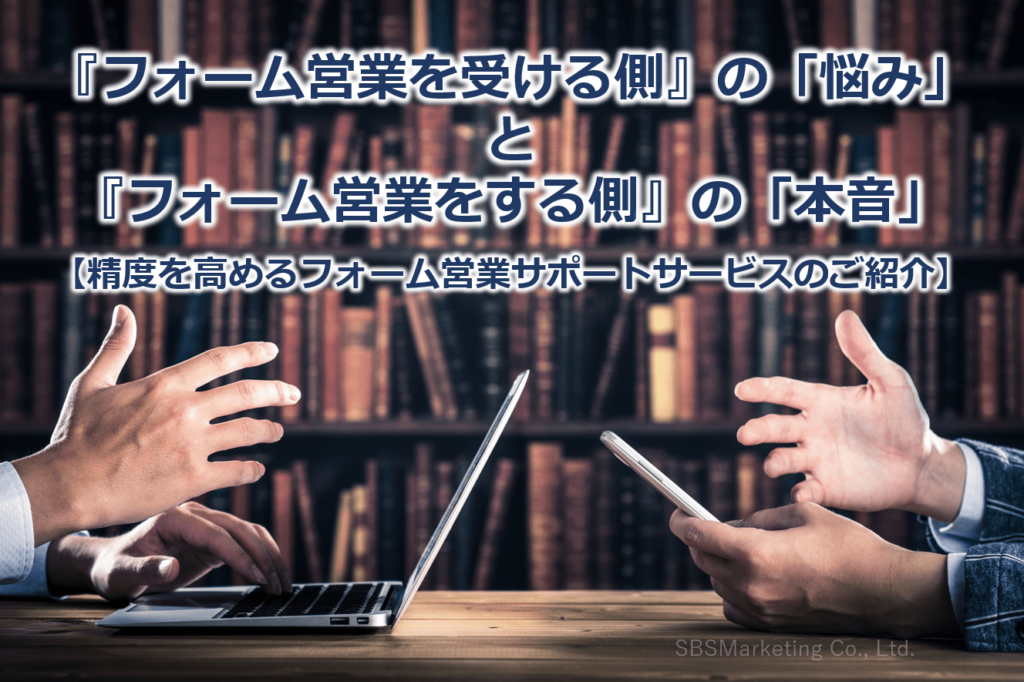『リンゲルマン効果』を解説したこのページをまとめたPDFデータを無料でお送りいたします!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名」「メールアドレス」、「お問い合わせ内容」欄に『リンゲルマン効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
リンゲルマン効果とは?

リンゲルマン効果とは、集団や組織で共同作業を行う際、人数の増加とともに一人当たりの効率が低下する現象を言います。
本来、作業をする人数が多ければ、効率化されて大きな成果を上げることになるはずですが、リンゲルマン効果が発生することによって、共同作業を行う際に無意識に他のメンバーに依存し手を抜いてしまう現象が発生してしまいます。
『社会的手抜き(怠慢)現象』『フリーライダー(ただ乗り)現象』とも呼ばれており、これは端的に表現すると、「自分以外の誰かがやるだろう」と無責任になる心理作用と言えます。
リンゲルマン効果の由来

リンゲルマン効果は、フランスの農学者であるマクシミリアン・リンゲルマン氏によって提唱された理論で、グループの規模とプロジェクトに対する個人の貢献度が反比例の関係にあることを、以下の実験によってリンゲルマン氏含め示したとされています。
実験1:綱引き

「一人で綱引きをする」「複数人で綱引きをする」という2つのケースで、一人が綱を引く力に変化が起こるかを比較しました。
一人で綱を引く力を100%とした場合、2人で綱を引いた場合の一人当たりの力が93%、3人の場合は85%、4人の場合は77%、8人で綱を引いた場合の一人当たりの力が49%、となりました。
この実験結果によって、綱を引く人数が増えるごとに(無意識に)一人当たりが発揮する力が減少し、8人で綱を引いた場合の一人当たりの力は半分以下の49%しか発揮しなかった、ということが明らかになりました。
つまり、集団を構成する人数に反比例して、個人の貢献度が低下する傾向があり、「大人数でやった方が効率的」という従来の考え方と矛盾することを指摘しました。
実験2:チアリーダー

心理学者であるラタネ氏とダーリー氏は、チアリーダー2人にそれぞれ目隠しとヘッドフォンを着用してもらい、お互いの様子が分からない状態で、単独の場合とペアの場合で声量に変化があるかを実験しました。
その結果、ペアの場合は単独の場合と比較して94%の声量しか出ませんでした。
ですが、チアリーダーの2人は、どちらの場合も全力で声を出したという認識だったことから、集団作業における「手抜き」は、無意識に行われているということが、この実験によって明らかになりました。
リンゲルマン効果と傍観者効果の違い

リンゲルマン効果と類似した心理事象に『傍観者効果』というものがあります。
傍観者効果は集団心理の一つで、例として、ある事件が発生した際に目撃者の数が多いほど、その目撃者たちは「傍観者」となり、自身の周囲にいる傍観者と同化してしまい、当事者意識を失って率先して被害者の救助や通報などの行動を起こさなくなる、という心理事象です。
リンゲルマン効果は集団で行う作業に対しての無意識の「手抜き」ですが、傍観者効果は突発的な出来事に対しての意図した「行動」ということで違いはありますが、「誰かがやってくれるだろう」という意識が共通点として挙げられます。
傍観者効果はなぜ起こるのか?
上述の心理学者のラタネ氏とダーリー氏によると、「多元的無知」「責任分散」「評価懸念」の3つが複合的に作用して発生するとしています。
- 多元的無知
周りの行動に合わせて誤った判断をしてしまうこと。
「周囲の人が動いていないのだから」と、自分も行動しないという判断をすること。 - 責任の分散
周りにいる人たちと同じ行動をすれば、責任が分散するいう判断をすること。
集団の規模が大きいほど「自分が何もしなくても変わらない」という心理が働きやすくなります。 - 評価懸念
自身の行動が他者から批判されるリスクを心配すること。
「余計なことをすると迷惑と思われる」など、周囲の評価を気にすることで率先して行動できなくなってしまいます。
リンゲルマン効果と働きアリの法則の違い

北海道大学大学院 農学研究院の長谷川 英祐准教授が明らかにした『働きアリの法則』も、集団において活動に手を抜く・働かないという現象です。
『2:6:2の法則』とも呼ばれています(※1)。
『働きアリの法則』とは、集団は以下の3つのグループに分類できるというものです。
- よく働くアリ=全体の20%。よく働く。
- 普通に働くアリ=全体の60%。働きアリのように活動することもあるがしないときも。
- 働かないアリ=全体の20%。特に活動しない。
※1 #17 働きアリの群れには必ず、働かないアリがいる
「働かないアリ」に注目してアリの社会を研究している長谷川英祐さん(農学研究院 准教授)を研究室に訪ね、お話をうかがいました。 不思議な現象ですね イソップ寓話でも、アリは「働き者」として知られ...
元々経済学で用いられる用語ですが、働きアリだけでなく、人間社会や企業組織にもこの法則が成り立つとされています。
企業組織で想定した場合、集団を構成するメンバー間に基本的なスキルの差がなくとも、行動スピードが速くフットワークが軽い「よく働く」上位20%と「普通に働く」60%に仕事が集中するため、残り20%のメンバーの働きが悪くなるという「反応閾値(しきいち)」によってばらつきが発生するとされています。
「大人数でやった方が効率的」という考え方と矛盾する点で『リンゲルマン効果』と共通しますが、作業の偏りによって発生するという点では違いがあります。
リンゲルマン効果の発生による弊害
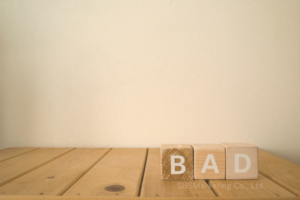
『リンゲルマン効果』が発生することによって、集団や組織の成長を鈍化させる・衰退を招く可能性があります。
具体的な弊害は以下の3つとされています。
生産性が低下する

手を抜く・怠けるメンバーが増えるほど、集団や組織全体の生産性が低下します。
生産性が低下することによって、企業組織であれば経営の悪化、集団であれば瓦解のリスクを伴うことになります。
モチベーションが低下する

集団や組織を構成するメンバーのモチベーション低下も引き起こしてしまいます。
人数が増えれば増えるほど、個々人への注目度や期待感が低下しがちです。
そのため、「注目されていない」「評価されていない」という感情が強まることになり、モチベーションが低下してしまいます。
そういったモチベーションの低いメンバーの手抜きがさらに増え、そんな環境下でも意欲を持って取り組むメンバーの負荷が高まり、意欲の低いメンバーも高いメンバーも離職のリスクが高まってしまいます。
フリーライダーが増加する
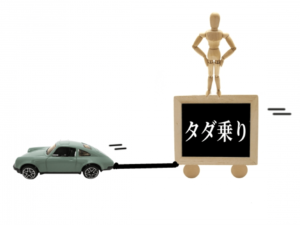
経済学用語である「フリーライダー」とは、ただ乗りを意味します。
「サボって集団や組織の掲げる目標達成に寄与していないのに報酬は他のメンバーよりも多くもらう」という「他人の挙げた成果にただ乗りする」人を指します。
こういったフリーライダーが増えてしまうと、他のメンバーの負担増加や、集団・組織全体のモチベーション低下につながってしまいます。
企業組織におけるリンゲルマン効果の発生例

企業組織の発生例としては「業務中のネットサーフィン」が挙げられます。
国際ニュース週刊誌『Newsweek』によると、アメリカ全土の就業者のうち「90%が業務中にネットサーフィンをしている」ということが分かりました。
もちろん、ネットサーフィンをしている=企業が停滞するというわけではありませんが、ネットサーフィンをしている時間を業務に傾ければ、就業者が所属する企業が発展する機会が生まれるはずです。
リンゲルマン効果が発生しやすい企業組織とは?

従業員の多い大企業
上述の通り、組織を構成する人数が多ければ多いほど、評価が自身に行き届いていないと感じやすく、注目されている実感が薄いとリンゲルマン効果が発生しやすくなります。
テレワーク・リモートワークを導入している企業
新型コロナウイルス感染対策を契機に、テレワークやリモートワークを導入する企業が増えました。
そのため、社員の仕事ぶりが目に見えにくい勤務形態が、リンゲルマン効果を誘発しやすい環境とも言えます。
リンゲルマン効果がなぜ発生してしまうのか?

集団や組織において「手抜き」というリンゲルマン効果が起きるのはどのような原因があるのでしょうか。
当事者意識が低い
集団・チームとして求められる成果目標が明確でも、個々人の目標や達成度が明確でなければ、無意識に「誰かがやってくれるだろう」と思いがちです。
また、個々人の役割が明確でも、自身のやるべきこと・ノルマを達成していれば、それ以上の成果に向けて積極的な行動を起こさないというケースも。
責任感の欠如
責任感を持って取り組まなければ、社内外からの信頼・信用を得ることができません。責任感が無い場合、やるべきことの効率を考えず、他人任せになりがちです。
集団・組織における同調バイアス
周囲の人々などの多数の意見や、行動の「常識」や「普通」「ルール」という価値観を、少数意見に暗黙的に強制する『同調圧力』・『同調バイアス』(※2)。
仮に集団・組織で『社会的手抜き』が発生すると、それが暗黙的な集団の規範となってしまい、自身の存在が浮くことを恐れて「周りの人が頑張っていないから、自分だけ頑張っても仕方がない」と同調バイアスがリンゲルマン効果を加速させてしまうリスクがあります。
※2 『同調圧力(同調バイアス)』については、こちらのページをご覧ください。
多数派が少数派に価値観を暗黙的に強制する『同調圧力』。なぜ発生するのか、メリットやデメリット、日本でよく見受けられる理由やビジネスへの応用について解説しています。
コミュニケーション不足
メンバー間のコミュニケーションが不足していると、所属する集団への帰属意識やメンバーへの仲間意識が欠落することにつながり、疎外感を感じるケースが増えて、やるべきことに意欲が湧かなくなり、社会的手抜きが生じることになってしまいます。
個々人への評価が不適切
人は他者から注目されている時の方が、パフォーマンスの質は高まります。
集団・組織全体だけでなく、自身という個々人の評価が適正にされているかわからなくなると、貢献しようという意欲は低下し、社会的手抜きが起こりやすくなってしまいます。
勤怠管理・人事システムの未整備
勤怠やモチベーションなどを管理するシステムが未整備だと「誰も見ていないから」と気が緩み、手を抜くケースも増えます。
リンゲルマン効果の予防策

リンゲルマン効果が発生すると、無意識に手を抜くメンバーが現れてモチベーションや生産性が低下してしまいます。
このリンゲルマン効果を発生させないための方法は以下の通りです。
集団・組織を少数精鋭体制にする
人数が増えるほど発生しやすくなるリンゲルマン効果。そのため、集団・組織を少人数にすることで、個人の責任が薄まらず評価の目が行き届くようになります。
役割分担を明確化して当事者意識を創出する
個々人に求める役割を明確にすることもリンゲルマン効果の発生を防ぐための方法です。
集団・組織において各人の役割分担を明確にすることで「誰かがやるだろう」という他人任せの意識を取り除くことができます。
自身のミッションを認識できるようになることで、集団・組織内で自身の存在価値を自己認識できるようになり、一人ひとりに当事者意識を持たせることができやすくなります。
成果や貢献度に応じた評価制度を取り入れる
一人ひとりが出す成果や貢献度といった仕事ぶりが評価に反映されない評価体制の場合、リンゲルマン効果が発生しやすくなります。
年功序列制度は特に若手メンバーのモチベーションを低下させてしまう大きな要因です。成果や貢献度を評価に反映する制度に切り替えることができれば、社会的手抜きを回避しやすくなります。
評価に反映させるために、成果や貢献度をより可視化する(・手抜きをしていないかをチェックする)システムを導入するのも、必要かもしれません。
「相互評価制度」を導入する
「他者から見られている」環境ではリンゲルマン効果は起こりづらいため、評価面でメンバー間で評価し合う制度を導入することが有効な一手となります。
上司・部下などさまざまな役職・立場の人が多面的に評価する「360度評価」などを取り入れる場合、貢献度の評価がより可視化でき、集団・組織間内のコミュニケーションの活性化にもつながります。
「1on1ミーティング」を実施する
上司と部下が定期的に話し合う「1on1ミーティング」の実施も、リンゲルマン効果抑止にとって有効と言えます。
個々人の目標に対する進捗や、困っていること・協力して欲しいことの共有、成果や課題のフィードバックなどを定期的に話し合うことで、協力関係を強化でき、手を抜かずにやるべきことに取り組める可能性が高まります。
認め合う・応援し合う環境づくり
同僚同士・上司と部下同士といった立場や役職の垣根を越えてお互いを認める・応援する環境は、前向きなアクションの大きな後押しになります。
「自分はこの集団・組織に欠かせない存在」と認識できるよう、関係性を築けるような環境づくりが大きなポイントになります。
最後に

無意識のうちに手を抜いてしまい、集団・組織にとって大きな弊害を起こしてしまう『リンゲルマン効果』。

発生を防ぐためには、『リンゲルマン効果』を理解し、集団・組織における個々人の役割の理解を促し当事者意識を高めて一人ひとりが自律的にやるべきことを管理する=セルフマネジメントを促しつつ、「認める」「理解してくれる」存在が集団や組織にいることを相互に理解することが、リンゲルマン効果の発生抑制につながります。
『リンゲルマン効果』を解説したこのページをまとめたPDFデータを無料でお送りいたします!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名」「メールアドレス」、「お問い合わせ内容」欄に『リンゲルマン効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。