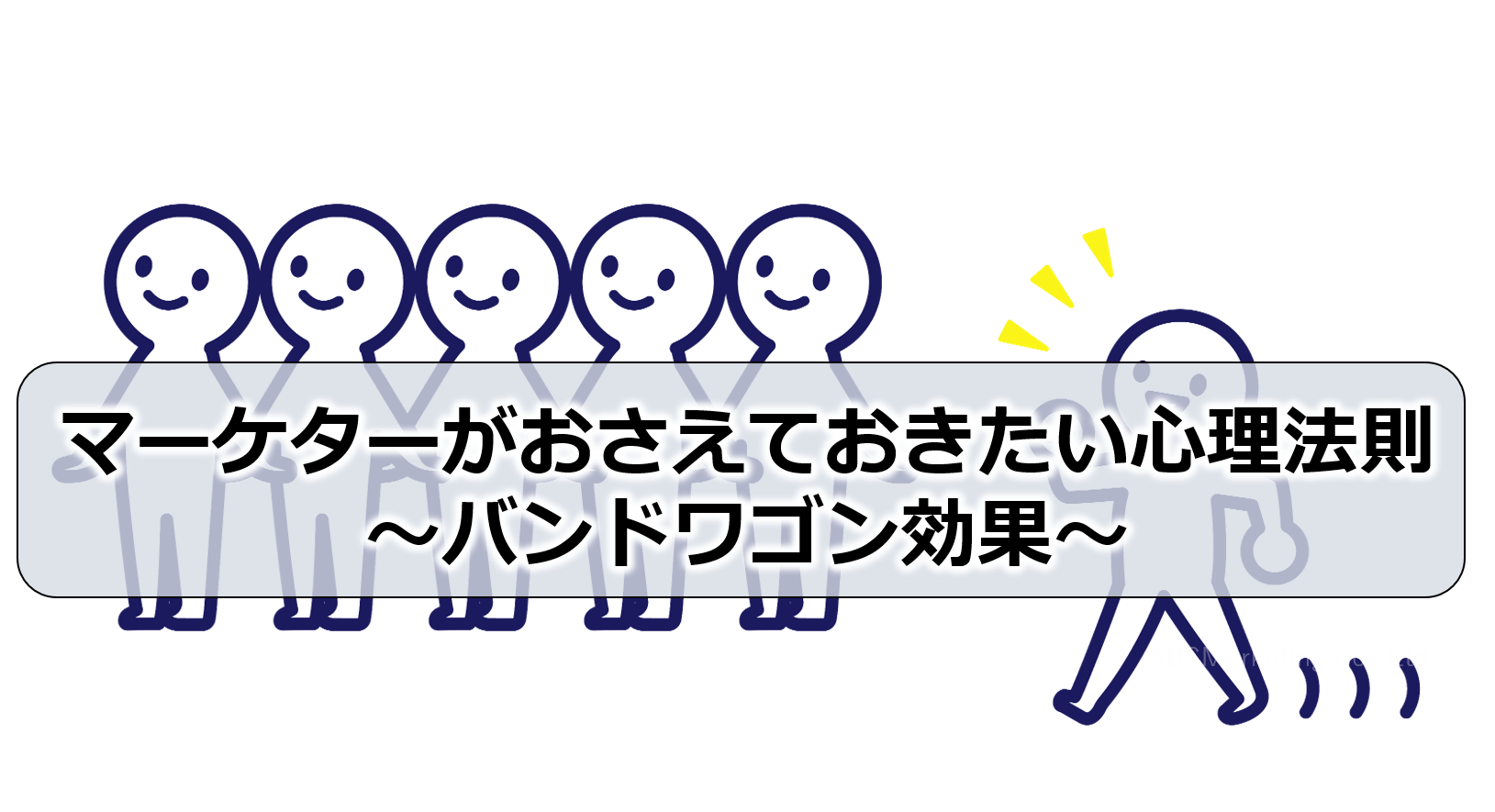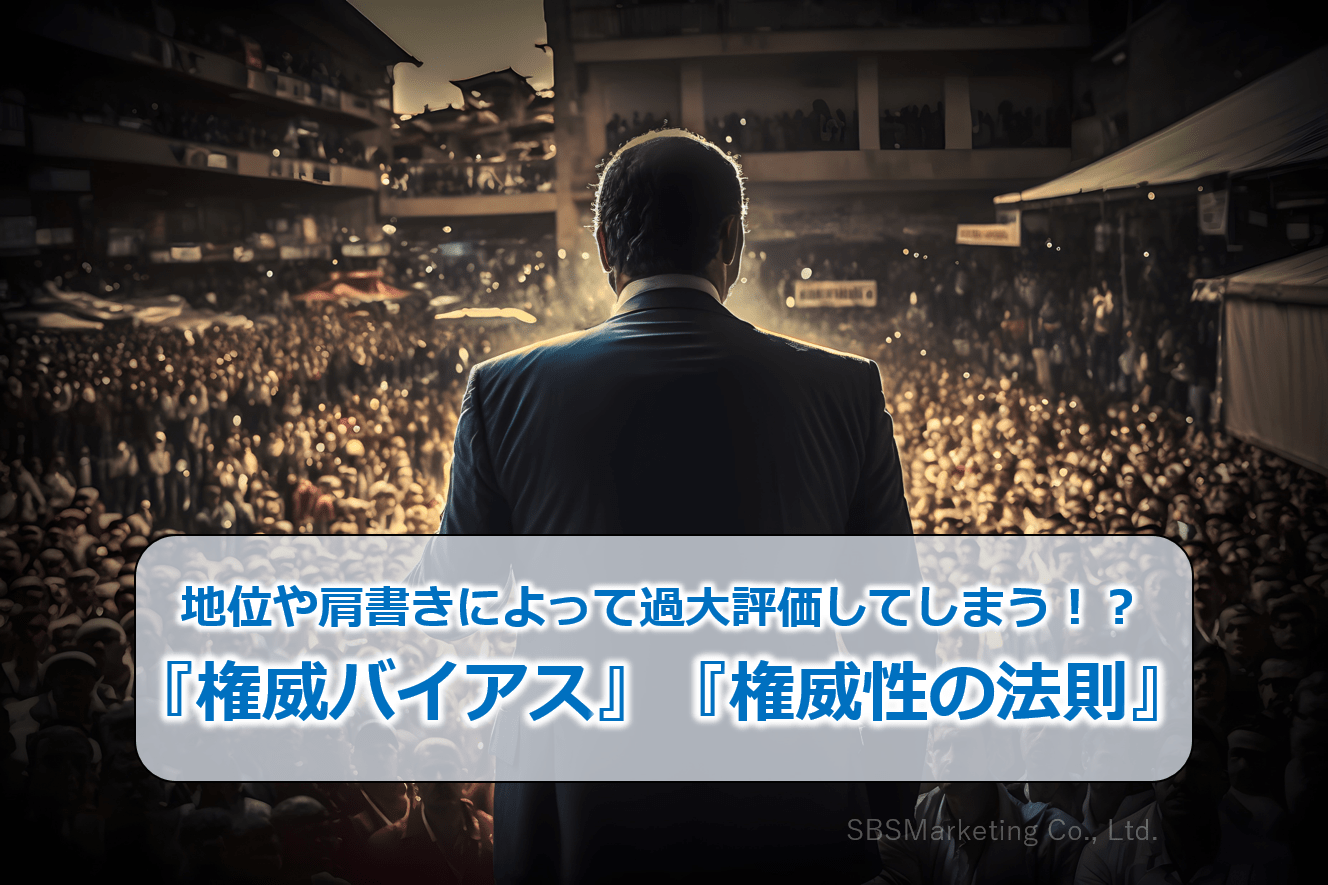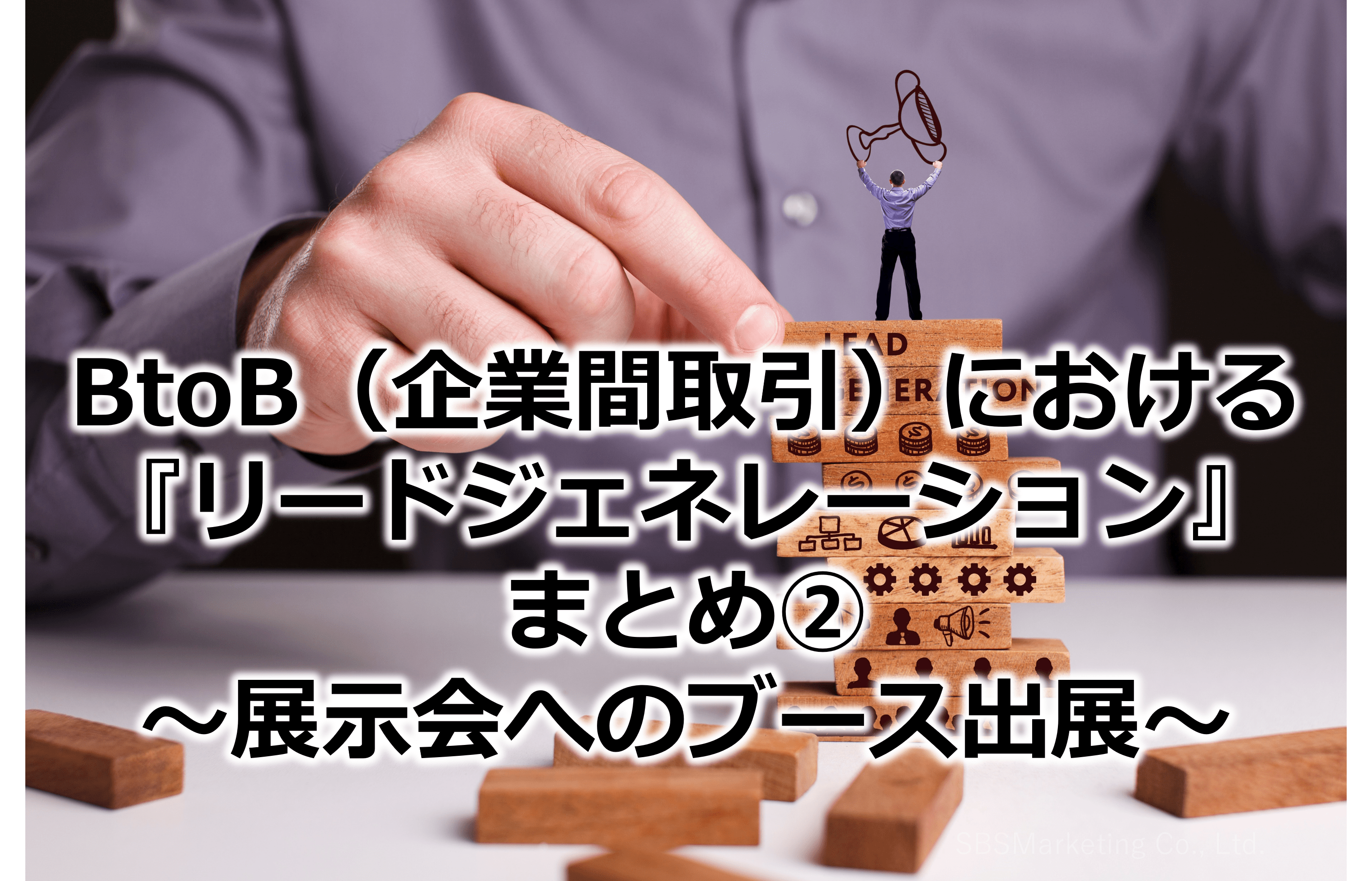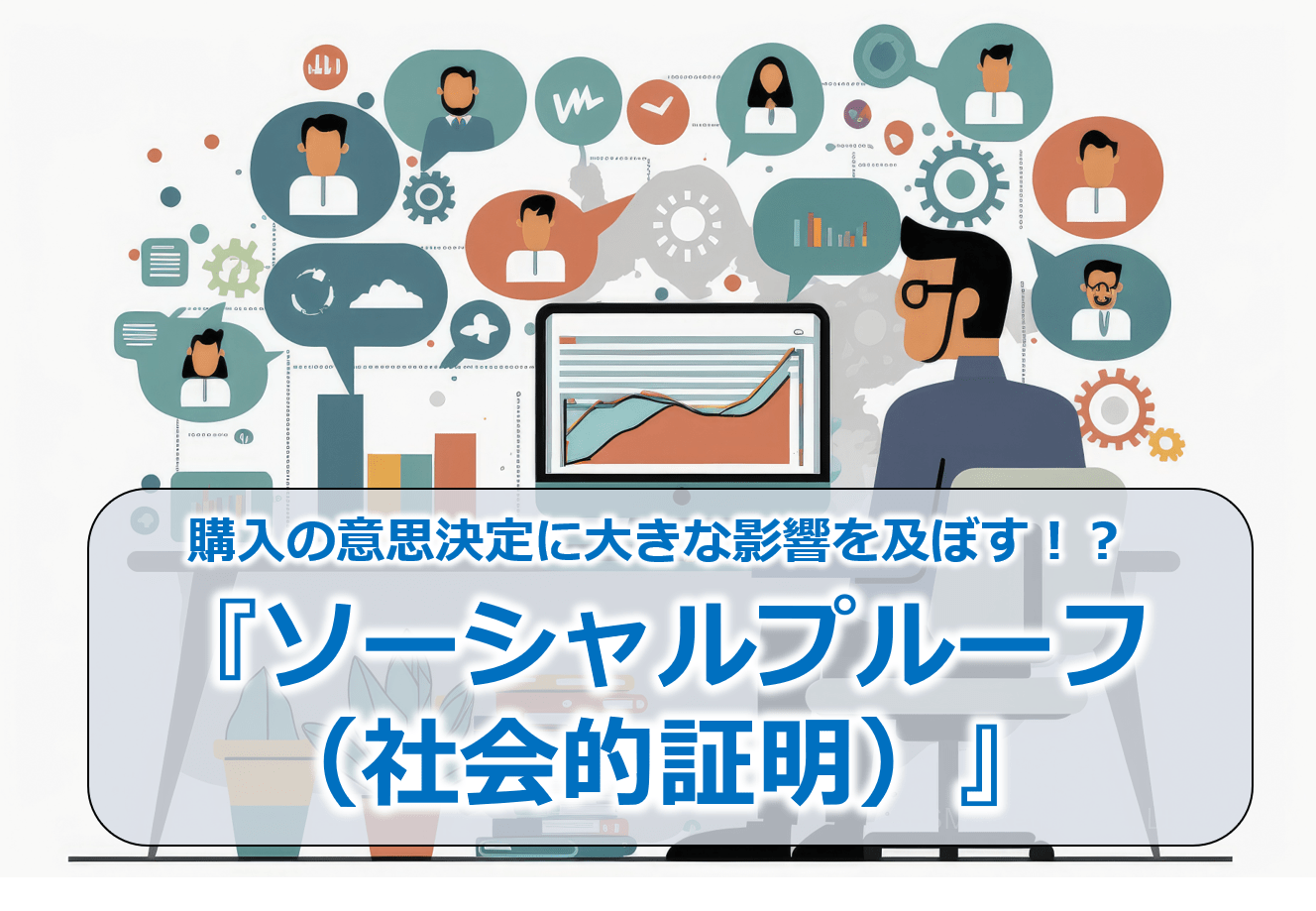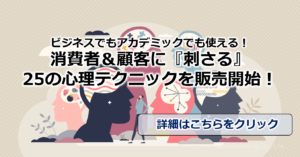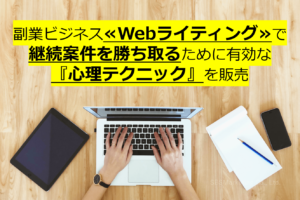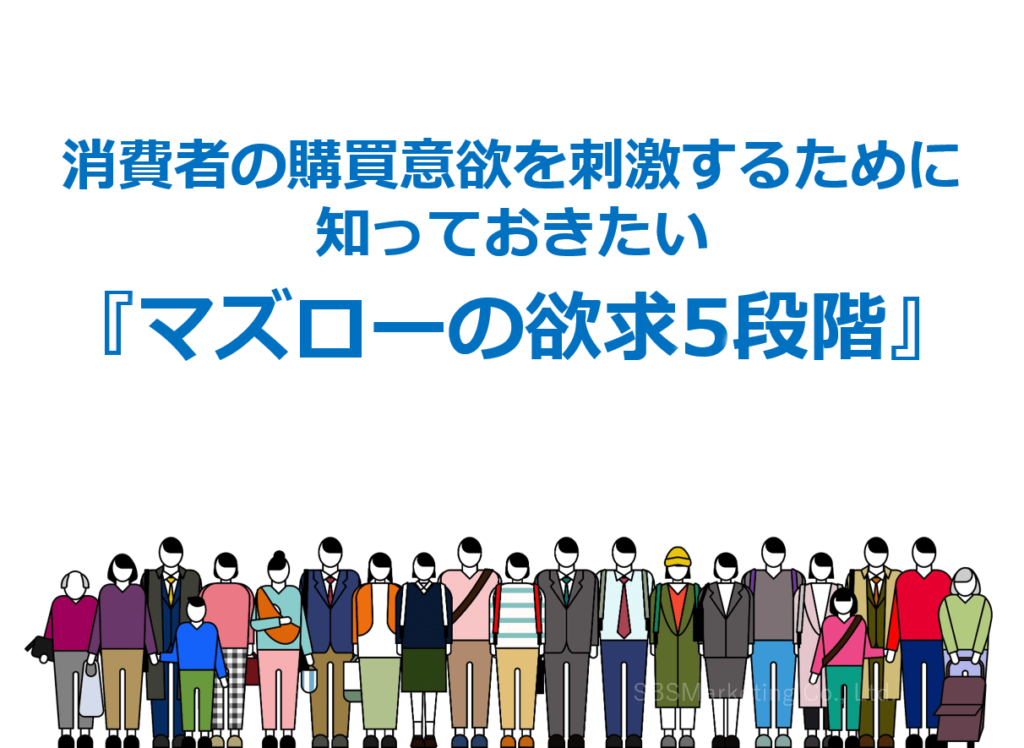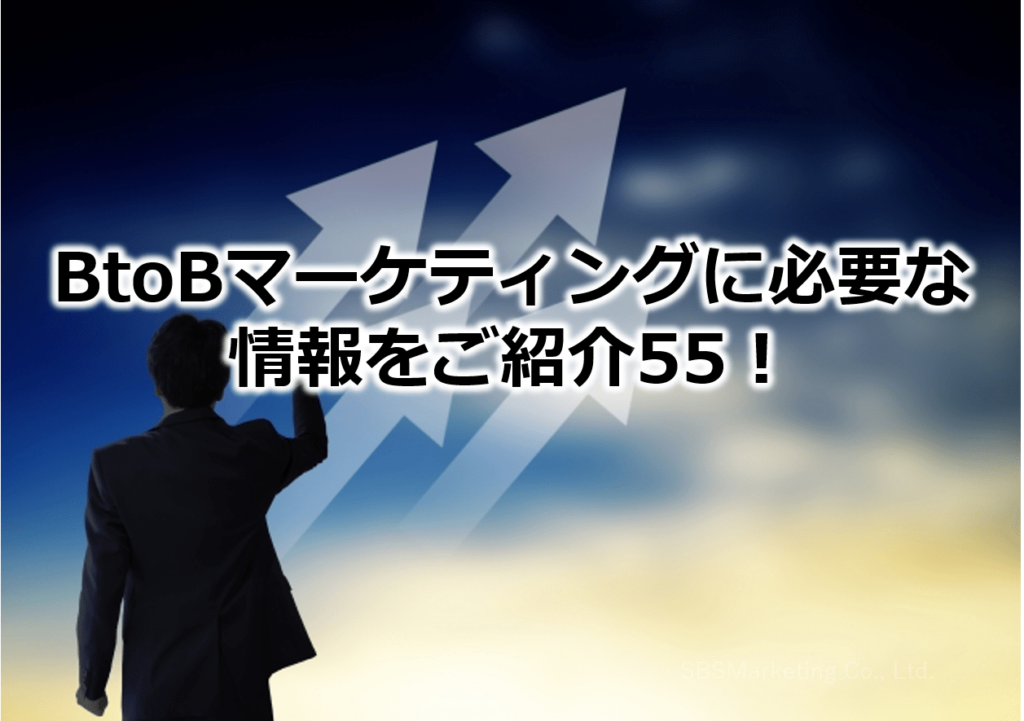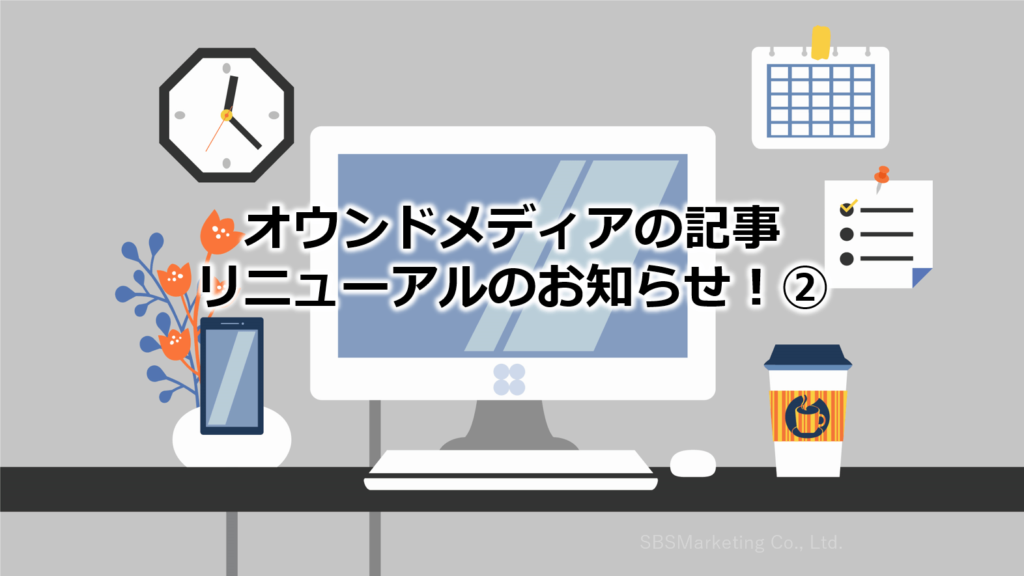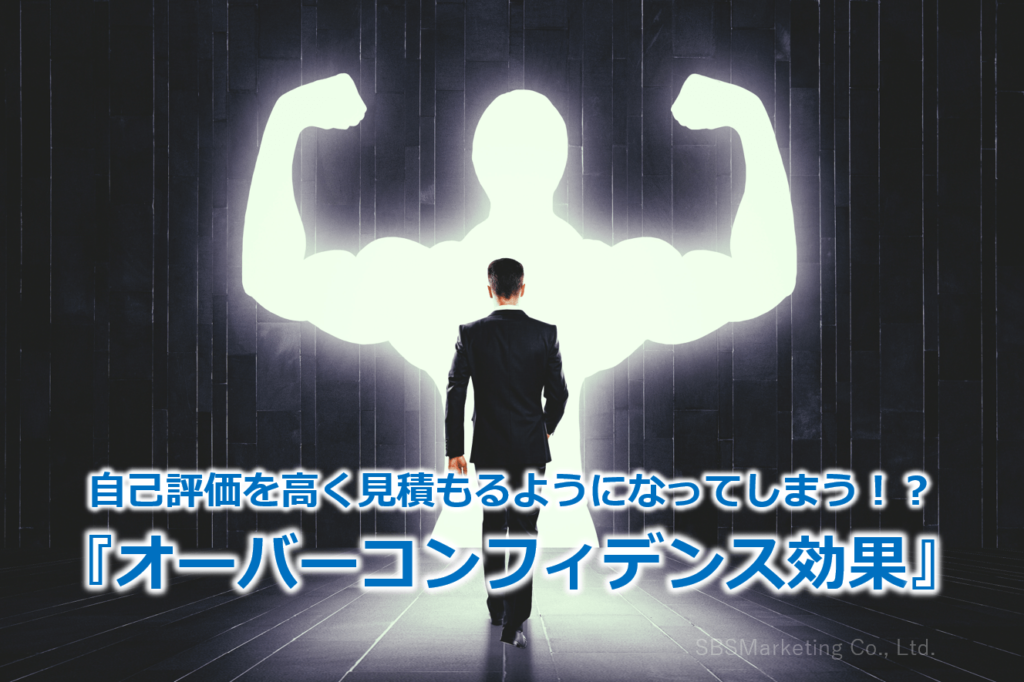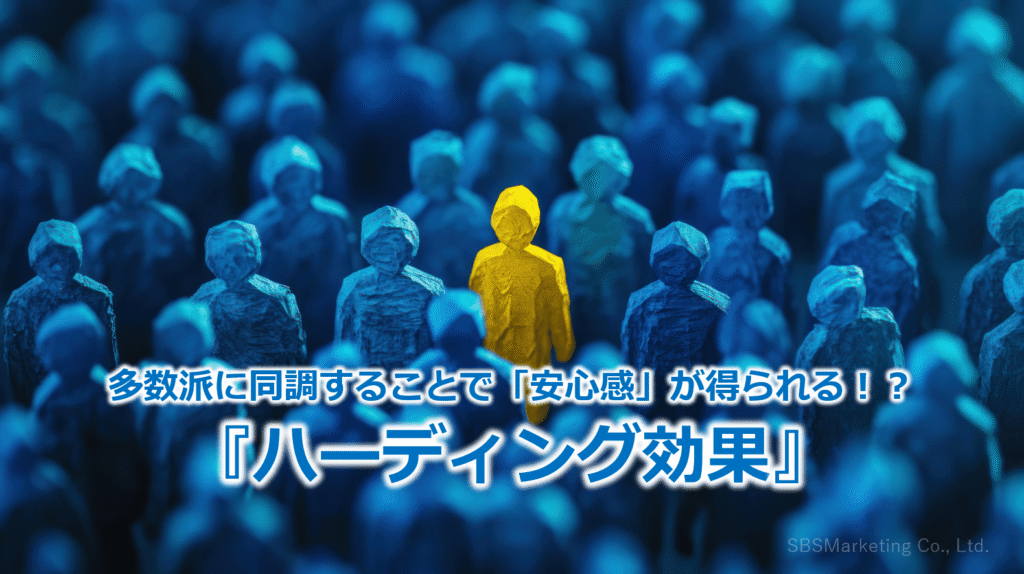
自分自身も多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』。
効果の概要と発生例、発生する原因(要因)やマーケティングへの活用例、ビジネスシーンに活用する際の注意点などについて解説しています。
『ハーディング効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『ハーディング効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『ハーディング効果』とは?
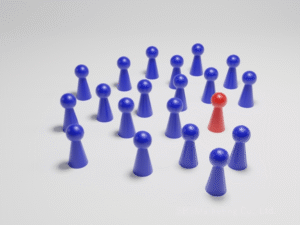
『ハーディング効果(Herding effect)』とは、多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする心理現象のことです。
人は、合理性を踏まえて自分の判断が正しいと思っていても、周囲の人と異なっていると不安になり同調しようと流されてしまう傾向があります。
そういった傾向によって、「集団の一員」として同調し、多数派に従い孤立感を避けようとするようになるわけです。
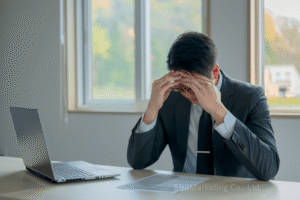
自身が同調する多数派・集団の判断が非合理であった場合、多数派に組み入ることを優先するあまり、自身の合理的な判断や情報を無視して賛同してしまうケースもあります。
名称の由来

「ハーディング(Herding)」とは、動物の「群れ」という意味で、人間が群衆の中で同様の行動や判断をすることをあらわしています。
アメリカ合衆国の小説家、詩人、評論家である、エドガー・アラン・ポーの小説『群衆の人』にインスパイアされた論点と言われています。
効果を実証した実験例

『ハーディング効果』の実験例として、心理学者のソロモン・アッシュによる「アッシュの同調実験」というものが知られています。
この実験は、1グループ7人で行いますが、そのうち6人は「サクラ」です。
実験の参加者には、まず基本となる長さの直線が描かれたカードと、長さの異なる直線が数本描かれたカードを見せ、その中から基準の長さと同じものをそれぞれに選んでもらいます。
その際、サクラの参加者たちが「明らかに誤った答え」を選んだとしても、被験者の75%は「サクラの回答に同調する」という結果が得られました。
『バンドワゴン効果』との関係性

この『ハーディング効果』と『バンドワゴン効果』は、どちらも「多数派に同調する」心理事象ですが、『バンドワゴン効果』は「人気がある」「流行に乗り遅れたくない」という心理が背景にありますが、『ハーディング効果』の背景には「安心感」があり、その点が違いと言えます。
- バンドワゴン効果・・・「安心感を得たい」
- ハーディング効果・・・「人気がある」「流行に乗り遅れたくない」
※『バンドワゴン効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
バンドワゴン効果とは? バンドワゴン効果とは、経済学者であるライベンシュタインが1950年の論文の中で提示した行動心理学の事象の1つです。 「バンドワゴン」とは行列の先頭を行く「楽隊車」を意味し、「みんなが持っているなら …
『セルフハーディング効果』

周囲の集団の行動や判断だけでなく、自分の過去の行動や判断に影響を受ける『セルフハーディング効果』という現象もあります。

例としては、あるサプリを以前に摂取した際、「体の調子が良くなった」と感じた経験から、同じサプリを摂取し続けることが習慣になっている、というケース。
特に「過去に自分が選択した行動や判断が正しかった」と成功体験として認識し、同様の行動や判断を繰り返したり「習慣化」することで安心感を得る、というケースが考えられます。
科学的な根拠があるかどうかではなく、自身の経験上の効果によって『セルフハーディング効果』は成立する傾向があります。
『ハーディング効果』の発生例
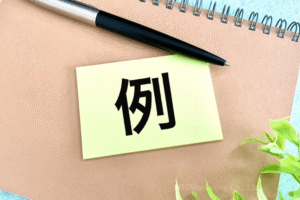
この『ハーディング効果』は、日常生活でも多く見かける心理現象です。
- 人気の飲食店を選ぶ
- 評価の高い商品が欲しくなる
- 「赤信号」なのに渡ってしまう
- 評価の高い銘柄に投資してしまう
- 特定の政治家・政党に扇動されてしまう
人気の飲食店を選ぶ

日常生活の例としては、飲食店を選ぶ際、行列ができている店や予約の取りづらい店に行きたくなる。
また、レストランで周りの人たちが同じ料理を頼んでいるのをみると、「(その料理は)きっと美味しいんだろう」と判断して、自分も同じ料理を注文してしまう。
評価の高い商品が欲しくなる
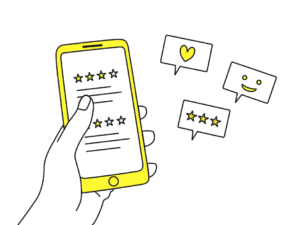
周りの友人たちが持っているアイテムを欲しくなったり、流行のファッションを自分も購入するケースも、『ハーディング効果』の一例と言えます。
また、オンラインショッピングにおいて、高いレビュー数や評価を受けている商品を購入するというケースも当てはまります。
「赤信号」なのに渡ってしまう
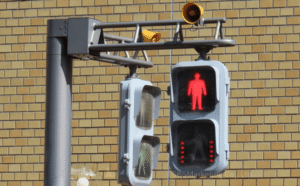
周囲の人が赤信号で渡っていると、自分も思わず渡ってしまう。
評価の高い銘柄に投資してしまう

株式投資などにおいて、多くの人が「良い銘柄」だと評価していると、自分も投資してしまう。

ちなみに、2008年にアメリカの投資銀行である、リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻を端に起こった金融危機「リーマンショック」も、投資家の中で「サブプライムローン」関連商品の購入が過熱したことで、『ハーディング効果』が起きて生じたと考えられています。
特定の政治家・政党に扇動されてしまう

政治において、過激な発言などで民衆を扇動する場合にも、自分の周囲の支持者と同調して「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』が生じていると言えます。
なぜ『ハーディング効果』が発生するのか?

多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』が発生する要因としては、以下の3つが挙げられます。
- 「少数派」になることへの不安
- 周囲の人の意見や行動を「自身の判断の裏付け」にする傾向
- 「自己肯定感」を高めたい
「少数派」になることへの不安

『ハーディング効果』の「周囲の人と同様の行動や判断をしたがる」背景には、「少数派であることへの不安」があると考えられます。
人間には「孤立したくない」「集団の一員として認められたい」という心理的傾向があります。
この傾向によって、少数派になることを避けるために、多数派の行動や判断に同調しようとするわけです。
周囲の人の意見や行動を「自身の判断の裏付け」にする傾向

人間には、周囲の意見や行動を、自分自身の判断を裏付ける情報として捉えようとする傾向があります。
特に、専門家などの権威性のある人物の意見や行動により強く影響を受けます。
この現象は、『権威バイアス』『権威性の法則』と言えます。
※『権威バイアス(権威性の法則)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
権威がある地位や肩書きによって、その人物や言動に対する評価が高く歪められてしまう『権威バイアス』『権威性の法則』。なぜ効果が発揮するのか、ビジネスシーンでの活用例などについて解説しています。
「自己肯定感」を高めたい

人間に備わっている、周囲の人々と同様の行動をとったり意見に同調することで、自分自身を正当化し「自己肯定感」を高めようとする傾向も『ハーディング効果』の発生要因の1つと言えます。
マーケティング施策への活用例

『ハーディング効果』をマーケティング施策に活用することで、商品やサービスに対する購買意欲を高めやすくなります。
- 「期間限定」や「数量限定」
- 展示会ブースの「人だかり」
- 『ソーシャルプルーフ』として活用する
- 『キューイングストラテジー』として「混み具合」を活かす
- 『インフルエンサーマーケティング』
「期間限定」や「数量限定」

「期間限定」や「数量限定」を謳うことで、多くの人がその商品やサービスを選んでいると思わせ、購入を促すことにつながります。
展示会ブースの「人だかり」
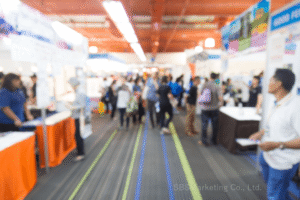
展示会の出展ブースにおいて、ブース内の「人だかり」が来場者の興味をそそり、惹きつける要因となります。
※ちなみに、展示会への出展の際におさえておくべきポイントについては、こちらのページをご覧ください。
『展示会』にもオンライン化などの変化の波が起こっていますが、オンライン・オフライン出展問わず展示会へのブース出展施策を実施するまえにおさえておきたいポイントを解説しています。
『ソーシャルプルーフ』として活用する

多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』は『ソーシャルプルーフ(社会的証明)』として活用可能です。
商品やサービスの紹介ページにポジティブなレビュー投稿が多ければ、『ソーシャルプルーフ』が作用しそれらの評価を参考にして購入判断しやすくなる効果が見込まれます。
※『ソーシャルプルーフ(社会的証明)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
周囲の人の意見や行動といった社会的評価に重き(信頼)を置いて、自分自身の判断や行動に妥当性を持たせようとする『ソーシャルプルーフ』。なぜ発生するのか、7つの活用例、獲得するための方法などについて解説しています。
『キューイングストラテジー』として「混み具合」を活かす

システムが効率的に情報を処理するために、待ち行列(キュー)として並べ、順番に処理することで効率化する『キューイングストラテジー』。
この発想を利用して、オフラインであれば店舗へと続く長い行列、オンラインであればWebサービスやオンラインゲームなどで「待機中のユーザー数」を表示することで、それを見た人に「多くの人がその商品・サービスを求めている」と伝えることが可能になります。
『インフルエンサーマーケティング』

マスメディアによく出る有名人や、SNSなどで影響力のある「インフルエンサー」が商品やサービスを推奨・推薦することで、その人物のファン・フォロワーを中心に購入率が高まりやすくなります。
↓
この続きでは、『ハーディング効果』をビジネスシーンに活用する際の注意点などについて解説しています。
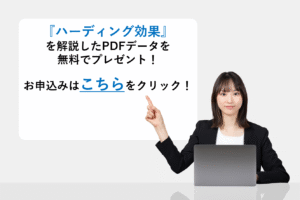 『ハーディング効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
『ハーディング効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『ハーディング効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
- BtoBマーケティング
- Herding effect
- アッシュの同調実験
- イノベーション
- インフルエンサーマーケティング
- キューイングストラテジー
- セルフハーディング効果
- ソーシャルプルーフ
- ハーディング効果
- バンドワゴン効果との関係性
- ビジネスチャンスを逃すリスク
- ブースの人だかり
- マーケティング施策への活用例
- リーマンショック
- 人気の飲食店を選ぶ
- 多数派に同調して安心感を得ようとする
- 孤立感を避けようとする
- 少数派になることへの不安
- 待ち行列
- 扇動される
- 数量限定
- 期間限定
- 株式会社SBSマーケティング
- 権威バイアス
- 権威性の法則
- 機会損失が生じやすい
- 活用する際の注意点
- 発生する要因
- 発生例
- 社会的証明
- 群衆の人
- 自己肯定感
- 虚偽の情報
- 評価の高い商品が欲しくなる
- 評価の高い銘柄に投資してしまう
- 誇大広告
- 非合理な判断をしてしまうリスク
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。