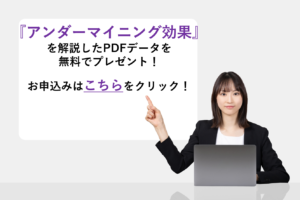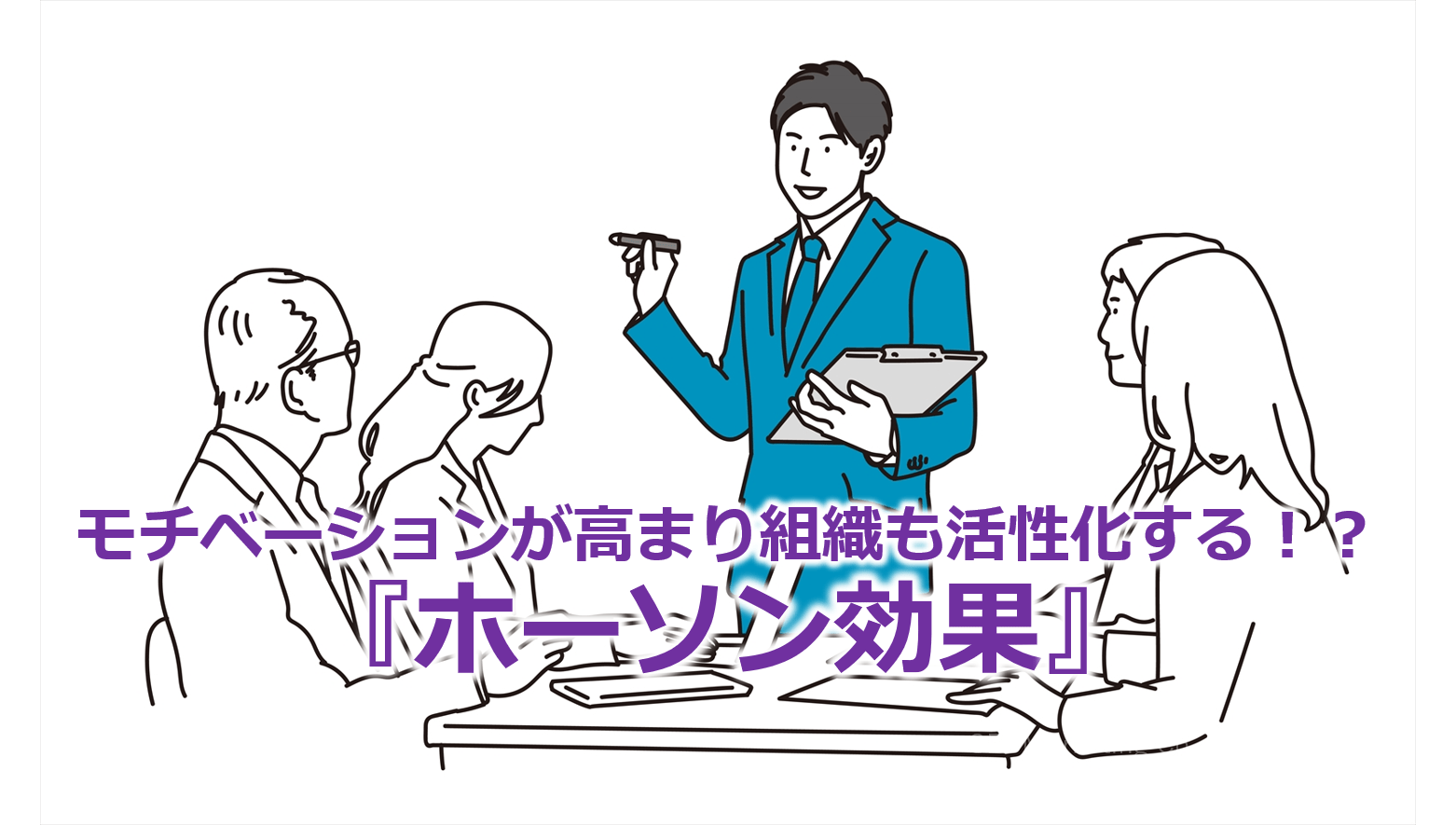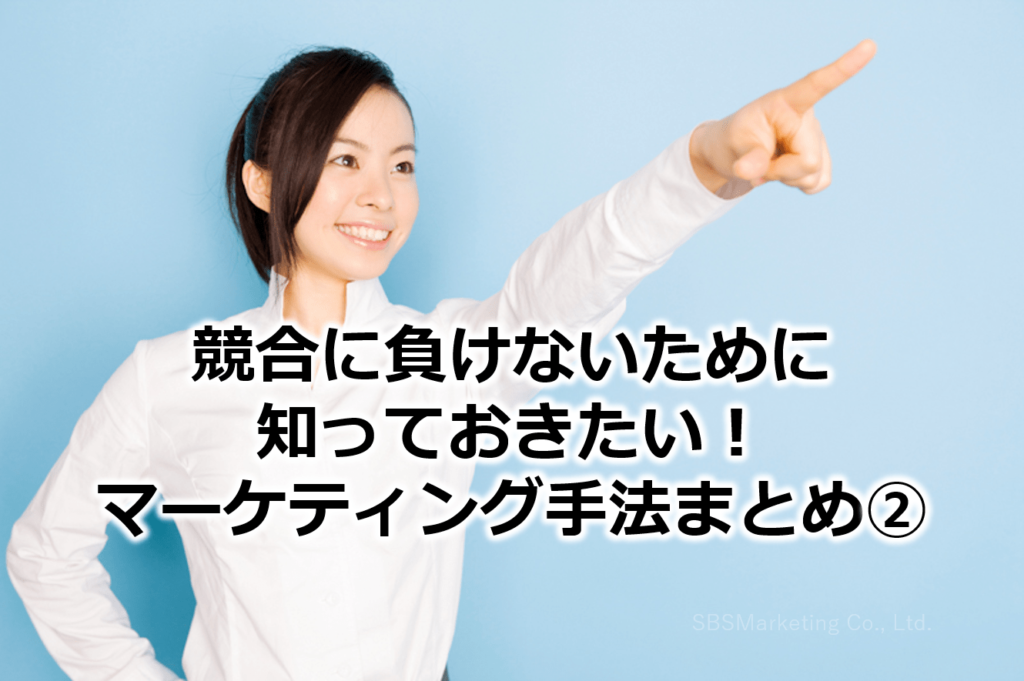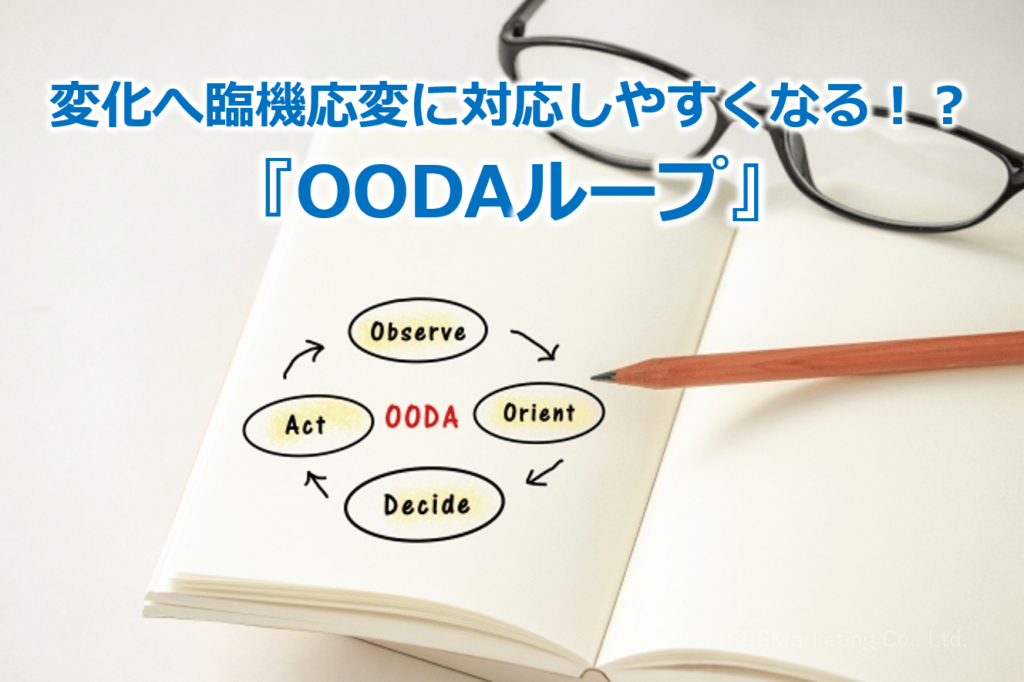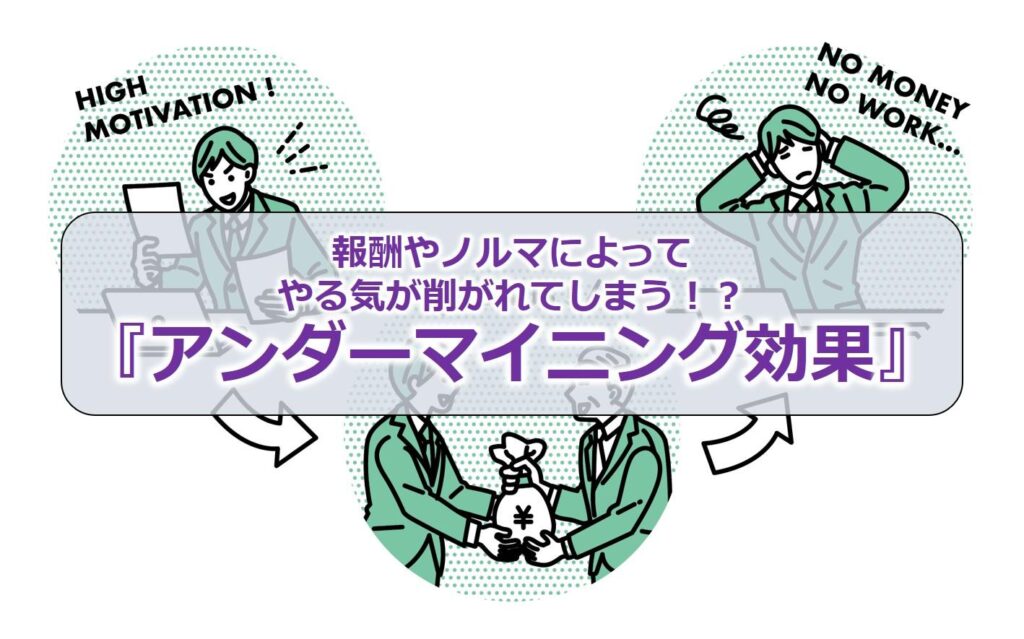
やりがいや満足感を得るために自発的に手掛けていた行為に、金銭といった物質的な報酬などを与えてしまうことで、モチベーションを削いでしまう『アンダーマイニング効果』。ビジネスシーンで発生する要因や具体的な影響、予防策について解説しています。
『アンダーマイニング効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『アンダーマイニング効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『アンダーマイニング効果』とは?
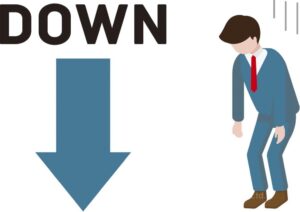
アンダーマイニング効果(Undermining Effect)とは、やりがいや満足感を得るために自発的に手掛けていた行為に、金銭といった物質的な報酬などを与えてしまうことで、モチベーションを削いでしまう心理事象を指します。
別名、『抑制効果』『過正当化効果』とも呼ばれています。
より具体的に言うと、「達成したい」「やり遂げたい」という内発的動機付けによって行動することに対して、「報酬を与える」「評価をする」また逆に「圧力をかける」「罰を与える」などの外発的動機付けによって、「報酬を受けること」「圧力を回避すること」が目的となり、内発的な動機が失われて、外発的動機付けがないとやる気が削がれてしまうという事象です。

例えば、元々はボランティアでやっていたことに対して、金銭報酬を受け取ってしまったことで、目的が「お金」に変わってしまい、報酬が無いとモチベーションが低下してしまうというケースが挙げられます。
『アンダーマイニング効果』の由来

アンダーマイニング効果は、アメリカの心理学者であるエドワード・L・デシ 氏とマーク・R・レッパー 氏によって、1971年に提唱されました。
両名は当時、流行していた「ソマパズル(立体パズル)」を用いて、大学生を2つのグループに分けて3つのセッションで実験を行い、この心理事象を実証しました。
セッション1:それぞれのグループにパズルを解いてもらう。
↓
セッション2:1つのグループにはパズルが解けるたびに報酬を与え、もう1つのグループには何も告げず報酬も与えない。
↓
セッション3:再びそれぞれのグループにパズルを解いてもらう。報酬はどちらにも与えない。

この実験の結果、何も報酬を与えられなかったグループはパズルに触れる時間の変化は見られず、報酬を与えられたグループのみパズルに触れる時間が減少しました。
報酬を与えられたグループは「パズルを解く=報酬を得るため」と感じるようになり、内発的な動機が失われモチベーションが低下してしまうことがわかりました。
『アンダーマイニング効果』を理解する際に必要な2つのポイント

アンダーマイニング効果を知るうえでポイントとなるのが、『内発的動機付け』と『外発的動機付け』です。
『内発的動機付け』

『内発的動機付け』とは、好奇心や探求心、向上心など、本人の内面から発生する動機付けのことです。
「うまくなりたい」「スキルアップしたい」「時間を忘れて取り組みたい」という、やりがいや興味などの自発的な意欲が例として挙げられます。
『外発的動機付け』

『外発的動機付け』とは、外部から与えられる動機付けのことです。
「第三者から褒められる」「報酬を与えられる」「評価をされる」「〆切やノルマ・罰則を設けられる」など、他者からの干渉によって発生するものが例として挙げられます。
ビジネスシーンで発生してしまう原因

元々はやりがいを持って実施していたが、外部から動機付けをされたことで「見返りのための手段」に変わってしまい、「見返りがなければやる意味がない」と考えるようになり、モチベーションが低下してしまう『アンダーマイニング効果』。
ビジネスシーンで考える場合、例えば実行するタスクに対する報酬制度や評価制度の存在は有用と考えがちですが、対象となるメンバーの資質やタイミングによっては逆効果になってしまいます。
また、このアンダーマイニング効果に陥ってしまっていることを、マネジメントをする人間もされる人間も気づかないケースが少なくありません。
「業務成果」に報酬を与える

業務に対するモチベーションを高めるために、成果を出したメンバーに報酬を与える制度を設けることは一般的ですが、当初は業務を遂行することへの使命感や、やりがいで実施していたとしても、その行為に報酬が与えられるようになると、「報酬を得ること」が目的に変化してしまいます。
そのため、報酬制度などを取り入れる際には、『内発的動機付け』を損なわないようにしなければなりません。
「業務への取り組み」を評価する

成果ではなく、業務に取り組む姿勢を評価するケースもありますが、メンバーによっては「高い評価を受けたい」「周囲から尊敬されたい」という欲求が先行してしまい、自発性を損なうリスクが高まってしまうので注意が必要です。

ちなみに、「周囲から尊敬されたい・評価されたい」≒他者から関心を持ってもらう・注目を浴びることで、モチベーションを高めて結果を出そうと頑張るようになる心理事象のことを『ホーソン効果』(※)と呼びます。
※『ホーソン効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
関心を持ってもらったり注目を浴びることによって結果を出そうと努めるようになる『ホーソン効果』。発生するメカニズムとビジネスシーンでの活用例、注意点をまじえて解説しています。

例えば、何らかの目標を達成したら表彰する制度を設ける、「社内で特別視されたい」という欲求をかきたてるような特別なプロジェクトチームを設立する、などがこの『ホーソン効果』を生じさせます。
「〆切やノルマ・罰則」を設ける

目標を達成させるための手段として、「〆切やノルマ・罰則を設ける」ことも、『アンダーマイニング効果』を発生させる要因となってしまいます。
「〆切やノルマ・罰則」という『外発的動機付け』は、短期的にはモチベーションアップなどの効果を発揮しますが、持続性に乏しく、〆切やノルマをクリアできなかった場合にストレスを生じさせてしまう、というリスクがあります(とはいえ、ビジネスである以上、〆切は必要ですが。。)。
ビジネスに及ぼす具体的な影響

『アンダーマイニング効果』がビジネスに及ぼす具体的な影響はさまざまありますが、代表例としては以下の3つが挙げられます。
生産性が低下する
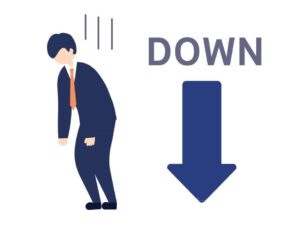
モチベーションなく取り組むことになるため、集中力も下がり生産性が低下することになってしまいます。
職場の人間関係が悪化することも

仮に報酬制度や評価制度を設けると、競争意識が行き過ぎることもありますし、おのずと業績の良いメンバーと悪いメンバーが生まれ、職場の人間関係が悪化することも。
退職率が上がってしまう

業務に対するモチベーションが低下することで、退職を考えるメンバーが増えることにもつながってしまいます。
↓
この続きでは、『アンダーマイニング効果』を発生させないための3つの方法などについて解説しています。
『アンダーマイニング効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『アンダーマイニング効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。