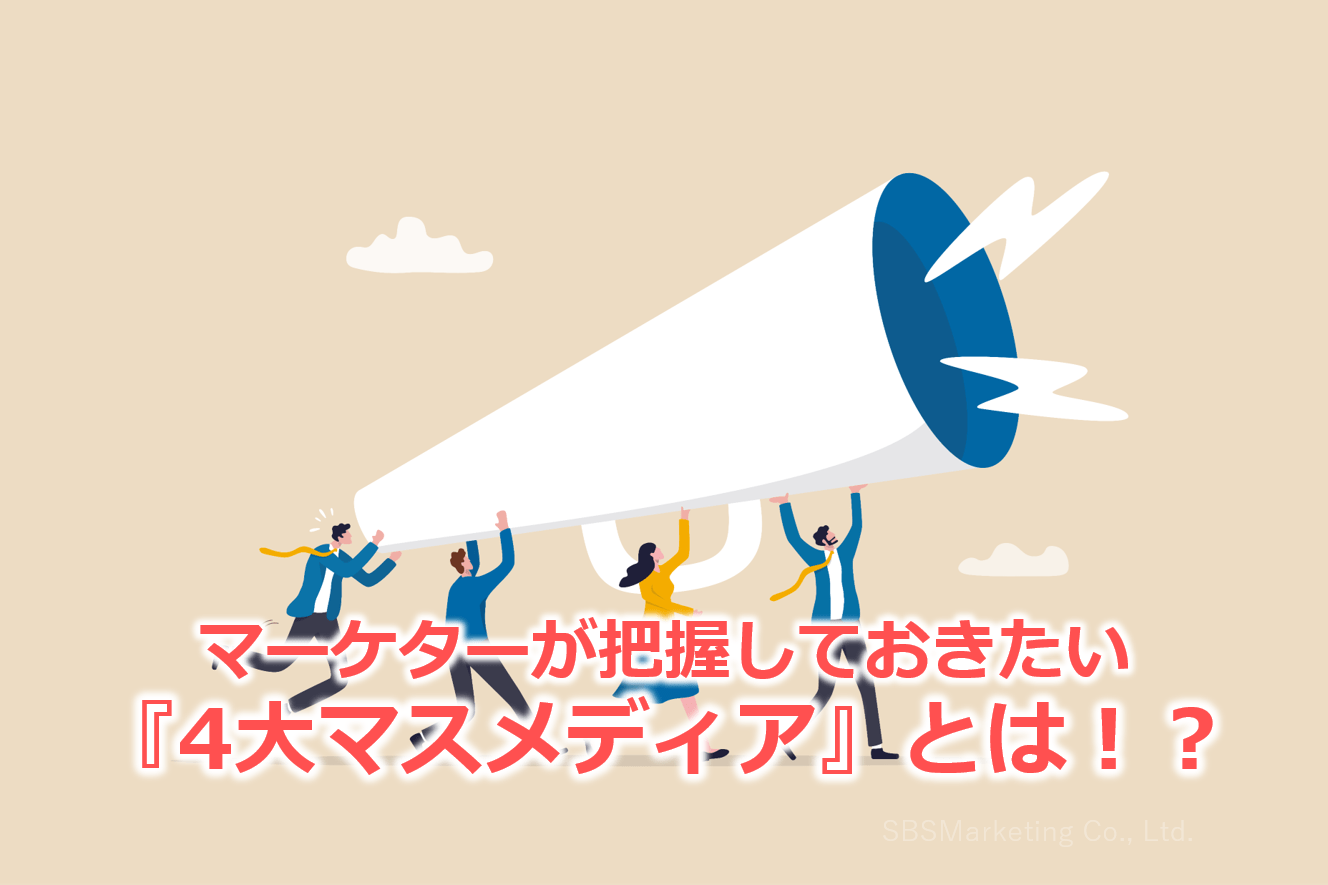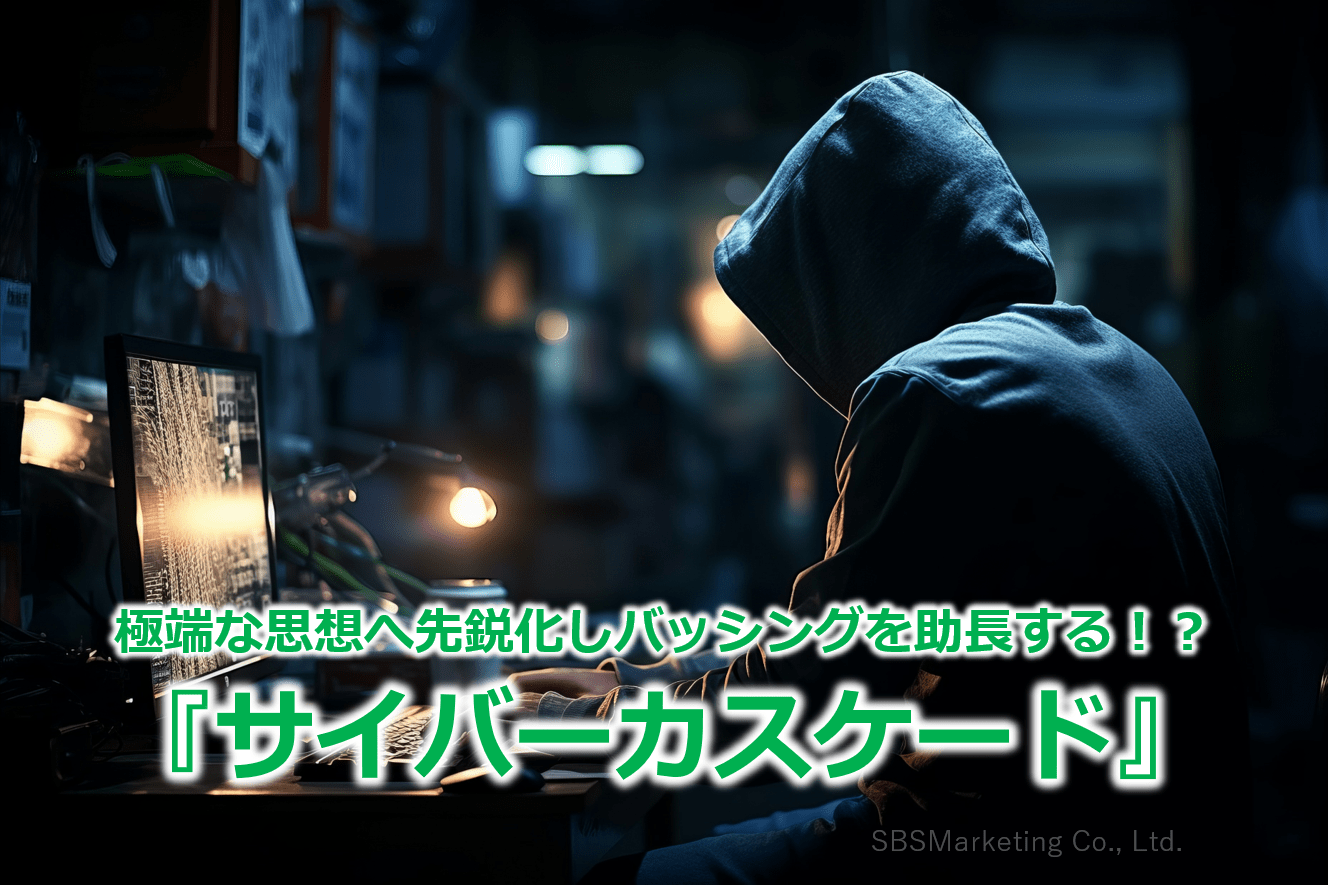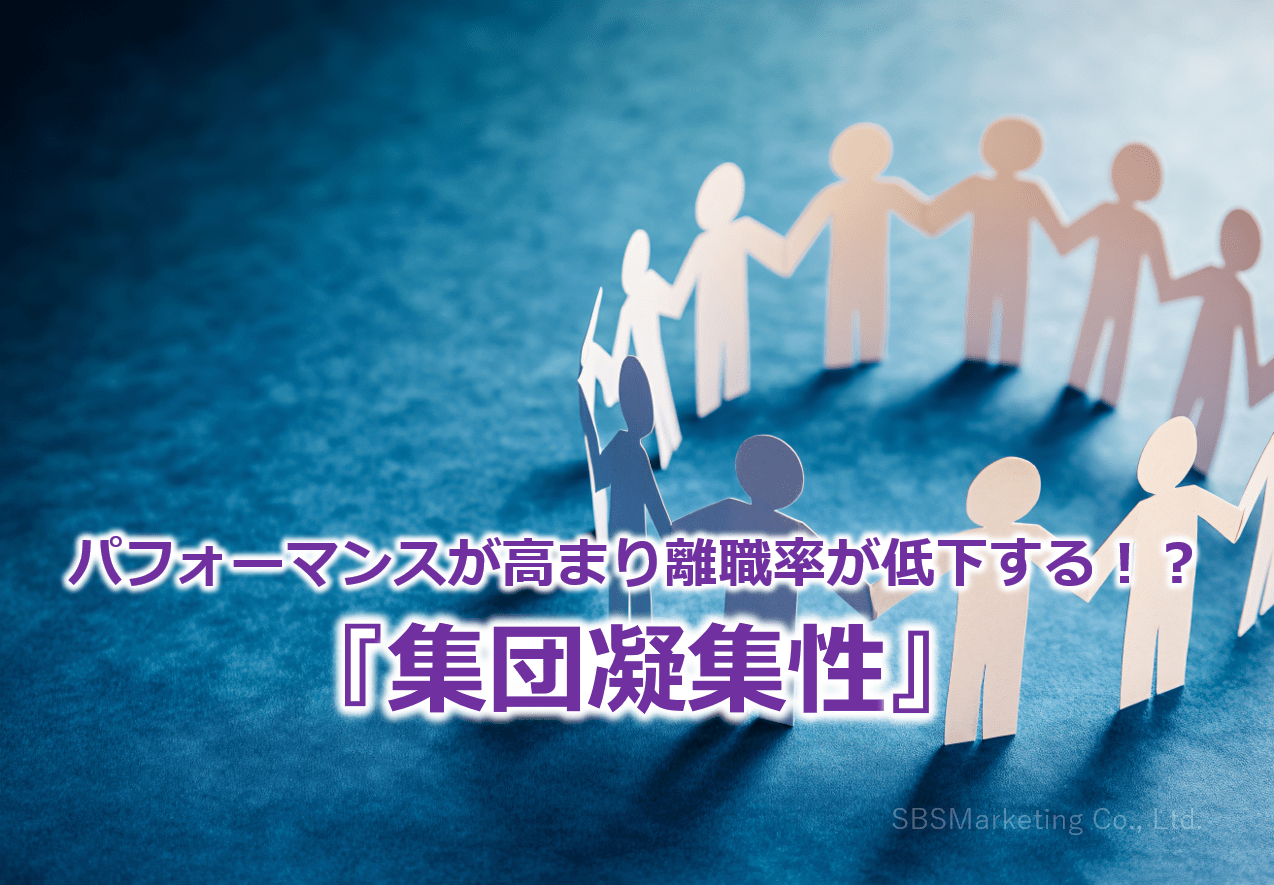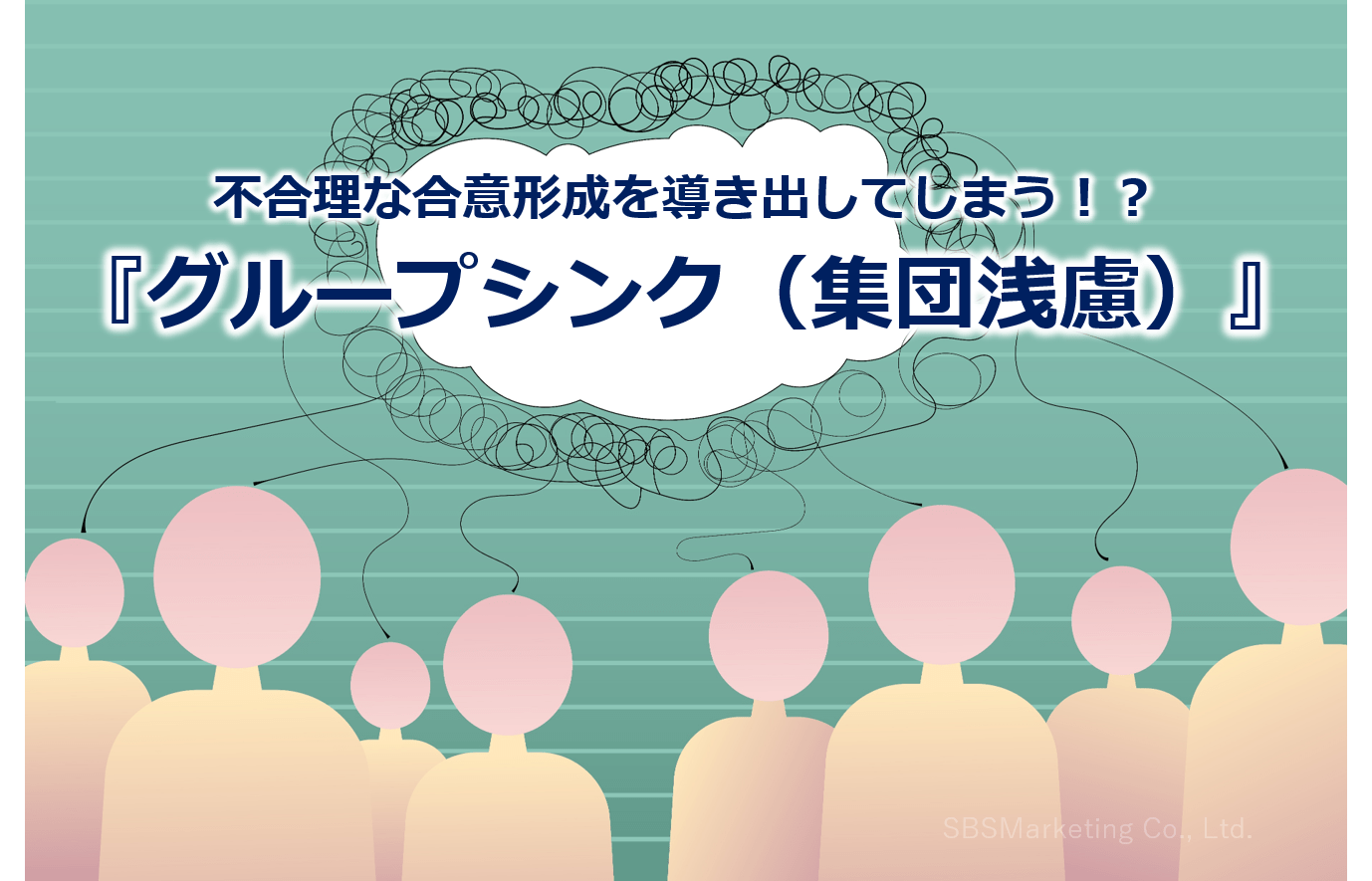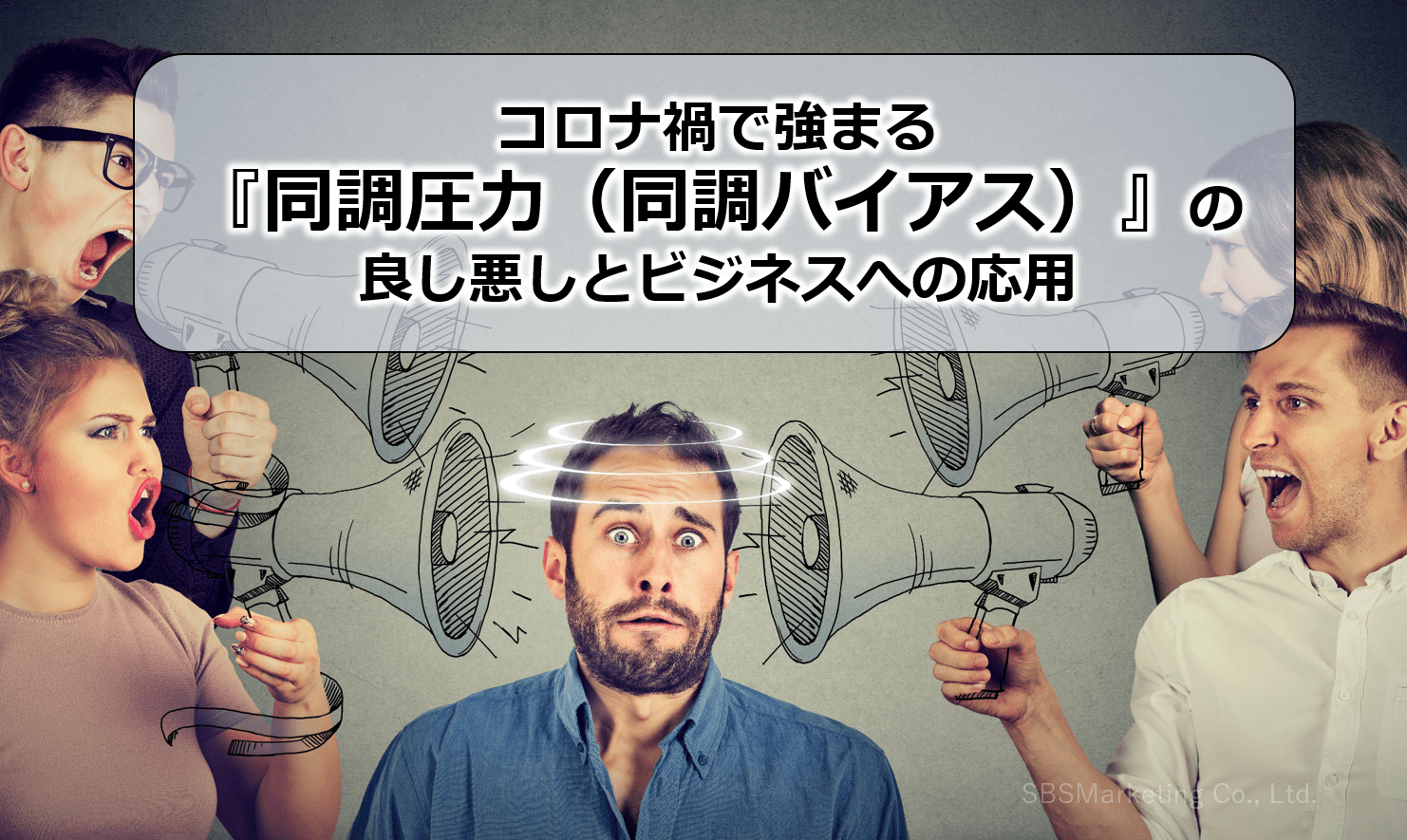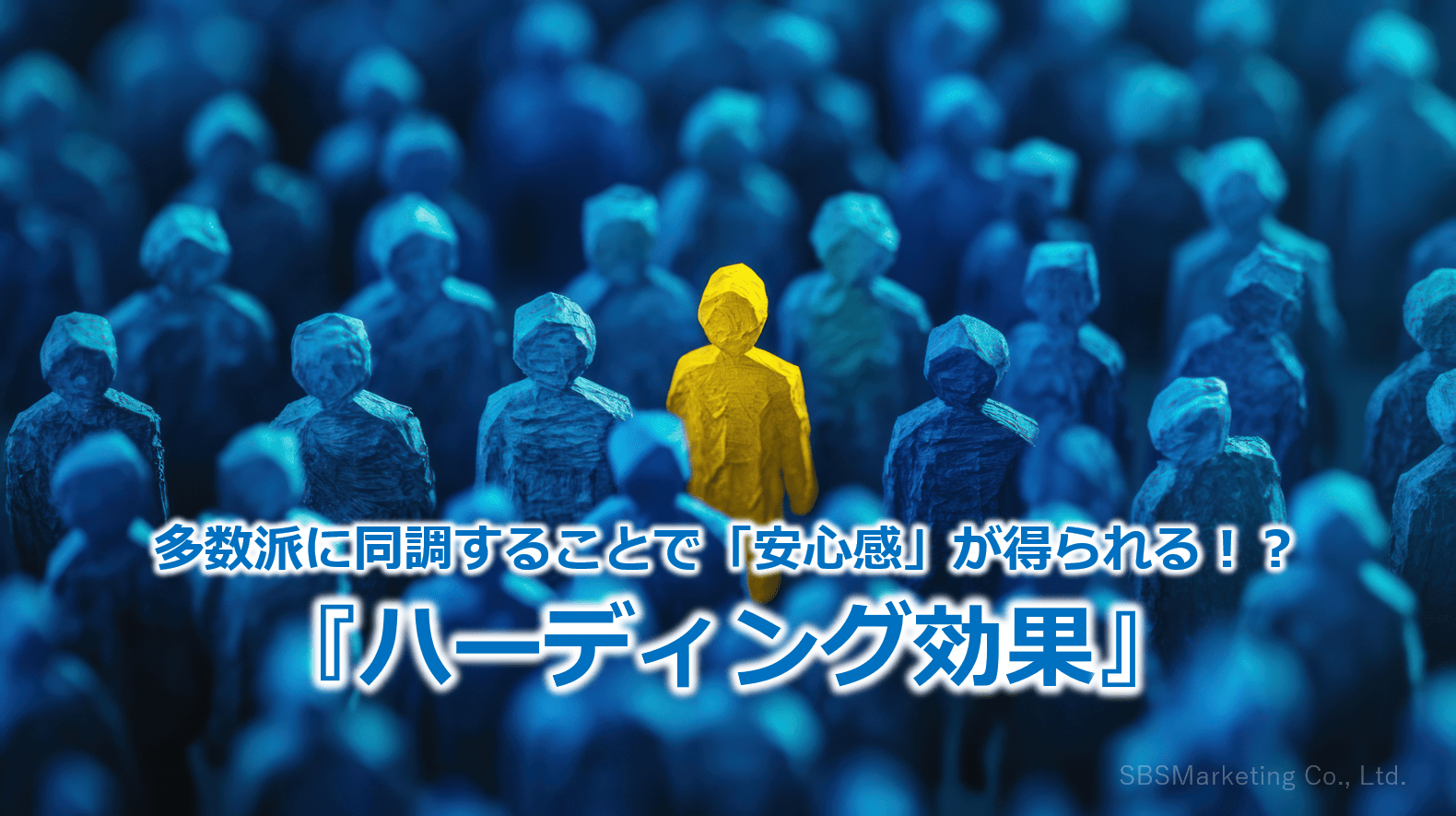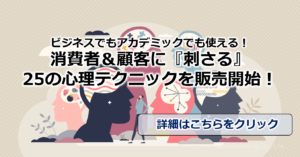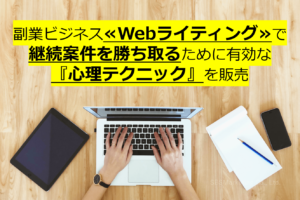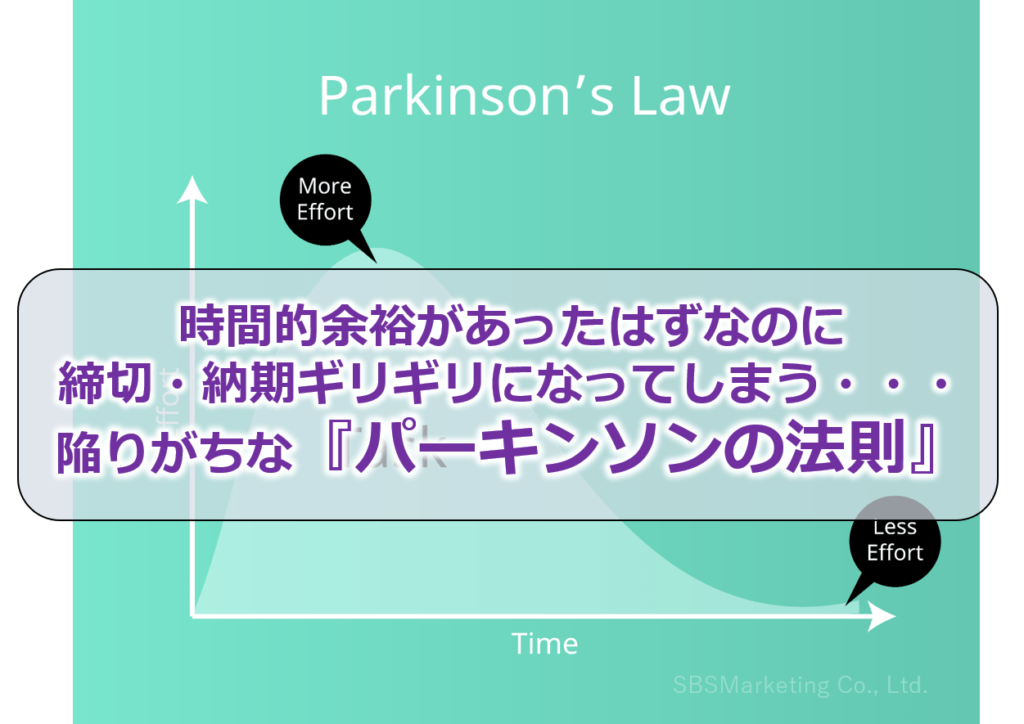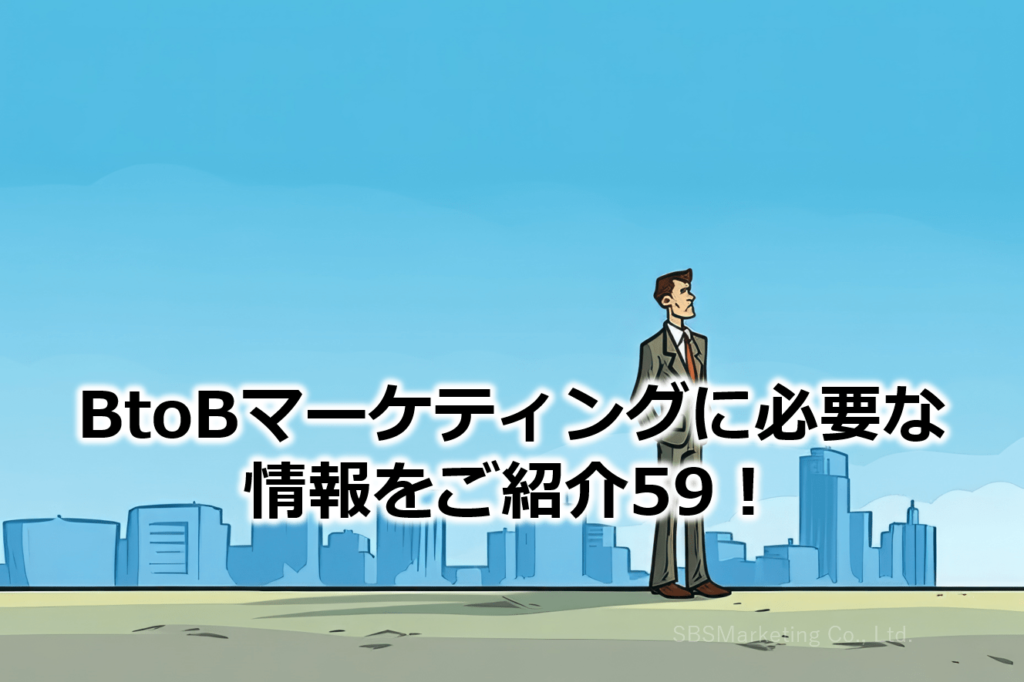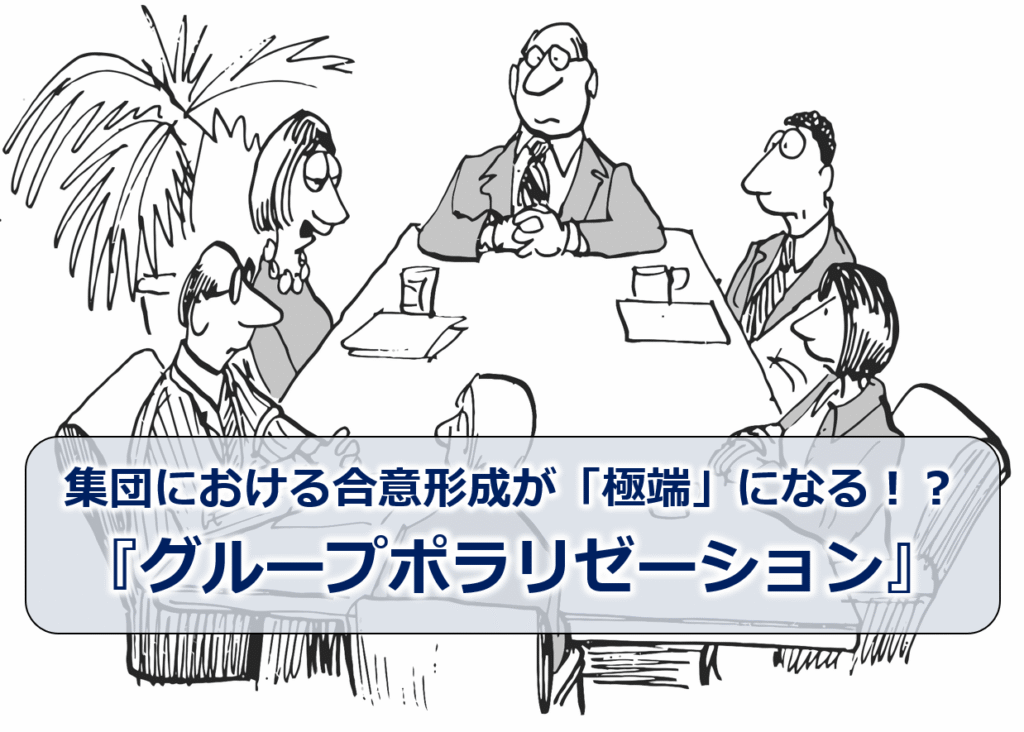
集団内で議論する際に、意見集約や意見収束の過程の中で「極端な方向」に偏る『グループポラリゼーション』。
3つの発生例や発生する・助長するメカニズム、陥らせないための2つの方法などについて解説しています。
『グループポラリゼーション』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『グループポラリゼーション』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『グループポラリゼーション』とは?

『グループポラリゼーション(Group Polarization)』とは、集団内で議論する際に、意見集約や意見収束の過程の中で「極端な方向」に偏る傾向のことです。
『グループポラライゼーション』とも呼ばれ、集団内での合意形成が、個人で意思決定するよりも極端になる現象とも言えます。
日本語では『集団極性化』や『集団分極化』と訳され、社会心理学の用語として知られています。
「偏光現象」が名称の由来に
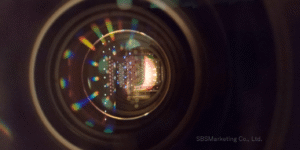
この『グループポラリゼーション』は、光の振動方向が特定の方向に偏る「偏向」現象を、集団の意見や意思決定に適用したものとされています。
良くも悪くも「両極端」になる傾向が
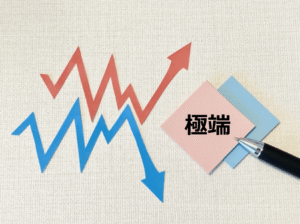
『グループポラリゼーション』は、必ずしも危険な方向へ先鋭化するとは限らず、逆により慎重な方向へ極性化する傾向もあります。
「両極端」な方向へ偏ることを、それぞれ「リスキーシフト」「コーシャスシフト」と呼ばれています。
- リスキーシフト:より危険(リスキー)な方向へ意見が偏る。
- コーシャスシフト:より安全な方向へ偏る。
『グループポラリゼーション』の発生例

良くも悪くも「極端」な方向へ偏る『グループポラリゼーション』の発生ケースは、以下の通りです。
- リスクの高い選択肢を選ぶ
- 面白味が欠ける選択肢を選ぶ
- インターネット空間・SNS上で「右寄り」に極端化する
リスクの高い選択肢を選ぶ

グループ内で議論を進める中で、危険性の高いリスキーな選択肢と、安全性の高いローリスクな選択肢がある場合、場合によっては、『グループポラリゼーション』が生じると、よりリスクの高い選択肢へと意見が偏りやすくなる「リスキーシフト」によって先鋭化するようになります。
面白味が欠ける選択肢を選ぶ

一方で、議論を進める中で、リスクが含まれる「とがった提案」が挙がったとしても、『グループポラリゼーション』(コーシャスシフト)が生じることによって、面白味に欠ける無難な内容に落ち着いてしまうのも、発生例の1つと言えます。
インターネット空間・SNS上で「右寄り」に極端化する
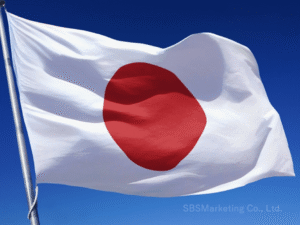
ネット空間・SNS上では、意見や思想が「過激化しやすい」傾向があります。
インターネットの大衆化により、平等性や匿名性が高まることで、発言の自由度も高まるようになります。
すると、意思決定が「極性化」しやすくなり、特に「右翼的方向」へと極端化しやすくなります。

なぜ「右傾化」するかという理由としては、既存メディアの体制化による「タブー化」が挙げられます。
日本では、戦後民主主義の下で「ナショナリズム」や「愛国主義」がタブー化され、自由に発言できない時代が続きました。
さらに、タブー化された風潮に沿うように、既存の4大マスメディアが左翼的・人権派的に体制化されたことから、アジアの周辺国に対する批判がタブー視され、「有事」「危機管理」という言葉も使うことが躊躇われるようになりました。
こういった戦後のマスメディアによって作り上げられた「閉鎖的な言論空間」の中で、抑圧された声がインターネットが普及した1995年以降、噴出するようになったという見解があります。
※『既存の4大マスメディア』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
『4大マスメディア』と呼ばれる、新聞、雑誌、テレビ、ラジオの媒体それぞれの最近の傾向と、現場のマーケターの目線で把握しておきたいポイント、「広告出稿して効果が出るのか」という視点を踏まえて解説しています。

さらに、SNSが普及したことによって、より過激さが増し人種差別的・排他的な言動を行う「ネット右翼」現象が生じるようになりますが、この現象には『サイバーカスケード』が大きな影響を及ぼしているという見方があります。
そして、右寄りに傾く「ネット右翼(ネトウヨ)」だけでなく、逆に左寄りに傾く「左翼思想(パヨク)」も『サイバーカスケード』の影響によって増加するようになっています。
その結果、両極端な主張を展開する人々が増加することで、分極化が進む傾向が続いています。
※『サイバーカスケード』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
同じ思想や主義を持っている他者とインターネット上で結びつきを強め先鋭化することで、異なる考えや主張を排除が進み、閉鎖的かつ過激なコミュニティを形成する『サイバーカスケード』。なぜ発生するのか、発生することによって生じる問題点、発生例や発生を回避する方法などについて解説しています。
『グループポラリゼーション』によって生じるデメリット

この『グループポラリゼーション』は、リスキー or ローリスクどちらの選択肢を選ぶとしても、組織や集団における「意思決定の質」を低下させる可能性があるため、注意が必要な心理的傾向です。
『グループポラリゼーション』が発生する・助長させるメカニズム
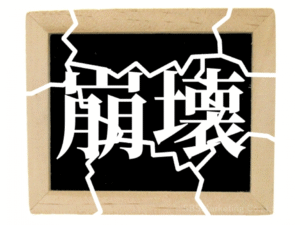
生じてしまうとデメリットによる「集団の崩壊」をもたらすことにつながる『グループポラリゼーション』。
その心理的傾向を発生させる・助長するメカニズムとしては、以下の点が挙げられます。
- 情報伝達の偏り
- 自己呈示
- 集団思考
- 高い『集団凝集性』
- 『同調圧力(同調バイアス)』
- 『ハーディング効果』
情報伝達の偏り

集団内で共有される情報が、リスクの高い選択肢に関する情報に偏っている場合、集団全体の意見もリスクの高い選択肢へ偏りやすくなってしまいます。
自己呈示

集団の中に、自身の「見せたい部分」だけを見せて意図的に印象操作する『自己呈示』をする人がいると、突拍子もない大胆な意見を表明しやすいため、その意見に偏りやすくなってしまいます。
集団思考

集団の中で、批判的な思考を放棄し「合意形成」を優先してしまう『集団思考』が生じてしまうことも、『グループポラリゼーション』を発生させる要因の一つと言えます。
高い『集団凝集性』

「集団の一員として留まりたい」と思わせる『集団凝集性』によって、「極端な方向」に偏るというケースも考えられます。
またこの『集団凝集性』によって、不合理な結論に合意形成してしまう『集団浅慮(グループシンク)』という現象が生じやすくなってしまいます。
※『集団凝集性』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
「ステーキを売るな、シズルを売れ!」で知られる『ホイラーの法則』。提唱した人物と、セールスのノウハウとも言える5つそれぞれの公式について解説しています。
※『集団浅慮(グループシンク)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
集団で合意形成を図る際に、不合理な意思決定や望ましくない行動が容認されてしまう『グループシンク(集団浅慮)』。陥ることで生じる兆候や発生例、陥ってしまう原因と対策、マーケティング施策への応用例などについて解説しています。
『同調圧力(同調バイアス)』
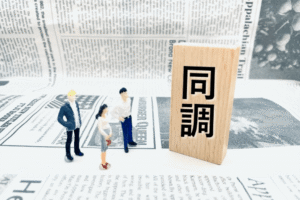
『グループポラリゼーション』を助長させる要因として、判断基準や価値観を少数派に暗黙的に強制することになる『同調圧力』が挙げられます。
このバイアスが作用することで、多数派になった先鋭化した意見に賛同することで「安心感」を得ようとする心理が働き、「極端に偏った方向」に結論付く可能性が高まることになります。
※『同調圧力(同調バイアス)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
多数派が少数派に価値観を暗黙的に強制する『同調圧力』。なぜ発生するのか、メリットやデメリット、日本でよく見受けられる理由やビジネスへの応用について解説しています。
『ハーディング効果』
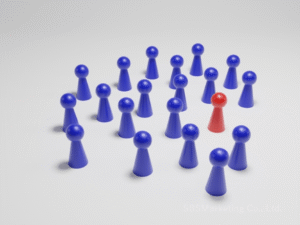
『グループポラリゼーション』を助長させる要因としては『ハーディング効果』も当てはまります。
多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』。
「集団の一員」として同調し、多数派に従うことで孤立感を避けようとする心理作用によって、『グループポラリゼーション』を加速させることにつながります。
※『ハーディング効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
自分自身も多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』。効果の概要と発生例、発生する原因(要因)やマーケティングへの活用例、ビジネスシーンに活用する際の注意点などについて解説しています。
↓
この続きでは、『グループポラリゼーション』に陥らないようにするための方法について解説しています。
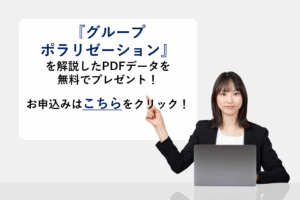 『グループポラリゼーション』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
『グループポラリゼーション』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『グループポラリゼーション』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
- 4大マスメディア
- BtoBマーケティング
- Group Polarization
- クリティカルシンキング
- グループシンク
- グループポラライゼーション
- グループポラリゼーション
- コーシャスシフト
- サイバーカスケード
- タブー化
- ナショナリズム
- ネット右翼
- ネトウヨ
- ハーディング効果
- パヨク
- リスキーシフト
- リスクの高い選択肢
- ローリスクな選択肢
- 人権派的
- 保守的
- 偏光現象
- 助長させるメカニズム
- 右傾化
- 右寄り
- 右翼的
- 同調バイアス
- 同調圧力
- 左翼的
- 心理的安全性
- 情報伝達の偏り
- 意思決定の質を低下させる
- 愛国主義
- 批判的思考
- 株式会社SBSマーケティング
- 極端な合意形成
- 発生するメカニズム
- 自己呈示
- 過激化
- 閉鎖的な言論空間
- 集団の崩壊
- 集団凝集性
- 集団分極化
- 集団思考
- 集団極性化
- 集団浅慮
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。