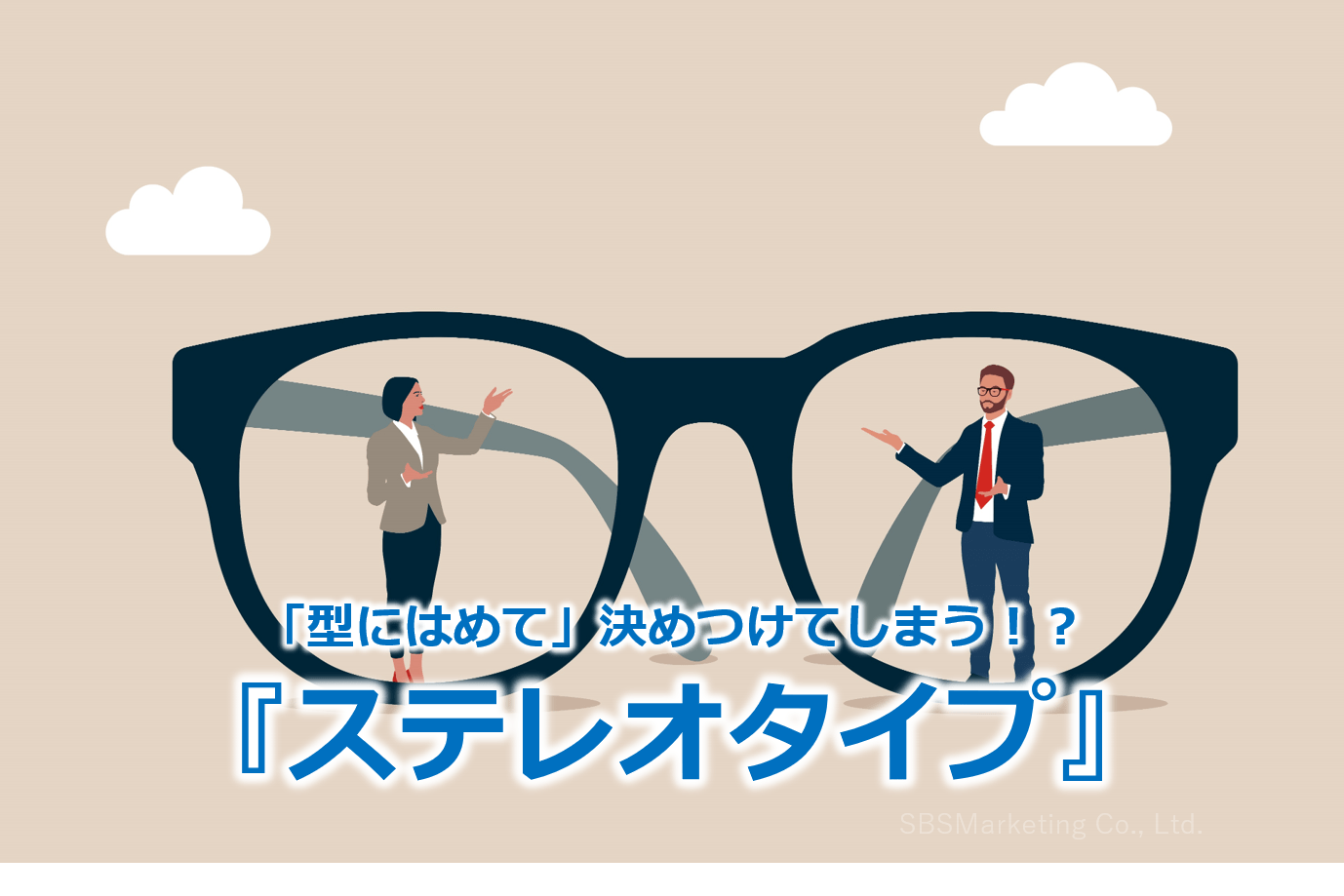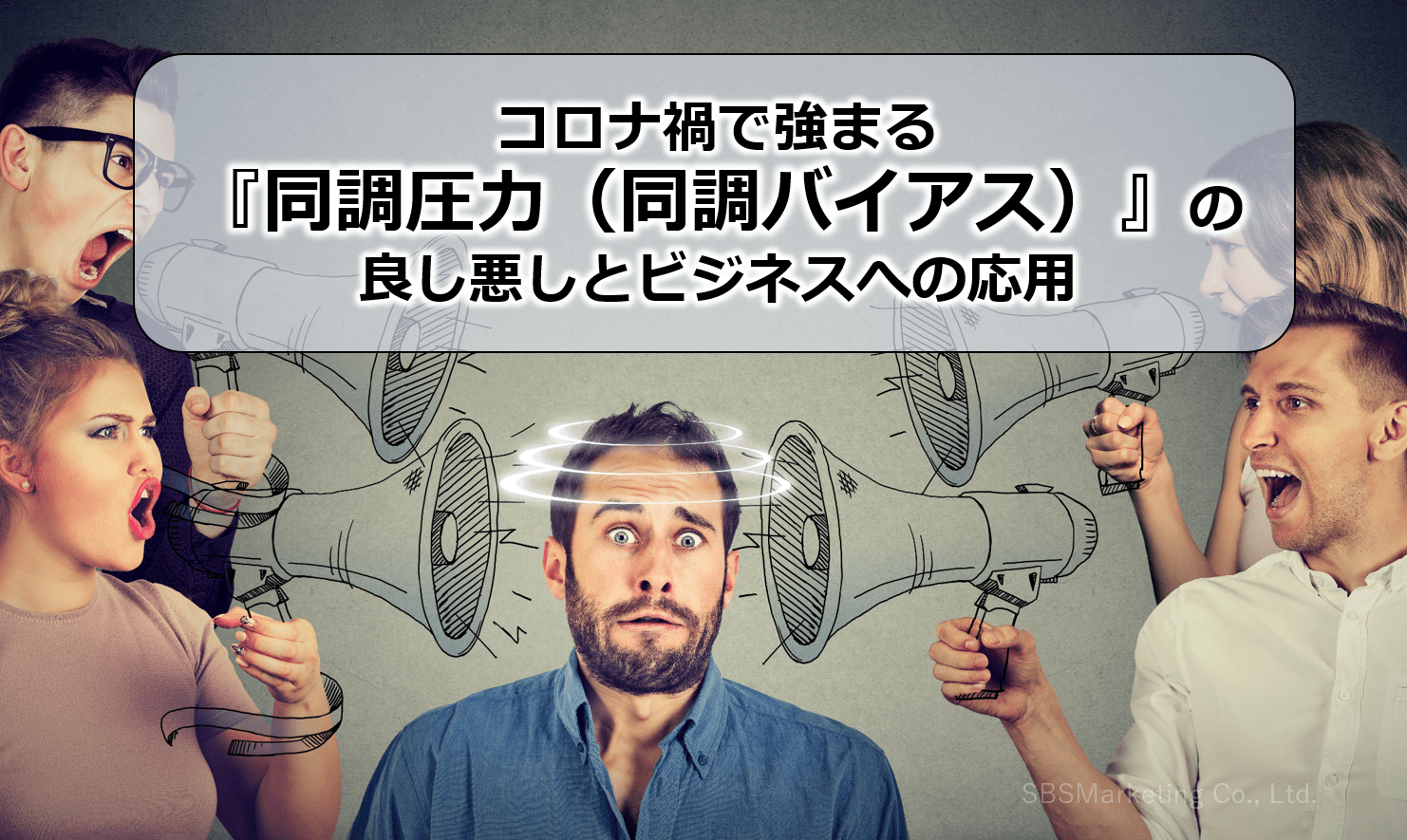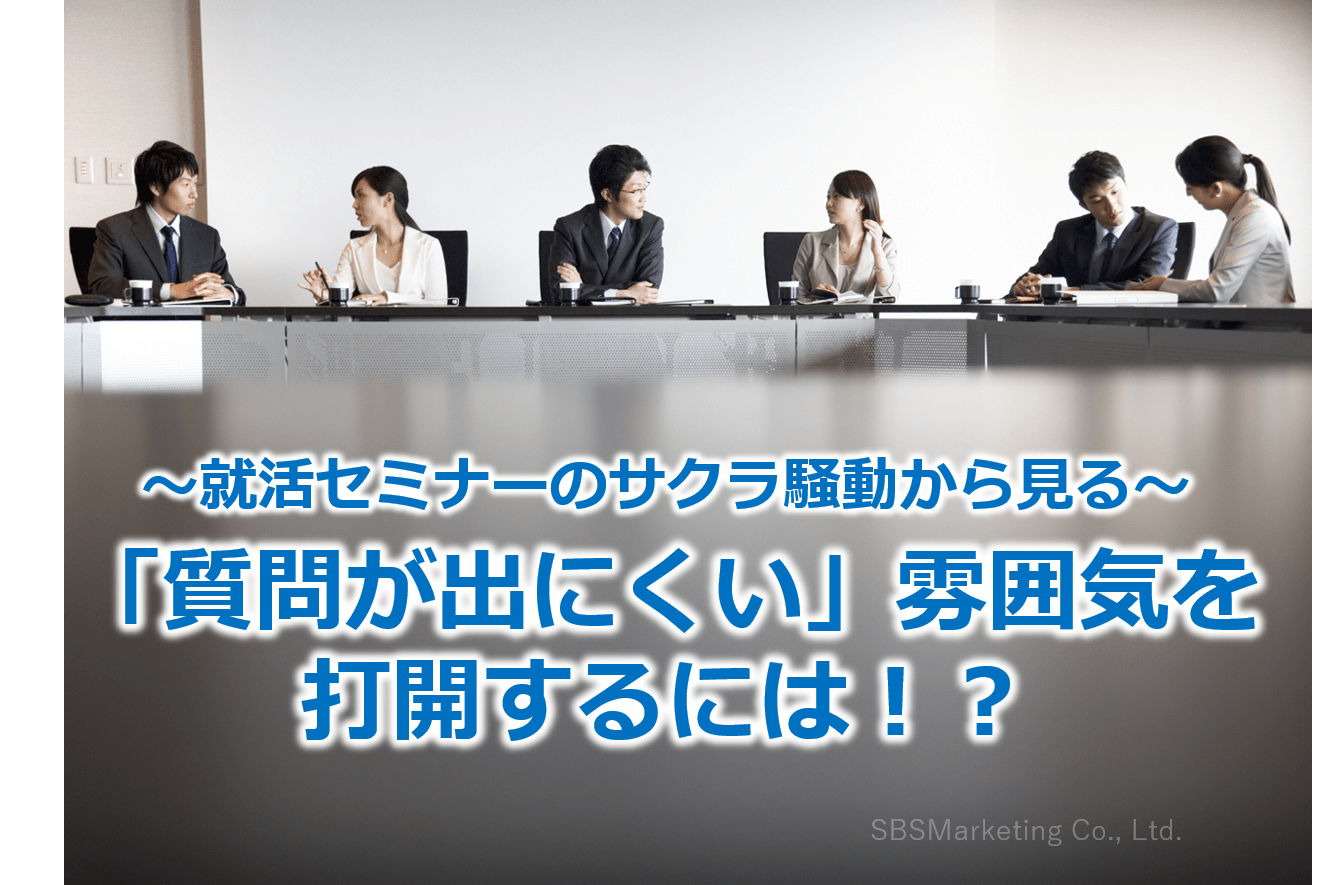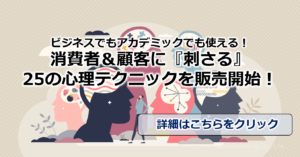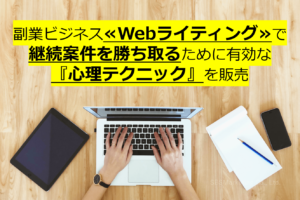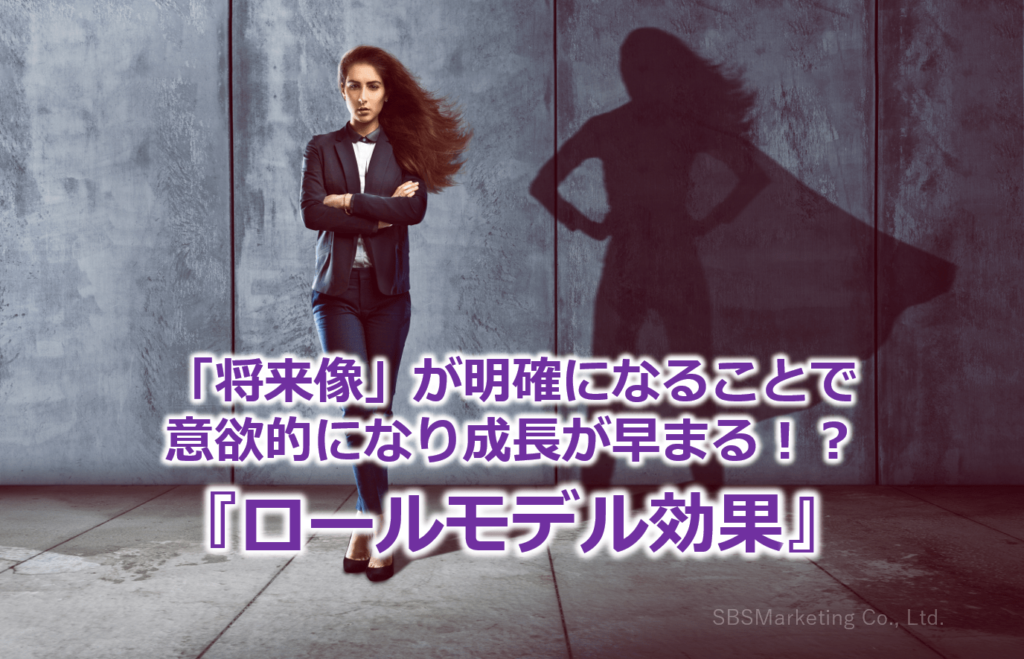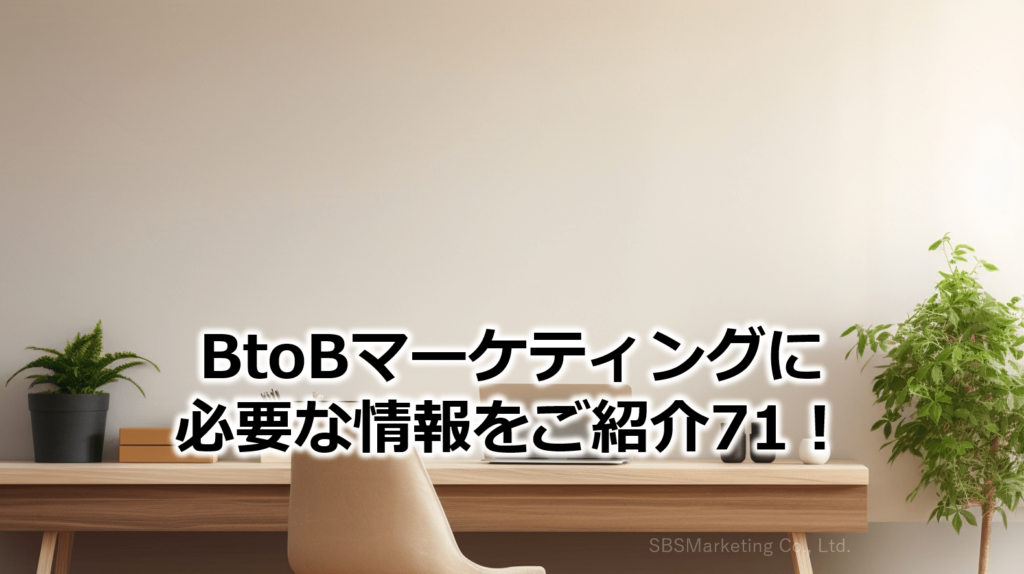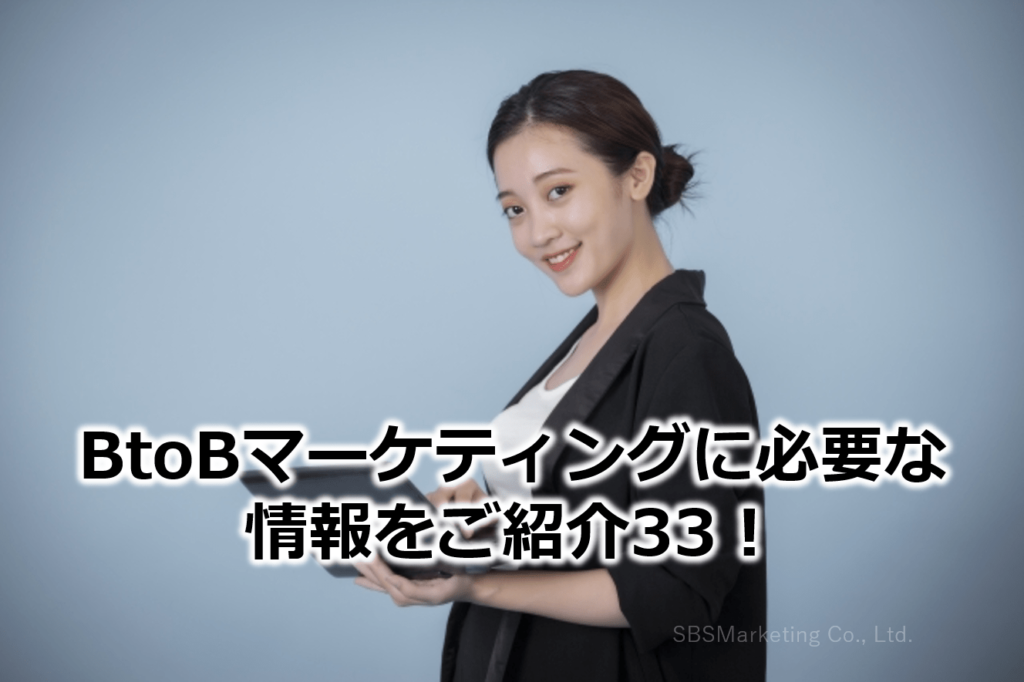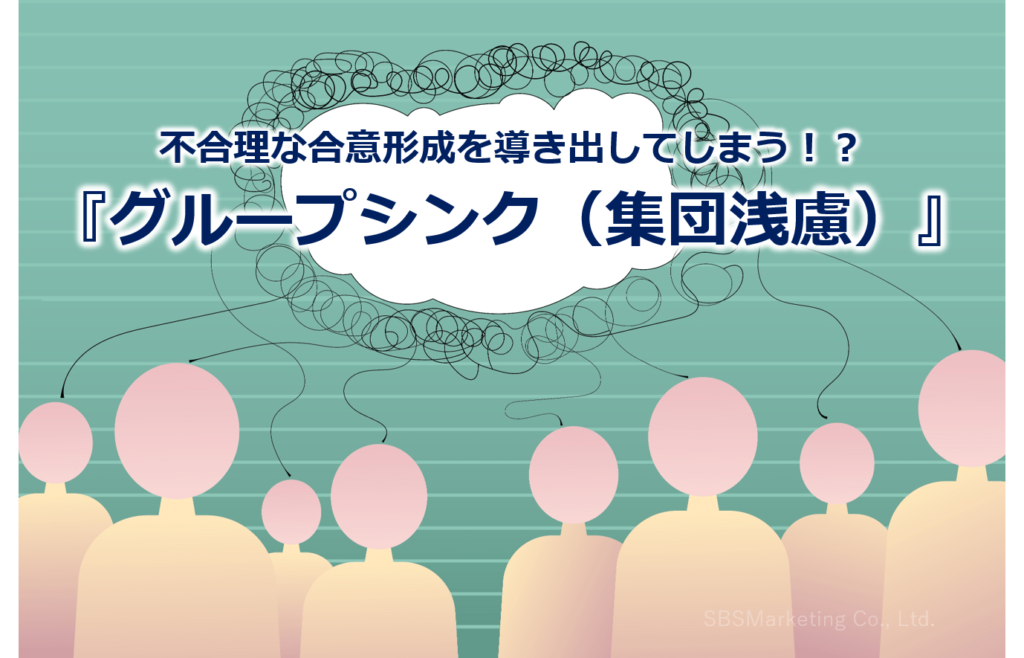
集団で合意形成を図る際に、不合理な意思決定や望ましくない行動が容認されてしまう『グループシンク(集団浅慮)』。
陥ることで生じる兆候や発生例、陥ってしまう原因と対策、マーケティング施策への応用例などについて解説しています。
『グループシンク(集団浅慮)』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『グループシンク』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
『グループシンク(集団浅慮)』とは?

特定の議題について議論し結論を出す会議や、業務上の問題解決をしたり進捗を共有するミーティングのどちらも、企業組織などの集団における「合意形成」を目的として行われます。
それらを実施する際には、「集団」だからこそ生じてしまう『グループシンク』という「落とし穴」に注意が必要です。
『グループシンク(Group think)』とは、集団で合意形成を図る際に、不合理な意思決定や望ましくない行動が容認されてしまうことを意味し、『集団浅慮(しゅうだんせんりょ)』や『集団思考』とも呼ばれています。
提唱したのは?

この『グループシンク(集団浅慮)』という考え方は、アメリカにあるイェール大学の社会心理学者、アーヴィング・ジャニス 氏によって提唱されました。
1941年の真珠湾攻撃のリスクを過小評価したことや、1961年のキューバ侵攻作戦の失敗などについて、『グループシンク(集団浅慮)』の観点から考察しました。
グループシンクとグループシフト

『グループシンク』と似た言葉に『グループシフト』がありますが、違いとしては以下の通りです。
- グループシンク:別名、集団浅慮。集団で合意形成を図る際に、不合理な意思決定や望ましくない行動が容認されてしまうこと。
- グループシフト:別名、集団傾向。同じ意見や思考を持つ人同士が議論することにより、極端な方向性や指針が決まってしまうこと。
『グループシンク(集団浅慮)』に陥ることで生じる兆候

『グループシンク(集団浅慮)』に陥ってしまうことで生じる代表的な兆候は、以下の3つが挙げられます。
- 「自信過剰」な集団になる
- 『ステレオタイプ』な見方が強まる
- 異論を受け入れず封殺する
「自信過剰」な集団になる

『グループシンク(集団浅慮)』に陥ると、集団としての能力に過剰な自信を持つようになります。
過剰な自信を持ってしまうことで、業績不振などの兆候があったとしても「問題ないだろう」と楽観的に捉えるようになり、リスク要因を過小評価することになります。
また都合の悪い意見や情報を遮断するようにもなり、集団・組織としての自浄能力を失うことにもなってしまいます。
『ステレオタイプ』な見方が強まる

集団として自信過剰になってしまうことで「精神的閉鎖性」が強くなり、偏った考え方に傾倒するようになります。
すると、自身が所属する集団にとって不利益・不利な情報を割り引いて解釈するようになってしまいます。
また、『ステレオタイプ』(※)のように、先入観や固定観念という「色メガネ」を介して物事を捉えるようになり、「型にはめて」決めつけを行う傾向が強まるようになります。
※『ステレオタイプ』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
特定の属性に対する先入観や思い込みによって「型にはめて」決めつけてしまう『ステレオタイプ』。代表的な7つの具体例や生じることによるデメリットとメリット、予防する・克服するための方法などについて解説しています。
異論を受け入れず封殺する

意見が斉一化(せいいつか)することも、『グループシンク(集団浅慮)』に陥ってしまった際の兆候の1つです。
意見交換や議論をする際、異議・異論を唱える人物に対して、圧力や中傷が加えられやすくなります。
そのため、問題を指摘することができなり、また指摘したとしても、握りつぶされてしまいます。
『グループシンク(集団浅慮)』の発生例

『グループシンク(集団浅慮)』には、事例となるような有名な事象や実際の企業組織で起こりがちなケースなど、さまざまあります。
ピッグス湾事件

有名な『グループシンク(集団浅慮)』の発生例としては、アメリカ史に残る軍事作戦の失敗として知られている「ピッグス湾事件」が挙げられます。
1961年に発生したピッグス湾事件とは、アメリカのジョン・F・ケネディ政権が、カストロ政権を倒すために起こしたピッグス湾への侵攻作戦のことです。

2,000人程度のキューバ反政府軍に依存している、空軍の援護や物資補給が不十分であるなどの不安要素があり、作戦を練っていた段階で反対意見が噴出していましたが、権威のある専門家やCIA(米中央情報局)の見解にケネディらがそのまま従ってしまい、作戦を決行。結果、失敗することになりました。
つまり、作戦を立てる段階であがっていた反対意見(不安要素)をあえて見過ごし、根拠の薄い肯定的な意見を採用するという『グループシンク(集団浅慮)』が生じてしまい、失敗という結果につながってしまったということです。
チャレンジャー号爆発事故
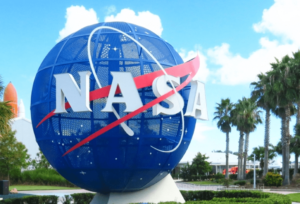
1986年に発生した、NASAのスペースシャトルであるチャレンジャー号の打ち上げ失敗事故。
この事故が発生してしまった原因としては、スペースシャトル打ち上げのプロジェクトメンバーに、過度のプレッシャーやストレスがかかっていたことが挙げられています。
当時、チャレンジャー号の打ち上げプロジェクトではトラブルが続いており、打ち上げが延期になってしまうと予算の縮小や計画自体の見直しが検討されてしまう恐れがありました。
そのプレッシャーやストレスから、スペースシャトルの構成部品を製造した会社から不具合の報告があったにも関わらず、打ち上げを強行してしまいました。

NASAでは、問題が解決するまで関係者全員で議論を重ねるルールがありましたが、リスクに関する意見交換を徹底せずに「打ち上げ成功」という成果を優先した結果、打ち上げ直後に大爆発が起こり、チャレンジャー号に搭乗していた7名の乗組員が亡くなってしまいました。
この事例のように、通常時は優秀な集団であったとしても、プレッシャーやストレスがかかる環境下においては、人命にかかわるような議論であっても不適切な結論を導き出してしまうという『グループシンク(集団浅慮)』が発生する場合があります。
政治における決定プロセス

身近な例としては、政治における決定プロセスが挙げられます。
有力な派閥に属する一部の議員が特定の政策に固執し、ほかの多くの議員がそれとは異なる意見を持っている場合、有力な派閥に属する議員らと異なる意見を抑え込もうとする『グループシンク(集団浅慮)』が生じ、最終的な政策決定に誤りや歪みが生じてしまうことがあります。
社内で不合理な意思決定をしてしまう

ビジネスにおいて身近なケースとして、会社での議論の場において、参加者のパワーバランスを考慮したりその場の空気を読んで、不合理な意思決定をしてしまう、という事態が挙げられます。
すると、「みんなで決めたことだから間違っていない」という幻想が生まれ、現実性の有無を踏まえずに無茶な施策を推し進めたりするようになってしまいます。
不祥事が起きてしまう

『グループシンク(集団浅慮)』による「不合理な意思決定」の具体例として「不祥事」が挙げられます。
集団としての「和」を重視しようとする「企業文化」が社内に浸透していると、企業組織として欠かせない倫理観や道徳観を無視しやすくなり、企業規模やホワイト・ブラックという企業体質問わず、コンプライアンス違反やハラスメント問題などの「不祥事」が起こりやすくなってしまいます。
『グループシンク(集団浅慮)』に陥ってしまう原因

『グループシンク(集団浅慮)』に陥ってしまう原因として、以下のような事象が集団や組織に生じています。
- 「集団凝集性」が作用してしまう
- 「閉鎖的」な組織
- 過度なストレス・プレッシャーがかかる
- 特定の人物に権力が集中している
- 責任の所在が不明確
- 「利害関係」が生じている
「集団凝集性」が作用してしまう
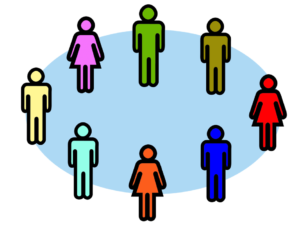
集団に留まらせようとする帰属意識が高い心理的性質を意味する「集団凝集性」。
この集団凝集性が高まることによって、企業組織への定着率が高まったり組織力が強まるというメリットがあります。
一方で、議論の場において組織の閉鎖性が高まってしまったり「同調圧力」(※)や「固定概念」が強まってしまうというリスクもあります。

特に「同調圧力」が強まってしまうと、少数派に多数派と同じ意思決定や行動をとるよう暗黙的に強制するようになるため、多数派と異なる意見を持っていたとしても非難されることを恐れ、発言自体を控えるようになってしまいます。
つまり、「集団凝集性」が高いほど、組織が閉鎖的になりやすく「同調圧力」が強まってしまうため、『グループシンク(集団浅慮)』が生じやすくなるということです。
※『同調圧力』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
多数派が少数派に価値観を暗黙的に強制する『同調圧力』。なぜ発生するのか、メリットやデメリット、日本でよく見受けられる理由やビジネスへの応用について解説しています。
「閉鎖的」な組織

組織自体が閉鎖的であったり、人員の流動性がない企業では、外部の情報が入りづらく同質的な集団が形成されやすくなります。
そのため、物事を客観的に判断したり多角的な議論が行えなくなり、『グループシンク(集団浅慮)』を引き起こしてしまいます。
過度なストレス・プレッシャーがかかる

ノルマ達成やトラブル対応など、時間的な制限や圧力・心理的負荷がかかってしまうと、「行動する」「結論を出す」こと自体が目的になってしまい、十分な検討がなされずに不合理な判断や行動を導き出してしまうリスクが高まってしまいます。
特定の人物に権力が集中している
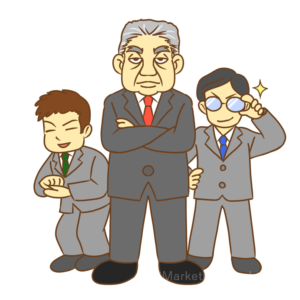
集団の中に、突出して権威性が高い重鎮がいたり、トップダウンの社風が強いと、ほかのメンバーは「従うだけ」の状態になってしまい、多様な意見が出ずらくなってしまいます。
責任の所在が不明確

各人の役割分担や責任の所在が不明確になっていると、それぞれの責任感は薄くなり「他責思考」に傾倒しやすく、意見を出さなくなったり、決定事項に責任を持たなくなってしまい、『グループシンク(集団浅慮)』に陥ってしまう恐れがあります。
「利害関係」が生じている

議論などで導き出す結論次第で何らかの「利害」が発生する場合、議論の内容よりも参加者自身の利益を優先する思考が強まってしまうため、集団・組織として不合理な判断を下してしまう『グループシンク(集団浅慮)』に陥りやすくなってしまいます。
『グループシンク(集団浅慮)』への対策

『グループシンク(集団浅慮)』に陥らないようにするためには、以下のアプローチが効果的です。
- 議論は「少人数」で行う
- 「匿名」で意見を募る
- リーダーの意識改革
- 「多様な意見」への理解を深める
- 「心理的安全性」の高い環境を築く
議論は「少人数」で行う

大人数で議論すると、権威性などパワーバランスに偏りが大きな影響を及ぼしやすくなり『グループシンク(集団浅慮)』に陥りやすくなるので、少人数でディスカッションすることで、それぞれが「当事者意識」を持ちやすくなり、論じるべき議題や課題に向き合って合理的な意見や決断をしやすくなります。
「匿名」で意見を募る

『グループシンク(集団浅慮)』が生じやすくなる「同調圧力」を回避するために、意見を「匿名」で収集することで、バイアスのかからない正直な意見を引き出すことができます。
リーダーの意識改革

議論を行う際、取りまとめるリーダーの意識や振る舞いが『グループシンク(集団浅慮)』の発生に大きな影響を及ぼすことになります。
そのため、リーダーに対して『グループシンク(集団浅慮)』についての教育を行い、強すぎるリーダーシップを抑え中立性を担保し、合理的な意思決定をするための議論を活発化させるように意識改革をすることもポイントになります。
「多様な意見」への理解を深める

『グループシンク(集団浅慮)』を防ぐためには、多角的な議論を展開できるように「多様な意見」の許容を促すことも大切になります。
そのためには、企業組織や集団が「さまざまな背景や価値観を持ったメンバーによって成り立っている」ことを、それぞれが理解するよう、集団文化を醸成することが求められます。
「心理的安全性」の高い環境を築く

「多様な意見への理解を深める」ことと関連して、多数派と異なる意見を発言したとしても、不利益を被ることのないよう、「心理的安全性」の高い議論環境を築くことも大切なポイントです。
※『心理的安全性』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
就活セミナーのサクラ騒動の背景にある「質問が出にくい」雰囲気。この雰囲気はビジネスシーンでも発生します。特にミーティングの場面を例に、質問が出にくい理由や雰囲気を打破する方法について解説しています。
↓
この続きでは、『グループシンク(集団浅慮)』のマーケティング施策への応用例について解説しています。
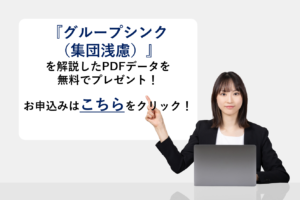 『グループシンク(集団浅慮)』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
『グループシンク(集団浅慮)』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『グループシンク』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
- BtoBマーケティング
- Group think
- SNS
- UGC
- インフルエンサー
- グループシフト
- グループシンク
- グループシンクによって生じる兆候
- グループシンクに陥ってしまう原因
- グループシンクのマーケティング施策への応用例
- コンプライアンス違反
- ステレオタイプ
- ソーシャルプルーフ
- チャレンジャー号爆発事故
- ハラスメント
- バンドワゴン効果
- ピッグス湾事件
- リーダーの意識改革
- 不合理な合意形成
- 不祥事
- 利害関係
- 匿名で意見を募る
- 合理性のない意思決定
- 同調圧力
- 多様な意見
- 少人数で議論
- 心理的安全性
- 政治における決定プロセス
- 株式会社SBSマーケティング
- 権威性が高い重鎮
- 異論を封殺
- 自信過剰
- 責任の所在が不明確
- 過度なプレッシャー
- 閉鎖的な組織
- 集団凝集性
- 集団浅慮
- 集団浅慮の発生例
- 集団浅慮への対策
- 高い帰属意識
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。