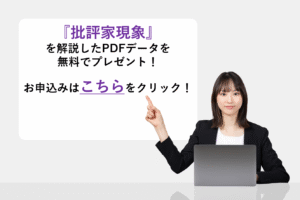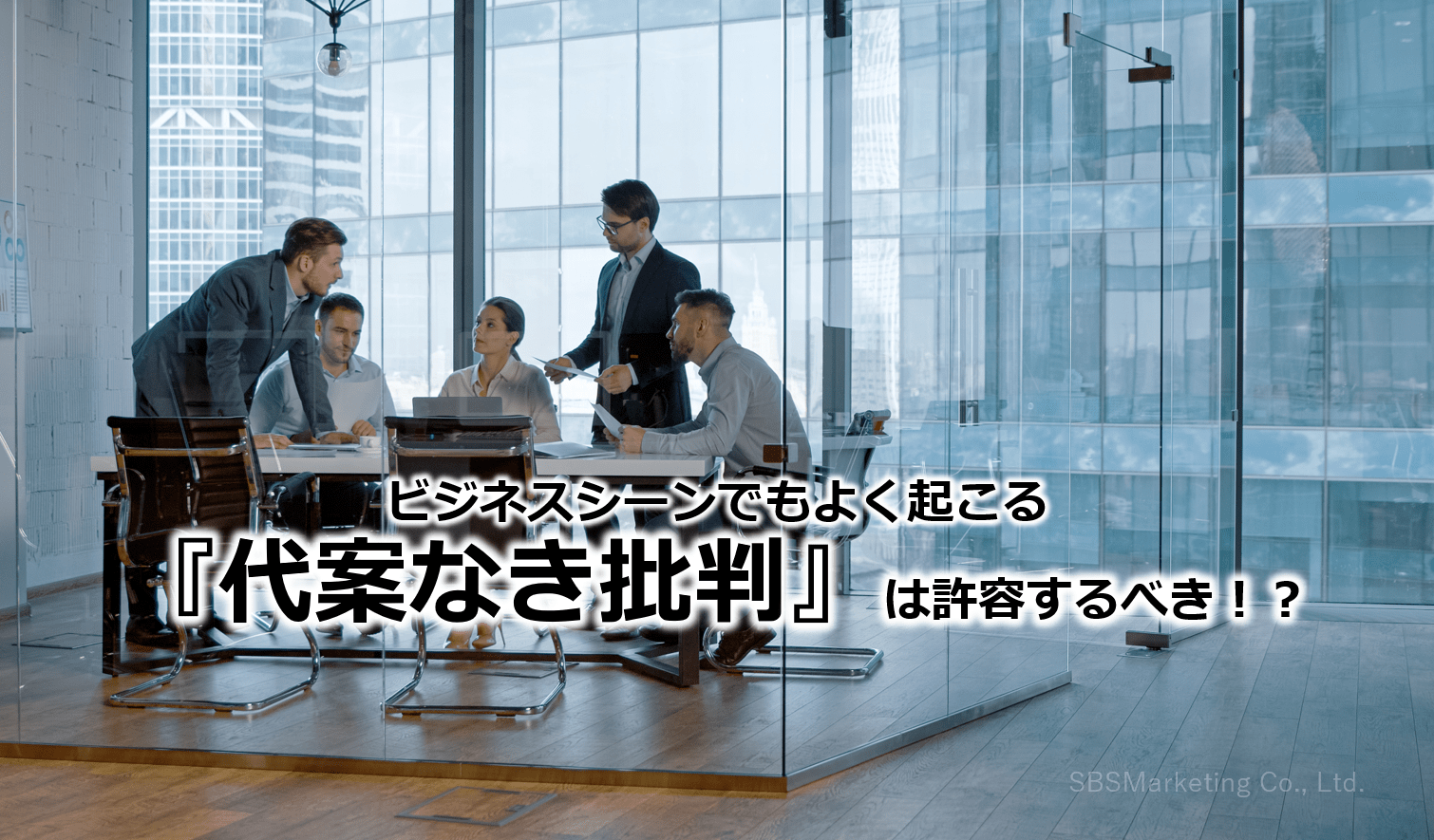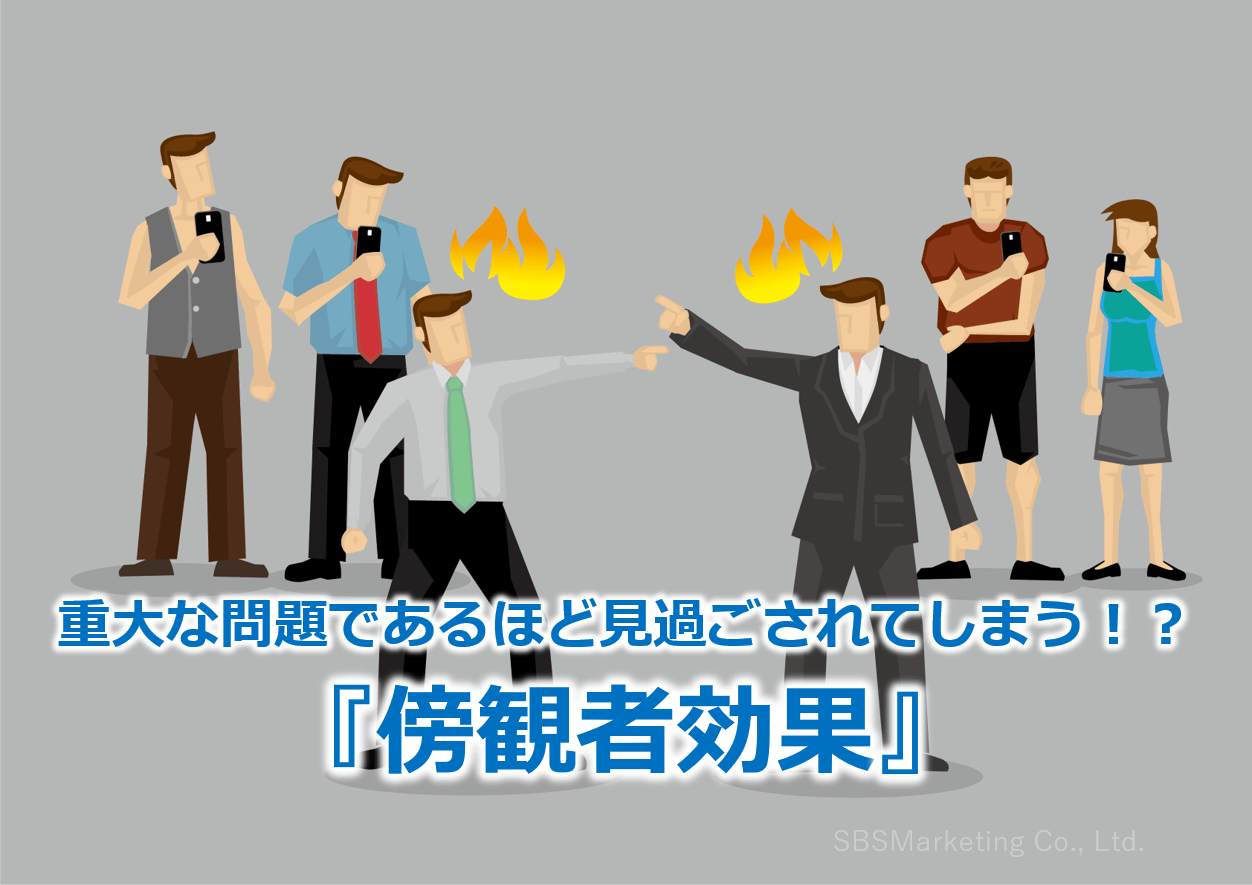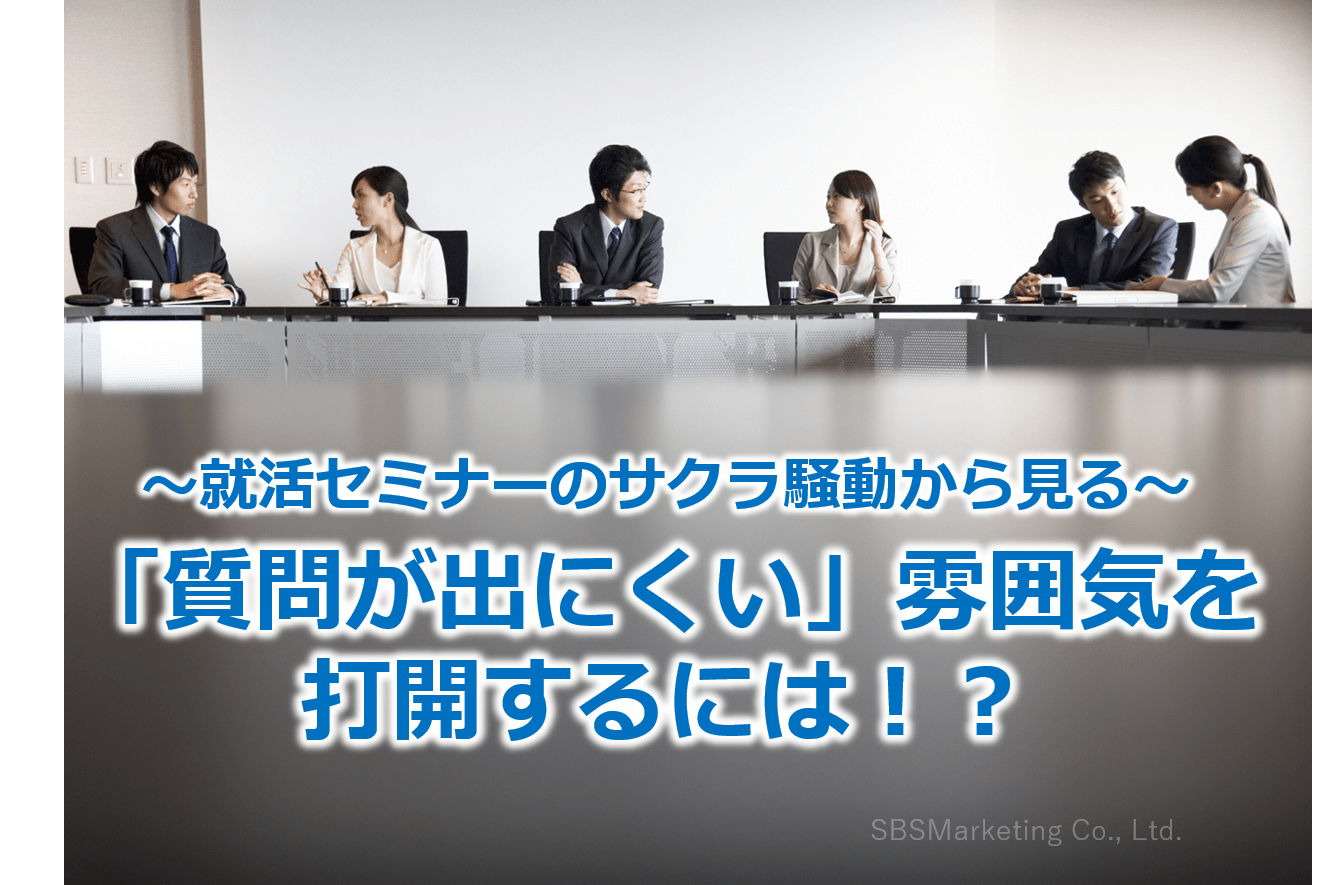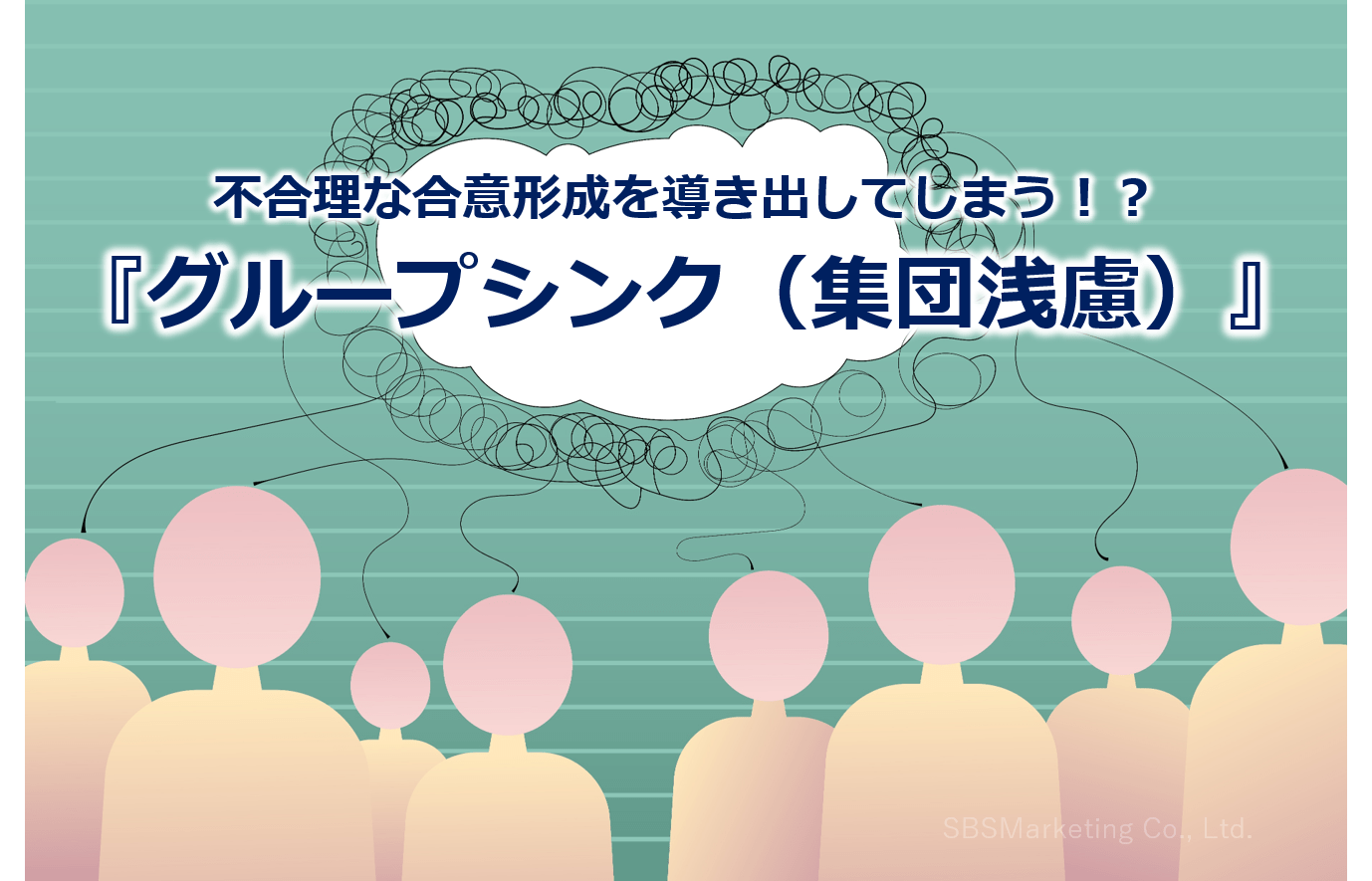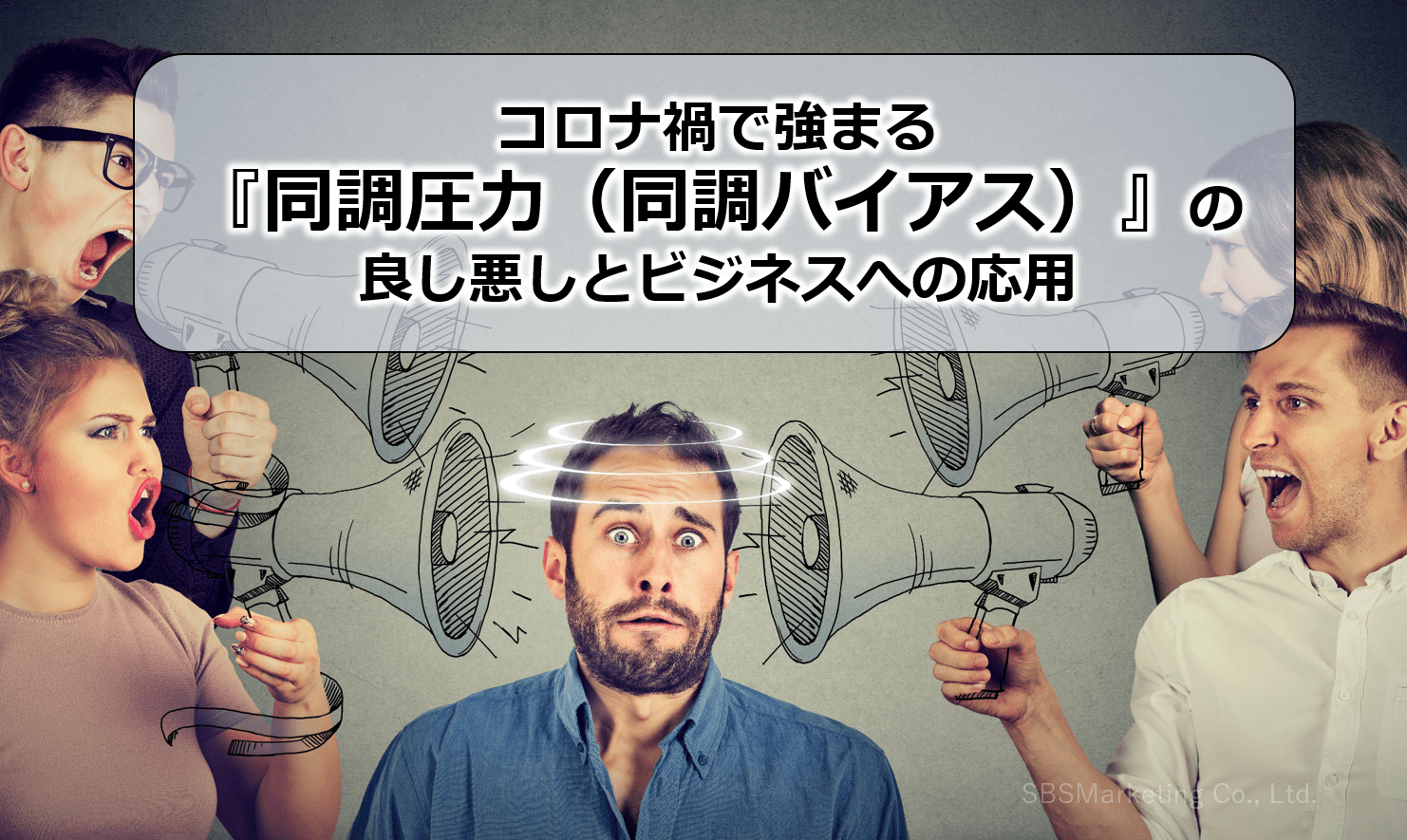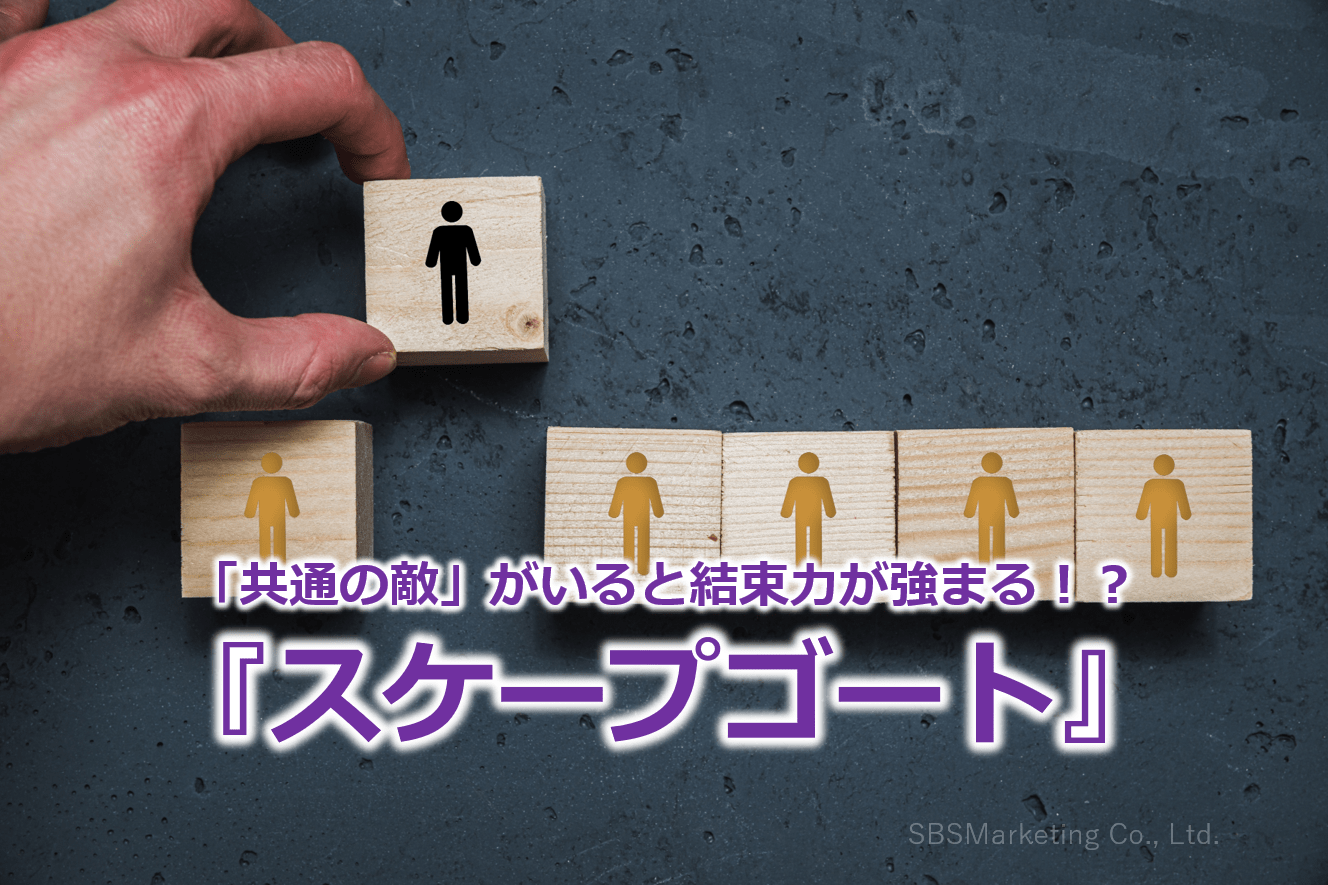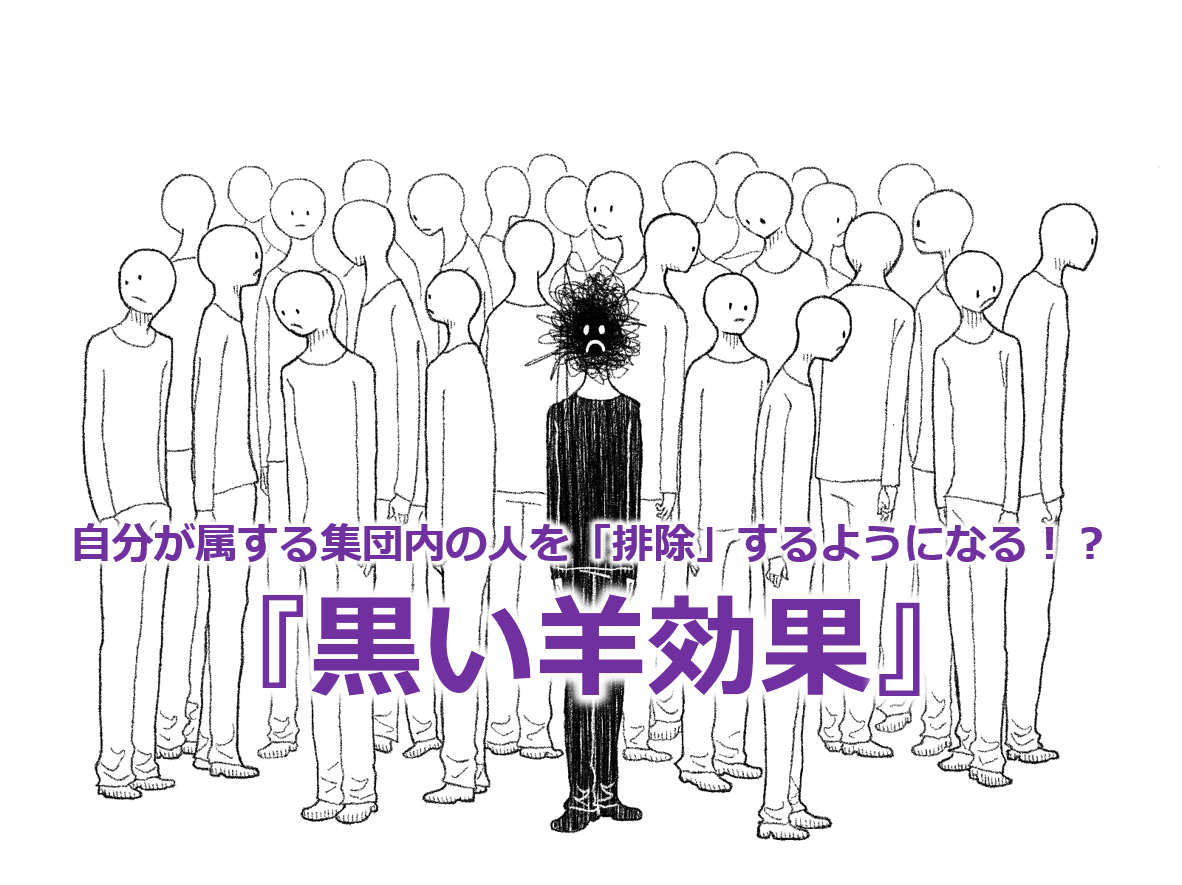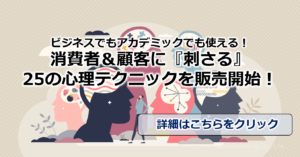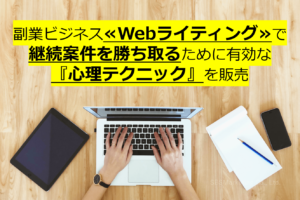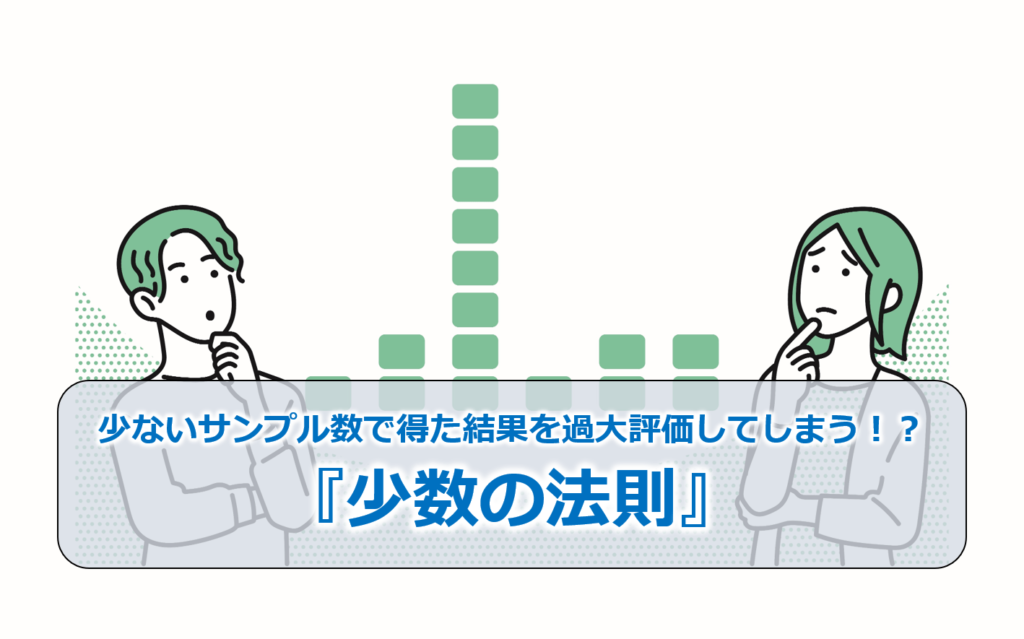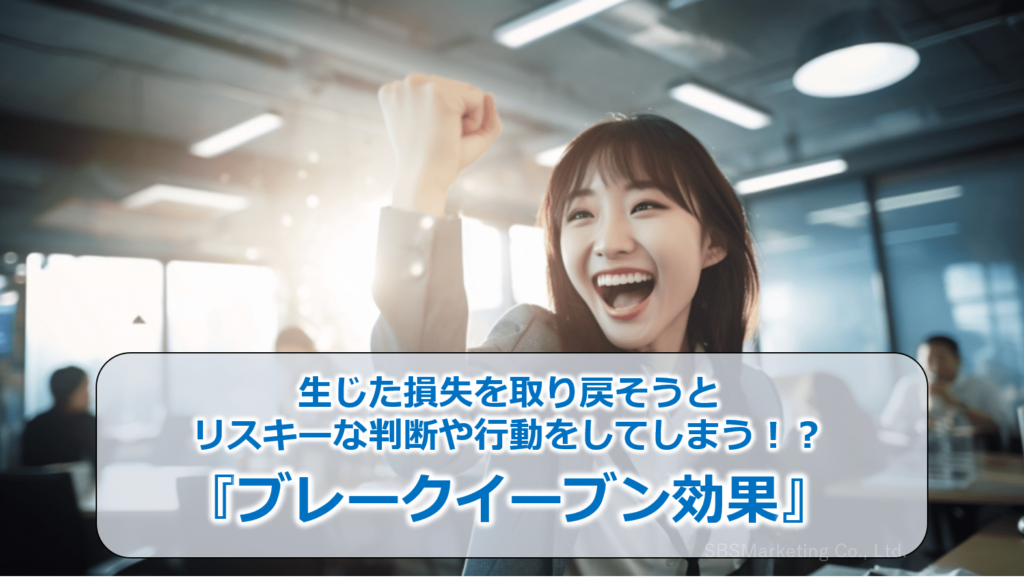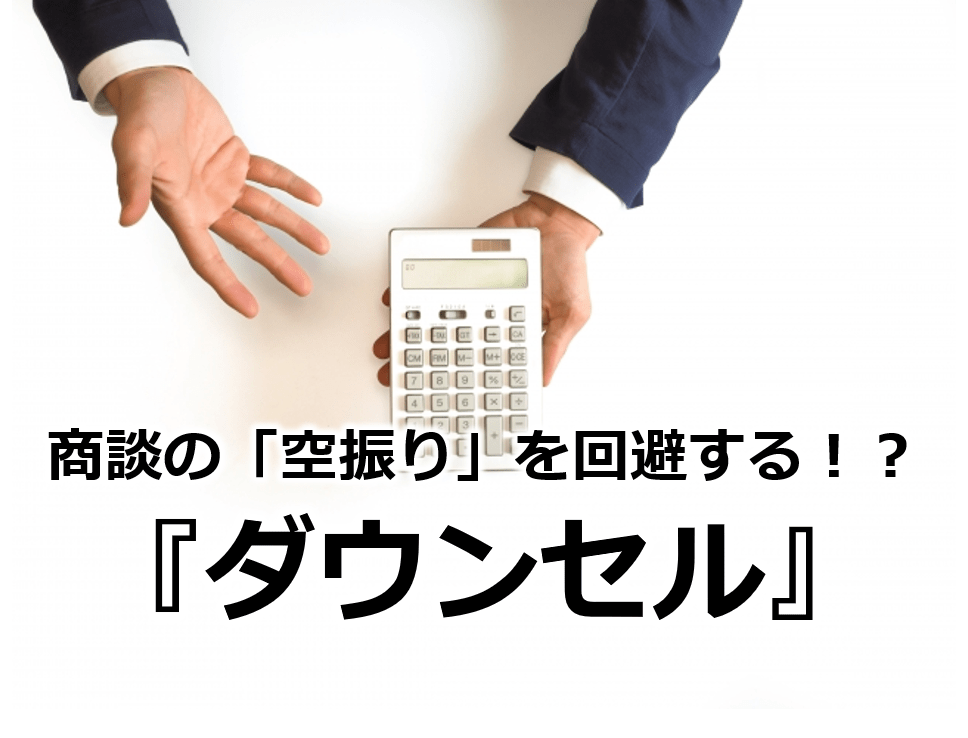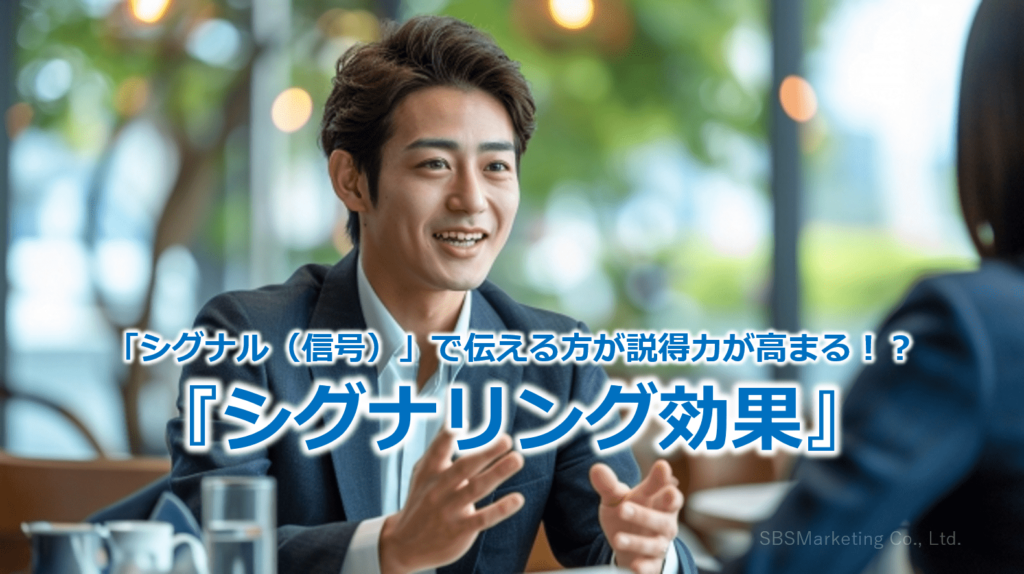「批評家」となって否定的な言動を繰り返し責任は回避するようになってしまう『批評家現象』。
「批評家」がいることによって生じる悪影響、なぜ「批評家」になってしまうのか、『批評家現象』を解消する方法などについて解説しています。
『批評家現象』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『批評家現象』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
身近に「批評家」になっている人、いませんか?

職場などにこんな人、いませんか?
- 会議で文句ばかり言って「マウント」を取りたがる。
- 文句ばかり言うクセに、責任を負おうとはせず「言いっ放し」。
- 新しい取り組みに対して批判的。リスクばかり気にする。
- 自身が抱える問題の解決案を提案されると、「じゃああなたがやって」と他人任せ(無責任)になる。
- 些細な出来事をまるで「大事件」のように騒ぎ立てる。

社内の会議やミーティングの場で、文句や否定的な発言が多い。
新しい取り組みを提案されても、リスクがあることを執拗に言及したり「重箱の隅」をつつくような揚げ足ばかり取る。そして代替案を提示することもない。
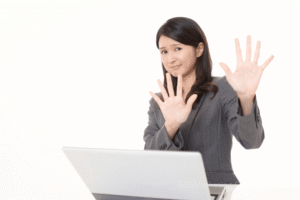
また、自分が問題提起したことに対して、誰かが解決策や対応策を提示しても、自身が責任を負うことを回避してその発言者に問題の解決をなすり付けようとする。
さらに、社内外の些細な出来事を「火の無いところに煙を立てる」ように、大事件のごとく吹聴し、余計に問題視しようとする。
こんな、「批評家」となって否定的な言動を繰り返し責任は回避する人のことを、『批評家現象』と呼んでいます。
「評論家」と「批評家」の違い
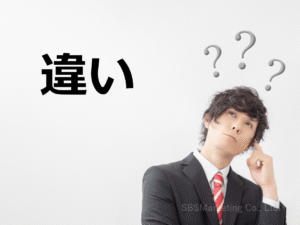
余談になりますが、「評論家」と「批評家」の違いは以下の通りです。
- 評論家:否定的な意見も肯定的な意見も述べる。
- 批評家:否定的な視点から意見を述べることが多い。

「評論」とは、特定の物事や分野について、価値や善悪、優劣などを考察して論じる、という意味です。
一方、「批評」とは、特定の事象の良し悪しや善悪を判断する、という意味ですが、「批判」という言葉と同義として扱われることから、「否定的なニュアンス」が強い傾向があります。
つまり、「評論家」は自身の意見を述べることに重きを置き、「批評家」はポジティブな点よりもネガティブな点を指摘する傾向があるということです。
『批評家現象』によって生じる悪影響
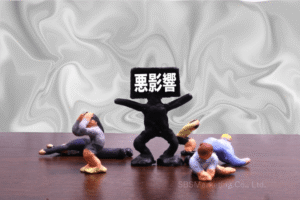
「批評家」となって否定的な言動ばかりを繰り返し、責任は回避するようになる『批評家現象』が生じることによる、ネガティブな影響は以下の通りです。
- 『代案なき批判』が横行してしまう
- 議論が停滞してしまう
- 「不合理な決定」に着地してしまう
- 「負のタスクリレー」が起こってしまう
- 激しい責任追及を受けやすくなる
『代案なき批判』が横行してしまう

否定的な意見だけでなく肯定的な意見も述べる「評論家」とは異なり、否定的な意見ばかり述べるようになる『批評家現象』。
この現象に陥ってしまうと、多くが上から目線で「批評家」を気取り、これといった対案・代案を提示することなく、ただ批判に終始してしまいます。
特にビジネスにおいて、(具体的でなくとも)代案を出すこともなく「ただ批判」だけするのは建設的でなく、「仕事人」としての責任感が欠如していると言えますが、横行しやすくなってしまうのです。
※『代案なき批判』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
出稿した広告効果が起用したタレントや類似した競合商品・サービスに向かってしまう『ヴァンパイア効果』。この広告効果の発生事象や発生するシーン、発生するリスクを回避する方法について解説しています。
議論が停滞してしまう

議論の場に「批評家」がいることで、ほかの参加者が「傍観者」になってしまい、当事者意識を失い前向きな言動をしなくなってしまいます。
この「傍観者」になってしまう現象は『傍観者効果(バイスタンダー・エフェクト)』と呼ばれています。
※『傍観者効果(バイスタンダー・エフェクト)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
ある事象に対して参加者や目撃者が多ければ多いほど自身の周囲にいる「傍観者」と同化してしまい、当事者意識を失い率先して行動を起こさなくなる『傍観者効果』。発生することで生じる影響や類似する心理事象、対策方法などについて解説しています。
「不合理な決定」に着地してしまう

仮に「批評家」が社内で権限があり、議論の場に『心理的安全性』が担保されない場合、その「批評家」の声が賛同を得やすくなり、異論を唱えようものなら『同調圧力』によって潰されてしまいます。
すると、参加者の中に『グループシンク(集団浅慮)』が生じやすくなり、不合理な合意形成に着地してしまうことに。
また、参加者の中に経営者や役職者がいて、それらの人物が『裸の王様現象』に陥っていると、より不合理な決定に着地してしまいやすくなってしまいます。
※『心理的安全性』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
就活セミナーのサクラ騒動の背景にある「質問が出にくい」雰囲気。この雰囲気はビジネスシーンでも発生します。特にミーティングの場面を例に、質問が出にくい理由や雰囲気を打破する方法について解説しています。
※『グループシンク(集団浅慮)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
集団で合意形成を図る際に、不合理な意思決定や望ましくない行動が容認されてしまう『グループシンク(集団浅慮)』。陥ることで生じる兆候や発生例、陥ってしまう原因と対策、マーケティング施策への応用例などについて解説しています。
※『同調圧力』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
多数派が少数派に価値観を暗黙的に強制する『同調圧力』。なぜ発生するのか、メリットやデメリット、日本でよく見受けられる理由やビジネスへの応用について解説しています。
※『裸の王様現象』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
日常生活でもビジネスシーンでも起こる『裸の王様』現象。企業で発生すると組織が機能不全を起こし経営は悪化、離職者も増えていくという世に言う『ブラック企業』化してしまいます。なぜ発生するのか、発生を防ぐ方法などを解説しています。
「負のタスクリレー」が起こってしまう
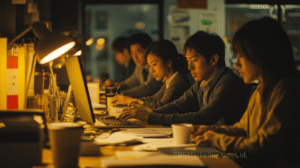
「批評家」の意見が多くの賛同を得て、道理を得ない合意形成がなされると、やらなくてよい業務が無理やり増やされ、時には「プロジェクト」化されて進捗を厳しく管理されてしまうことになってしまいます。
「批評家」が存在することで、やる必要のない業務が発生しプロジェクト化する「負のタスクリレー」が発生してしまう、というわけです。
激しい責任追及を受けやすくなる

例え「不合理な決定」とはいえ、責任者が集まるミーティングで決まったことなので、本来はやる必要のない「負のタスク」を進めることになります。
その中で何かしらのネガティブな結果が出たり状況になってしまうと、『批評家現象』に陥った人物が「そうなると思った」「だから言ったのに」とあたかも知っていた・予測が可能だったと指摘するようになる『後知恵バイアス』が生じやすくなってしまいます。
すると、やる必要のない業務を抱えつつ、ネガティブなことが起これば責任追及を厳しく受けるなど、劣悪な業務環境となってしまい、だんだんと仕事に対するモチベーションは下がり、退職者も続出することに。
※『後知恵バイアス』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
結果が起きた後に、あたかも知っていたと認識したり、予測が可能だったと当初の考えを修正する『後知恵バイアス』。発生例や発生することによる弊害、発生する要因や抑制する方法などについて解説しています。
なぜ「批評家」になってしまうのか?
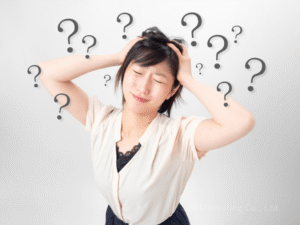
ただ単純に当人が「ひねくれている」ケースも考えられますが、それ以外に「批評家」になってしまう原因を挙げると、以下のようになります。
- 保守的な思考によって「変化を嫌う」
- 「優位に立とう」として揚げ足をとる
- 「他責思考」が強い
- 「危機感」が無い・足りない
- 『シーライオニング』という嫌がらせ
- 「ヒマ」「退屈」だから
保守的な思考によって「変化を嫌う」
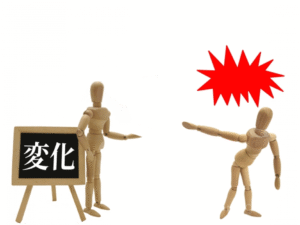
リスクをとって失敗した際に責任を負いたくない、個人として地位を守りたいなど、自己都合の保守的な理由から「評論家」になるというケース。
「優位に立とう」として揚げ足をとる
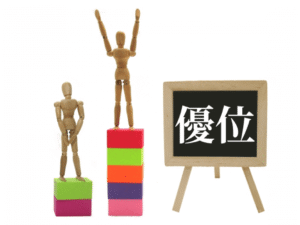
「人よりも優位に立ちたい」という心理傾向が強く、自分ではない誰かが優れているように見える時には、「重箱の隅をつつく」ような揚げ足を取ることで、自身の優位性を保ちたいと考えるケース。
「他責思考」が強い

何か問題やトラブルが発生した際に、その原因を自分以外の誰かや環境にあると考える「他責思考」。
自分ではなく周囲の人や環境が悪いと考える思考は「批評家」になる大きなきっかけになります。
「危機感」が無い・足りない

自身が置かれた立場などに危機感が無い、もしくは足らない人ほど、「批評家」になって否定的な言動をしやすくなります。
『シーライオニング』という嫌がらせ
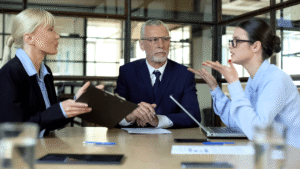
議論をするつもりが無いにも関わらず、相手に説明を求めて疲弊させる行為を意味する『シーライオニング(Sealioning)』。
言葉遣いは丁寧に聞こえたとしても相手の話を聴くつもりがない、自身が望む答えが返ってこないと舌打ちしたり曲解してしまったりすることが特徴です。
この『シーライオニング』という、建設的な議論をしたり相手の話を理解しようとするわけではなく、ただ説明させて疲弊させようとする「嫌がらせ」を目的として「批評家」になるケースも考えられます。
「ヒマ」「退屈」だから

人間は「ヒマ」であるほど余計なことに頭を巡らせるようになります。
そして、その巡らせた思考を行動に移し、退屈を埋めようとします。
この「ヒマ」や「退屈」というのは非常に厄介で、『批評家現象』を引き起こすほかにも、自身が属する集団内に「生贄=黒い羊」となる『スケープゴート』を生み出して、仲間外れや排除したりするようになる『黒い羊効果(ブラックシープ効果)』を生じさせやすくなってしまいます。
※『スケープゴート』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
団結力を高めるために「共通の敵」や「生贄」というレッテルを貼られ攻撃対象に仕立て上げられる『スケープゴート』。発生例と存在することで生じる影響、生じる原因や対処法などについて解説しています。
※『黒い羊効果(ブラックシープ効果)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。
集団の中で馴染めない人を仲間外れにしたり、同質性から逸脱した人を「異分子」として排除しようとする『黒い羊効果(ブラックシープ効果)』。発生例や発生する原因、黒い羊効果の対象になった時の対応策や黒い羊効果を生じさせない組織づくりのポイントなどについて解説しています。
↓
この続きでは、『批評家現象』を解消する方法などについて解説しています。
ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、
「お問い合わせ内容」欄に『批評家現象』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。
株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。
中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …
個人事業主&フリーランス様サービスはこちら
見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …
お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
- BtoBマーケティング
- グループシンク
- シーライオニング
- スケープゴート
- なぜ批評家になってしまうのか
- バイスタンダーエフェクト
- ヒマ
- ブラックシープ効果
- マネジメント
- 不合理な決定
- 些細なことを大事件のように騒ぎ立てる
- 他人任せ
- 他責思考
- 代案なき批判
- 保守的な思考
- 傍観者効果
- 優位に立とうとする
- 危機感が無い
- 同調圧力
- 変化を嫌う
- 多忙と多動
- 後知恵バイアス
- 心理的安全性
- 批判的でリスクばかり気にする
- 批評家現象
- 批評家現象を解消する方法
- 揚げ足をとる
- 文句ばかり言ってマウントを取りたがる
- 株式会社SBSマーケティング
- 根本的な解決
- 激しい責任追及
- 火の無いところに煙を立てる
- 無責任
- 自責思考
- 裸の王様現象
- 評論家と批評家の違い
- 議論が停滞
- 負のタスクリレー
- 負のループ
- 責任を負おうとはせず言いっ放し
- 退屈
- 重箱の隅をつつく
- 集団浅慮
- 黒い羊効果
マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。
現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。